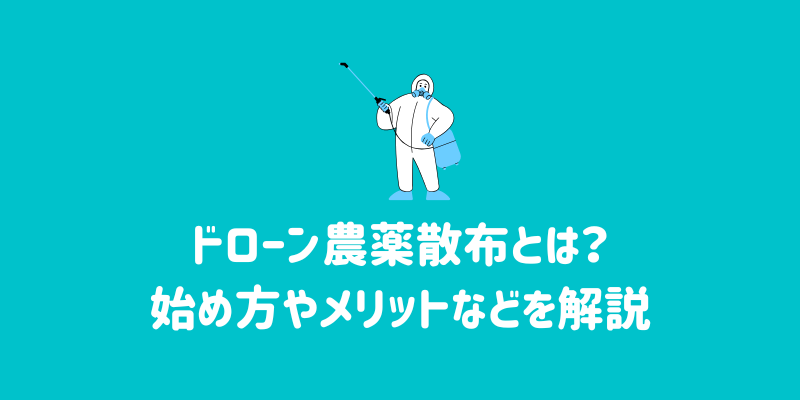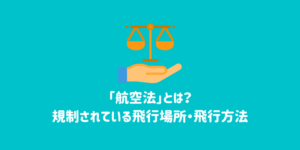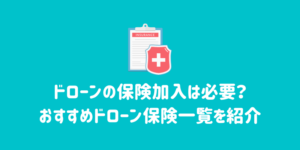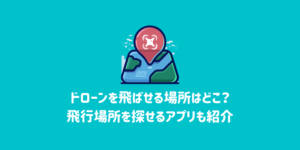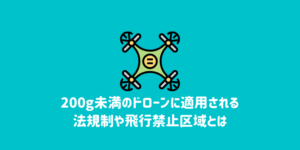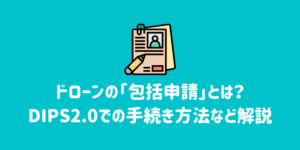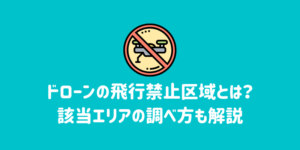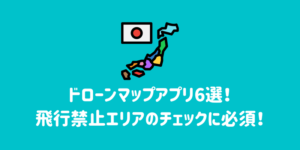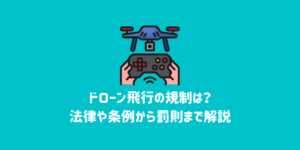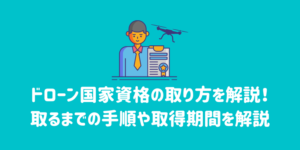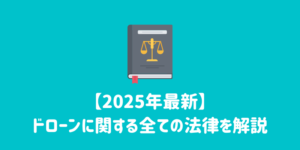農業分野において、ドローンは人手不足解消や作業の効率化など、さまざまな問題の解決に期待を集めています。
代表的なドローンの活用事例としては、機体に農薬を積載して畑などに散布する「農薬散布」です。
今回はドローンを活用した農薬散布のメリット・デメリットや、農薬散布に関わる法規制、農薬散布業務にドローンを導入するまでの流れを詳しく解説します。
ドローンの農薬散布に必要な免許・資格の有無についても記載しているので、ぜひ参考にしてみてください。
- 農薬散布ドローンの活躍の場
- ドローンによる農薬散布のメリット・デメリット
- ドローンで農薬散布する場合に係る法律・規制
- ドローンの農薬散布に必要な免許・資格の有無
- 農薬散布業務にドローンを導入するまでの流れ
農薬散布用ドローンとは
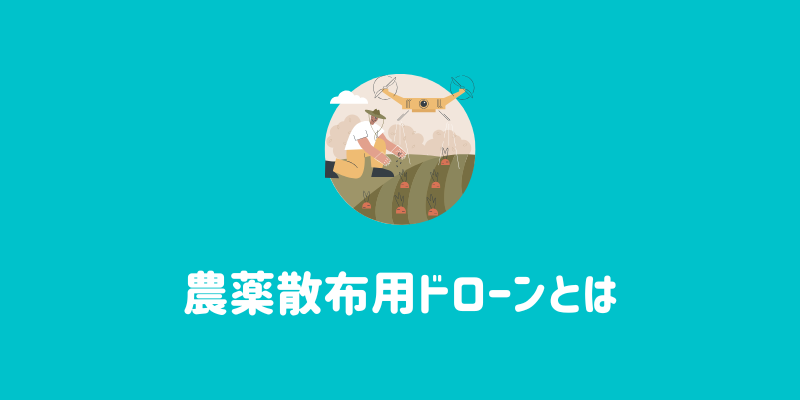
農薬散布用ドローンとは、農薬の積載と散布が可能なドローンで、機体に農薬を入れるタンクを搭載しています。
畑の上を飛行して、散布機から農薬を撒くことで、効率的かつ均質な農薬散布が可能になります。
さらに、農薬散布ドローンは、産業ヘリよりも軽量かつコンパクトなため、1人でも積み下ろしから農薬散布まで行えるのがメリットです。
農薬散布用ドローンが活躍する場所
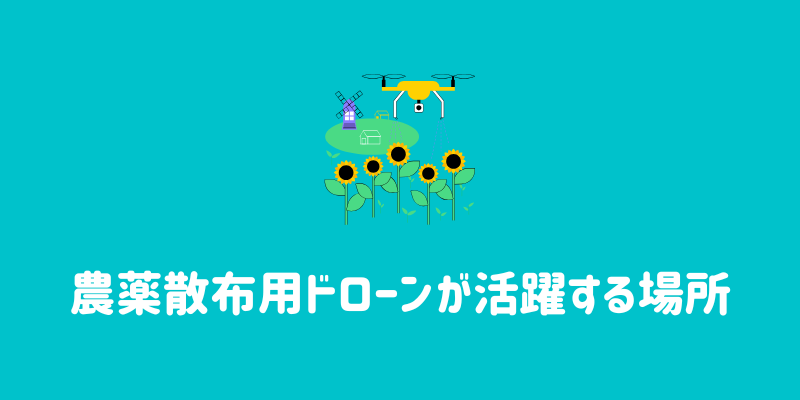
農薬散布用ドローンは、主に以下のような場所で活躍しています。
田畑
農薬散布用ドローンは、田んぼや畑での農薬散布に用いられるのが一般的です。
特に、夏場は炎天下で動噴機械を背負いながら作業をするのは重労働となりますが、ドローンを使えば厳しい気候の日でも、田んぼや畑に入る必要はありません。
また、ドローンは産業用ヘリよりも小回りが効くので、小規模な田んぼや畑でも人の手を使わずに農薬を散布できます。
果樹園
近年はりんごやみかん、ぶどうなどの果樹に対する農薬散布でのドローン活用も期待を集めています。
中国の大手ドローンメーカー「DJI」からは自動で障害物を避けたり、雑草と果樹を見分けたりできるドローンも発表されました。
しかし、国内の果樹園における農業散布ドローンの導入例は、未だ少ないのが現状です。
今後は果樹園にも対応したドローンの普及拡大や技術の進歩によっては、導入する農家も増えていくことが見込まれます。
ドローンで散布可能な農薬とは
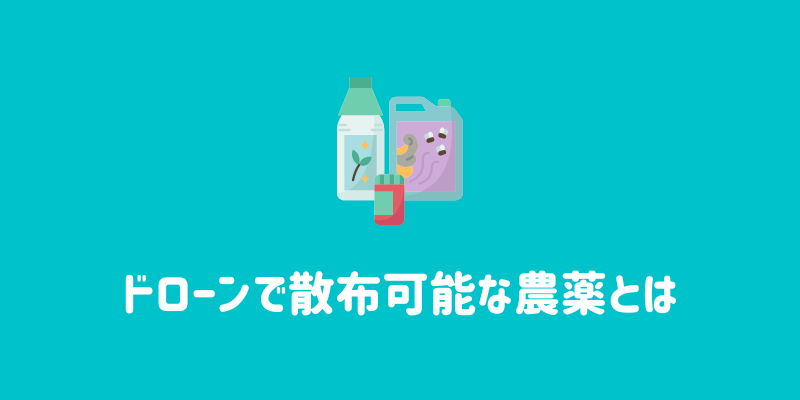
農薬を使用する場合、「農薬登録制度」に従い登録を受けた農薬のみ散布しなければなりません。
農薬登録制度とは、農薬取締法に基づき「基準に従って使えば安全であると判断できる」かどうかを農林水産省が審査・登録する制度のことです。
ドローンで農薬を散布するには、「ドローンに適した農薬」として登録されている農薬を使わなければなりません。
農薬登録制度にて、無人航空機・無人ヘリコプターによる散布または無人航空機・無人ヘリコプターによる滴下の使用が可能とされている農薬がこれに該当します。
現時点で登録済みの「ドローンに適した農薬」は、以下の農薬登録情報提供システムより検索が可能です。
ドローンによる農薬散布のメリット
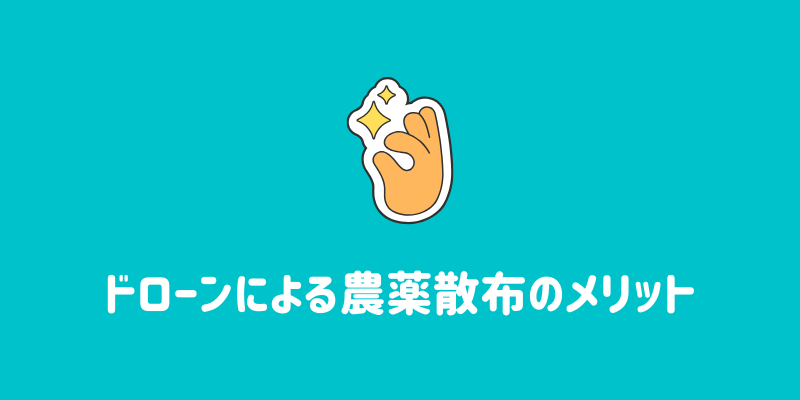
ドローンによる農薬散布のメリットは、以下の4点です。
- 広い面積でも少人数・短時間で農薬散布を行うことができる
- いつでも好きな時に農薬散布できる
- 農薬散布が安全に行える
- 体力に自信がない方でもラクに農薬散布が行える
では、1つずつ詳しくみていきましょう。
広い面積でも少人数・短時間で農薬散布を行うことができる
農薬散布にドローンを用いる上で最大のメリットが、「効率的な農薬散布」です。
人の手で行う従来の農薬散布方法は、時間がかかるだけでなく、圃場の規模によっては人的コストもかかります。
一方、ドローンであればコンパクトなため、機体の積み下ろし・農薬散布・片付けまで1人で行うことが可能です。
機体により速度が異なりますが、概ね1haの圃場であれば10分程度で農薬散布を完了できるため、大幅な時間短縮にもつながります。
いつでも好きな時に農薬散布できる
自身で農薬散布を実施することが難しく、業者に委託をしても「散布予定が決められているので害虫が発生してもすぐに対処できない」「雨が降ると長期延期になってしまう」といった悩みを抱える農家の方も少なくありません。
しかし、ドローンであればどんなタイミングでも適宜散布を行えるため、作物の品質を保つことができます。
農薬散布が安全に行える
ドローンを遠隔で操作して農薬を散布するため、離れた場所から作業を安全に行うことができます。
散布機を使って自力で行う場合、防護服を着用しても農薬に触れてしまうリスクがありました。
ドローンであれば、離れた場所から操縦をして農薬を散布できるため、今まで以上に安全性が増します。
体力に自信がない方でもラクに農薬散布が行える
ドローンは、小型かつコントローラーによる操縦だけで、農薬を散布することができます。
そのため、女性や高齢者など体力に自信がない方でも、作業による体への負荷がかかりません。
農業界で進む高齢化が危惧されている中、高齢者の方も簡単に農薬散布ができるツールであるドローンの存在は、今後も一層重宝されるでしょう。
ドローンによる農薬散布のデメリット
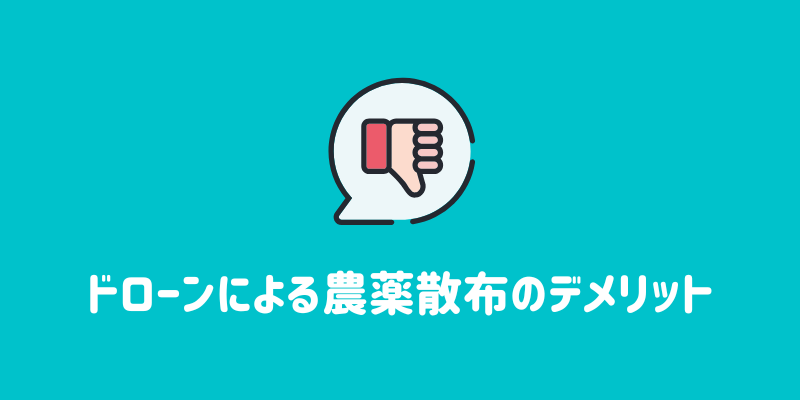
ドローンによる農薬散布のデメリットは、以下の4点です。
- 導入には数百万円の初期投資が必要
- 操縦・ドローンに関する知識が必要
- 申請の手間がかかる
- 使用する薬剤が限られる
メリットだけでなくデメリットも確認しておきましょう。
導入には数百万円の初期投資が必要
農薬散布にドローンを導入する際、様々な初期費用が必要となります。
機体購入の費用だけでなく、ドローンを運用するために必要となる資格取得費用も発生します。
ドローンスクールの受講費用は、100,000円~400,000円程度が相場です。
また、機体を購入するにしても、農薬散布ドローンは1,000,000円以上するものが多く、継続的に運用するには毎年のメンテナンス費も必要です。
操縦・ドローンに関する知識が必要
ドローンを操縦するには、操縦技術はもちろん機体に関わる知識も必要です。。
直接操縦をせずに自動操縦で運用するにしても、PCやタブレットなどの端末操作の知識が求められます。
そのため、そういった機器の扱いに抵抗のある方は、導入が難しくなる可能性があります。
- ドローンを操縦する自信がない
- いざ機器にトラブルが発生した際どうすれば良いか分からない
上記に該当する方は、専用のサポートデスクや農薬散布ドローンの実技講習などを活用しましょう。
申請の手間がかかる
ドローンによる農薬散布は、航空法の規制対象となっている「危険物輸送」や「物件投下」に該当します。
航空法の規制対象である飛行方法を実施する際は、国土交通省へ飛行許可申請を行わなければなりません。
ただし、ドローンの国家資格または国土交通省から認定を受けた団体の民間資格を取得していれば、申請の一部を簡略化することが可能です。
使用する薬剤が限られる
ドローンの農薬散布では、使用できる薬剤が法律によって限られています。
使用する作物や時期など細かい基準が定められており、法律を遵守しながら運用しなければなりません。
ただし、ドローンで使える農薬は拡大されているため、将来的には使える農薬の幅も広がっているでしょう。
おすすめの新型農薬散布用ドローン

農薬散布用ドローンは様々な機体が登場しており、それぞれ異なる性能を持っています。
ここでは、おすすめの農薬散布用ドローンについて性能と共にご紹介いたします。
①DJI/Agras T20 日本版
高い作業効率性と最新の飛行制御技術で、田畑だけでなく果樹園でも運用可能な高性能農業用ドローンです。
耐久性にも優れながら、数秒で折りたたみ・展開が可能な設計により携帯がしやすく、より作業をスムーズに進めることができます。
| メーカー | DJI |
| 価格 | 約160万円 |
| 積載可能容量 | 液剤16L、粒剤16kg |
| 飛行可能時間 | 10分~15分 |
| 散布可能面積 | 7m(散布幅) |
| 機体重量 | 23.1kg |
| 機体サイズ | ・2509×2213×732mm (アーム、プロペラ展開時) ・1795×1510×732mm (アーム展開、プロペラ折りたたみ時) ・1100×570×732mm (アーム、プロペラ折りたたみ時) |
②ヤマハ発動機/YMR-08
産業用無人ヘリコプターの開発・散布事業を通じて、日本の農業現場で防除ノウハウを培ってきたヤマハ製の農業用ドローンです。
パワフルなダウンウォッシュにより薬剤が作物の株元まで届き、前後対称の二重反転ローターでムラのない農薬散布を可能とします。
| メーカー | ヤマハ発動機 |
| 価格 | 約157万円~ |
| 積載可能容量 | 液剤10L、粒剤10kg |
| 飛行可能時間 | 15分 |
| 散布可能面積 | 5m(散布幅) |
| 機体重量 | 24.9kg以下 |
| 機体サイズ | ・2181×1923×669mm (フライト時) ・1799×559(フレーム),573(スキッド)mm (収納時) |
③MAZEX(マゼックス)/飛助MG DX 21年モデル
農業用ドローンの相場としてはリーズナブルな価格、コンパクトながら低燃費でコストパフォーマンスの高さが特徴的な機体です。
また、飛助MG DX 21年モデルは、中山間地での扱いやすさと、導入しやすいコスト設定を前提として開発されています。
オリジナルの飛行制御装置で安全性も高く、初めて農業用ドローンを導入する方にもおすすめです。
| メーカー | MAZEX |
| 価格 | 約55万円~ |
| 積載可能容量 | 5L |
| 飛行可能時間 | 18分 |
| 散布可能面積 | 62.5a |
| 機体重量 | 8.6kg |
| 機体サイズ | ・990×990×548mm (展開時) ・515×585×548mm (収納時) |
④クボタ/農業用ドローン T20K
大容量タンクと広幅散布により、規模の大きな圃場でも効率よく農薬を散布できる機体です。
タンクはカセット式となっているので、薬剤の交換やメンテナンスがしやすいという特徴もあります。
進化した障害物レーダーにより自動飛行時の安全性が高く、タッチパネル式のプロポで操縦も簡単です。
| メーカー | クボタ |
| 価格 | 約204万円~ |
| 積載可能容量 | 16L |
| 飛行可能時間 | 7分 |
| 散布可能面積 | 1.5ha |
| 機体重量 | 22.2kg |
| 機体サイズ | ・1795×1510×732mm (アーム展開、プロペラ折りたたみ時) ・1100×570×732mm (アームとプロペラ折りたたみ時) |
ドローンで農薬散布を行う際に関わる規制や法律とは
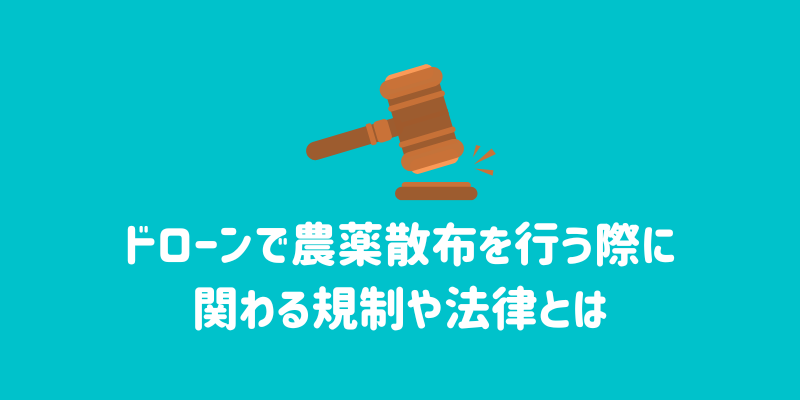
ドローンによる農薬散布は法規制に従って行う必要があります。
ここでは、ドローンで農薬散布を行う際に注意するべき法規制をご紹介いたします。
航空法
屋外でドローンを飛ばす場合、航空法にて様々な場所や飛行方法について制限が設けられています。
以下のような場所・飛行方法に該当するドローン飛行を実施する場合、国土交通省へ飛行許可申請を行わなければなりません。
| 飛行場所 | ・空港等周辺の空域 ・150メートル以上の上空 ・人口集中地区の上空 |
| 飛行方法 | ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・人、物件から30メートル未満での飛行 ・催し場所上空での飛行 ・危険物輸送 ・物件投下 |
農薬散布を行う場合、少なくとも「危険物輸送」や「物件投下」に該当するため、国土交通省への飛行許可申請が必要です。
場合によっては「人、物件から30メートル未満での飛行」や「夜間飛行」に該当する場合もあるため注意してください。。
航空法により定められたドローンの規制ルールについては、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらも参考にしてみてください。
農薬取締法
農薬取締法は、農薬を使用する者が遵守するべきルールとして定められた法律です。
「農薬を使用する際は農作物や人畜などに害を及ぼさないようにすること」などのルールが定められています。
ドローンで農薬散布を行う場合も農薬取締法のルールを守る必要がある他、農薬ラベルに記載されている使用方法を遵守しなければなりません。
特に、ドローンで農薬散布を行う場合、使用方法を遵守しながらドリフトが起こらないようにしてください。
万が一農薬のドリフトが発生した場合、都道府県の農薬指導部局へ報告する必要があります。
「空中散布ガイドライン」の確認も必須
農林水産省が提示している「空中散布ガイドライン」を確認したうえで、散布を行う前に散布計画書を作成することも義務付けられています。
- 散布の実施区域周辺の地理的状況
- 収穫間近の圃場が近接していないか
上記の作業環境を十分に考慮したうえで、以下の次項について記載した計画書を作成します。
- 実施場所・実施予定月日
- 作物名
- 散布農薬名称
- 10aあたりの使用料または希釈倍数
参考:無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
ドローンで農薬散布を行うのに免許や資格は必要?
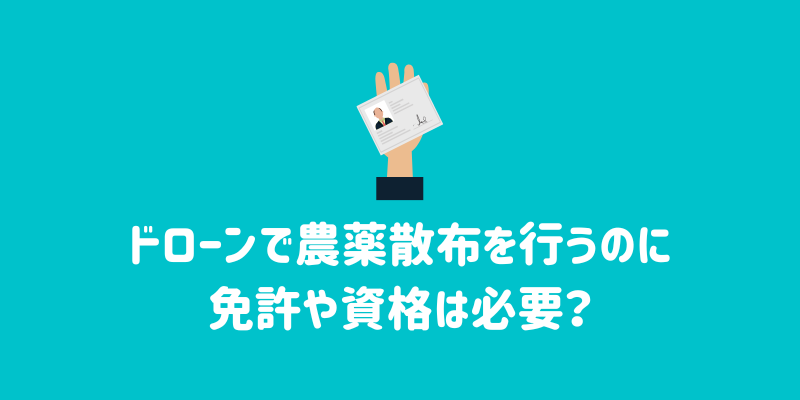
ドローンの農薬散布で取得が必須な免許や資格はありません。
必須ではないが免許(国家資格・民間資格)取得はおすすめ
2022年12月に導入された、ドローンの国家資格は必須ではありませんが取得がおすすめです。
ドローンの国家資格は、「一等資格(一等無人航空機操縦士)」と「二等資格(二等無人航空機操縦士)」の2つの区分があり、取得すると航空法で規制された特定飛行の一部に関して、許可申請が免除されます。
農薬散布においてドローンの免許・資格取得は義務付けられていないものの、許可申請による手間を省けるのは大きなメリットです。
なお、国土交通省から認定を受けている講習機関にて民間資格を取得済みの場合、国家資格取得に必要な試験内容が一部免除されます。
「農薬の散布」の知識は不可欠
農薬散布を行う場合、ドローンを使って薬剤を正しく的確に散布するための知識や技術も必要です。
「農林水産航空協会(農水協)」や「UTC農業ドローン協議会」などの団体では、ユーザーがドローンで正しく安全に農薬散布を行えるように認定教習所にて講習を開催しています。
また、農水協では農業用ドローンの機体性能について安全基準を満たしているかどうかもテストしています。
安全基準を満たしていると認定を受けた機体を扱うには、認定教習所を受講して資格を取得しなければなりません。。
主要なメーカーの農業用ドローンはほとんど農水協認定機となっているため、ドローンによる農薬散布は認定教習所の受講・資格取得が実質必須と認識して良いでしょう。
ドローンでの農薬散布を決定してから農薬散布するまでの流れ
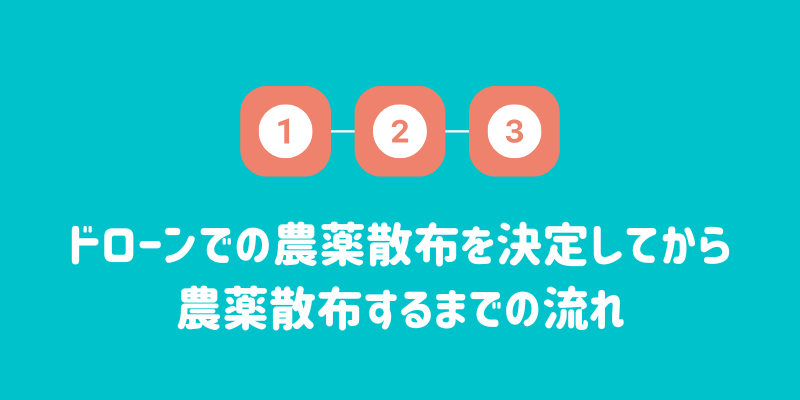
農薬散布にドローンを導入する場合、実際に散布を開始するまでの基本的な流れは以下の通りです。
具体的にどのようなことをすればよいのか、手順ごとに詳しく解説します。
1.農林水産省航空協会認定スクールで講習を受ける
ドローンで農薬散布を行う準備として、「農水協」が認定したスクールを受講し、試験に合格して技能認定を受けてください。
認定スクールは、農水協ホームページの「産業用マルチローター教習施設検索」ページから検索できます。
受講費用はスクールによって異なりますが、200,000円~400,000円程度が相場です。
認定スクールについてはり確認可能です。
2.講習受講終了後、技能認定証を取得
認定スクールにて座学・操縦実技講習を修了した後、技能認定に合格すれば農薬散布ドローン操縦士として資格が与えられます。
「産業用マルチローターオペレーター技能認定証」が交付され、農水協の認定機の操縦が可能になります。
なお、ドローンの機体によって、スクールで習う座学・操縦実技講習の内容は異なります。
そのため、一度技能認定を受けた機体とは別のドローンを運用する場合は、その都度試験を受けて資格を取得しなければなりません。
3.機体購入
農薬散布を行うための機体を購入します。
農薬散布をしたい面積を考慮しつつ、機体ごとに異なる農薬のタンク容量や飛行可能時間などの性能をチェックして選んでください。
また、自動飛行機能が搭載されている機体であれば操縦技術に関わらず安定した飛行ができるため、作業にかかる労力や時間をより削減できます。
4.保険加入
万が一の事態に備えて「ドローン保険」へ加入しておきましょう。
ドローン保険は、大きく分けて以下の2種類に分けられます。
| 賠償責任保険 | ドローン飛行により他人や物へ損害を与えてしまった際の賠償金を補償する保険 |
| 機体保険 | 故障や盗難など、機体そのものが被る損害による修理や捜索などの費用を補償する保険 |
5.国土交通省への許可申請
ドローンによる農薬散布は、少なくとも航空法で規制対象となっている「物件投下」や「危険物輸送」という飛行方法に該当します。
そのため、国土交通省へ飛行許可申請を行わなければなりません。
飛行許可申請は国土交通省ホームページより専用のフォーマットをダウンロードして紙面で提出するか、オンライン申請サービス「DIPS2.0」を使います。
飛行許可申請の具体的な手順は以下の記事で解説していますので、初めて申請を行う方は参考にしてみてください。
ドローンで農薬散布する際の注意点
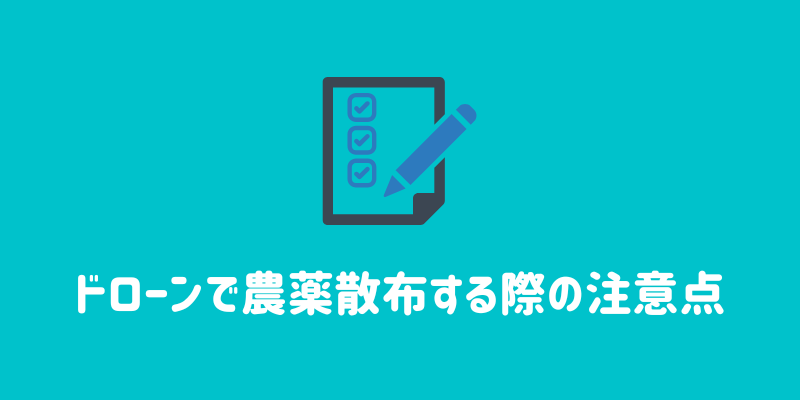
ドローンで農薬散布する際の注意点は以下の6点です。
- 必ず近隣住民へ周知しておく
- 飛行経路は周辺の環境に考慮して設定する
- ドリフトの防止策を十分に講じる
- 農薬から体を保護するための装備も忘れない
- 作業中は補助者を配置するor立入管理措置を行う
- 事故が発生した場合の対応を確認する
操縦ミスによるトラブルや、近隣住民へ思わぬ被害を発生させないためにも、注意して農薬散布ドローンを運用しましょう。
必ず近隣住民へ周知しておく
ドローンによる農薬散布の前に、まず近隣住民へ以下の点について周知してください。
- 農薬を散布する日時
- 使用する農薬の種類
- 農薬を使用する目的
事前の周知は、農薬による近隣住民への健康被害リスクを防ぎ、不要な通報で作業が中断するのも避けられます。
飛行経路は周辺の環境に考慮して設定する
ドローンの農薬散布では、風下から飛行を開始して農薬を散布する「横風散布」が推奨されています。
使用機体の取り扱い説明書などに記されている適切な散布方法に従い、周囲が農薬の影響を受けないように飛行させましょう。
また、以下のように安全性の確認が難しい場所が散布区域に含まれている場合は、より慎重な検討が必要です。
- 学校や病院など公共施設の付近
- 水源地や浄水場、河川の周辺
- 高圧線、発電所、変電所、電波発信施設などの周辺
- 家畜、養蜂、養魚、有機農産物、無農薬作物の生産圃場の周辺
ドリフトの防止策を十分に講じる
ドリフトとは、散布区域外に農薬が飛散してしまうトラブルのことです。
散布区域周辺の地理状況や耕作状況などを十分に考慮しながら、ドリフトが起こらないように十分な対策を講じる必要があります。
ドリフトの防止対策は、主に以下の通りです。
- 空中散布を行わない区域の設定
- 散布薬剤の選定(周囲の農作物にも適用のある農薬、飛散の少ない剤系の粒剤など)
- 近隣に影響が出にくい天候や時間帯の実施(安全な風向きや風が弱い日など)
- 飛行速度は遅く、飛行高度は低くする
- 飛散が少ない散布装置やノズルを選定する
- ドリフトを避けるべき対象に向かった散布は極力避ける
- 散布中の機体の引き起こしや旋回は控える
- 周囲の耕作者に周知のうえ、収穫日時のタイミング変更や作物の保護などを呼び掛ける
農薬から体を保護するための装備も忘れない
農薬は皮膚や粘膜に直接触れると健康被害につながります。
安全性に万全を期すため、遠隔操作をするドローンで農薬散布を実施する場合にも保護装備を必ず用意しましょう。
農薬散布時に必要な装備としては、以下の通りです。
- マスク(農薬用マスク、防塵マスク、保護マスク)
- 保護メガネ
- 防除⾐または長袖の上着と長ズボン
- ヘルメット
なお、マスクや保護メガネに関しては「労働安全衛生法に基づく形式検定に合格していること」「光学性能⾯、耐衝撃性及び耐摩耗性に基づいて作られたメガネであること」などの条件も明示されています。
詳細については、農林⽔産省消費・安全局植物防疫課が公表している以下の資料を参考にしましょう。
参考:無⼈航空機による農薬等の空中散布に関する Q&A (使⽤者向け)
作業中は補助者を配置するor立入管理措置を行う
農薬を散布する範囲に人が立ち入らないよう、補助者を配置したり、立入管理措置を行ったりしてください。
散布範囲に人が入ると農薬による健康被害リスクが生じるため、看板やカラーコーンなどを設置しましょう。
また、立入管理区画は、ドローンの飛行精度や落下範囲などを計算して、余裕を持たせた広さを設定します。
事故が発生した場合の対応を確認する
ドローンによる農薬散布で事故が発生した場合には、適切な対応をしなければなりません。
事故の種類によって、以下のように通報先が異なるため注意してください。
| 機体による事故や紛失 | 地方航空局へ報告 |
| 農薬の紛失・ドリフト等 | 都道府県の農薬指導部局へ報告 |
事故による怪我人などがいる場合には、負傷者の救護を最優先に考え、救急車を呼ぶなどの適切な対応をしましょう。
農薬散布用ドローンの導入にかかる費用
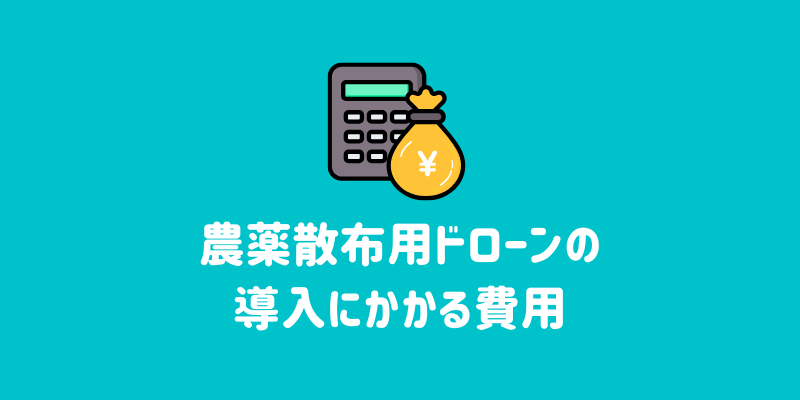
農薬散布用ドローンの導入にかかる費用は、以下の通りです。
| 機体費用 | 50万円〜200万円 |
| スクール費用 | 10万円〜40万円 |
| ドローン保険 | 5万円〜10万円/年 |
| 点検&修理費用 | 6万円〜/年 |
初期費用となる「機体費用」と「スクール費用」に加えて、ランニングコストとなる「ドローン保険」や「点検&修理費用」がかかります。
購入費や維持費に高額なお金がかかるため、導入の際にはよく検討しなければなりません。
農薬散布用ドローンはレンタルや請負サービスでも利用できる

農薬散布ドローンを導入するにも、まとまった資金がなく導入が難しいという場合は、レンタルや請負サービスを利用する選択肢もあります。
レンタルで利用する方法
レンタルの場合、ドローンレンタルサービスを利用する形が一般的です。
サービスによって用意されているドローンの種類は異なりますが、農薬散布ドローンをレンタルするのであれば産業用ドローンが充実しているところを選びましょう。
レンタルする場合の価格(値段)相場
農薬散布ドローンのレンタルにかかる費用は、1日当たり「30,000円~50,000円」程度が相場です。
レンタルする日数が多いほど費用が割安となる場合もあるため、料金設定についてよく確認するといいでしょう。
レンタルのメリット
レンタルにおける最大のメリットは、機体を購入するよりも低コストでドローンを導入できる点です。
また、将来的に機体の購入も視野に入れている方で、事前に機能や操作感を試しておきたい方も多く利用しています。
請負サービスに依頼する方法
農薬散布ドローンを導入して、自分で操縦するのが難しい場合、ドローンを活用した農薬散布の請負サービスに依頼するのも可能です。
防除請負業者だけでなく、農薬散布・測量・点検・空撮など幅広い分野の業務をドローンで遂行する請負業者も増えています。
請負してもらう場合の価格(値段)相場
農薬散布の場合、作業料金は散布が必要な面積に応じて変化します。
相場としては、「10aあたり1,500円~2,000円」程度です。
請負のメリット
農薬散布請負サービスを依頼すれば、自分がドローンを操縦せずに農薬散布を行えるため、ドローンに関する操縦技術や知識を身に付ける必要はありません。
機体の購入やスクール受講費、ドローン保険の保険料といった費用もかからないため、低コストで農薬散布が行えます。
ただし、自分で操縦ができない以上、好きなタイミングで農薬を散布できない点に注意が必要です。
農薬散布ドローンを自分で運用するか請負会社に依頼するか迷ったら
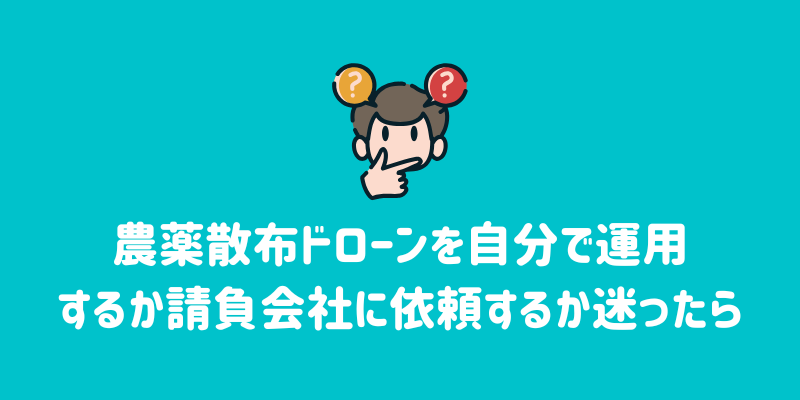
自分でドローンを運用して農薬散布をするか、請負会社に代行を依頼するか判断するうえで重要なポイントは「作地面積の広さ」です。
作地面積から判断する方法
例えば、55万円の農薬散布ドローンを購入のうえ運用する場合と、10aあたり1,500円の請負会社に年3回の散布を依頼する場合で比較してみましょう。
| 作地面積 | 自分で運用(購入費用) | 請負会社(1,500円/10a) |
|---|---|---|
| 4ha | 550,000円 | 180,000円/年 |
| 2ha | 550,000円 | 90,000円/年 |
作地面積が4haの場合、請負会社を利用する年間コストは18万円で、自分で運用する場合のドローン購入費用の3年分となります。
作地面積が2haでは、請負会社を利用する年間コストは、自分で運用する場合のドローン購入費用の6年分となり、回収コストが変わってきます。
ドローンの運用年数や作地面積の広さを考慮しながら、ドローンを購入するかどうかを決めるといいでしょう。
安く依頼したいなら農協への問い合わせもおすすめ
ドローンによる農薬散布の代行サービスは、民間の請負会社だけでなく農業協同組合(農協)からも提供されています。
従来の農協で依頼できる空中散布と言えば、ヘリコプターを用いた方法でしたが、ドローンを導入する農協が増えています。
ただし、すべての地域の農協でドローン農薬散布が普及しているわけではないため、まずは管轄の農協に確認してみましょう。
農協によるドローン農薬散布の代行サービスは民間の請負会社よりも料金が安い傾向にあるため、低コストで代行を依頼したい方におすすめです。
農薬散布用ドローンを自作(DIY)することはできる?
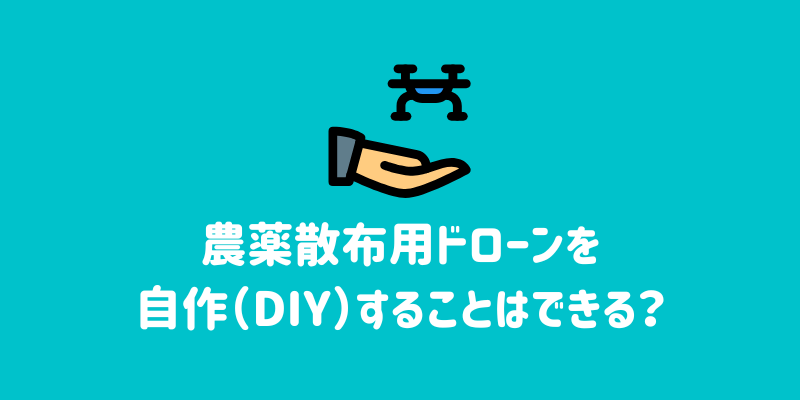
工学など機器のDIYに関する専門知識がある方であれば、農薬散布用ドローンを自作できます。
空撮用やレース用のドローンを自作のうえ使用しているユーザーは多く、以下のような必要なパーツさえ揃えれば自作は可能です。
- フレーム
- フライトコントローラー
- モーター、スピードコントローラー
- プロペラ
- バッテリー
- 受信機
- プロポ
農薬散布用ドローンは、上記に加えて農薬を積載するためのタンクも必要です。
また、農薬を積載しながら飛行するために相応のパワーも備えていなければなりません。
フレームやモーターは25kg程度の重量に耐えることができるものを選びましょう。
農薬散布用ドローンを自作するなら「組み立てキット」がおすすめ
1から必要なパーツを自分で集め、組み立てるには手間がかかるため、最初から必要なパーツや組み立て説明書が揃っている「組み立てキット」で自作するのがおすすめです。
完成品の機体よりも安く販売されているため、上手く組み立てれば低コストで農薬散布用ドローンを導入することが可能です。
農薬散布用ドローンを自作する際の注意点
農薬散布用ドローンの組み立てキットは、低コストなのが魅力ですが、商品によっては説明書がなく、写真だけを頼りに組み立てなければならないケースもあります。
その他にも、組み立て時に不明な点や不良品などが見つかった場合のサポート体制が整っているのかをよく確認しておきましょう。
また、農薬散布前に必要となる国土交通省への飛行許可申請の際、自作ドローンを使用する場合は、機体の安全性を保障する資料を添付しなければなりません。
完成品のドローンよりも申請が複雑になる可能性があるため、自信のない方はドローンの自作を避けてください。
ドローンで農薬散布を行う際のよくある質問
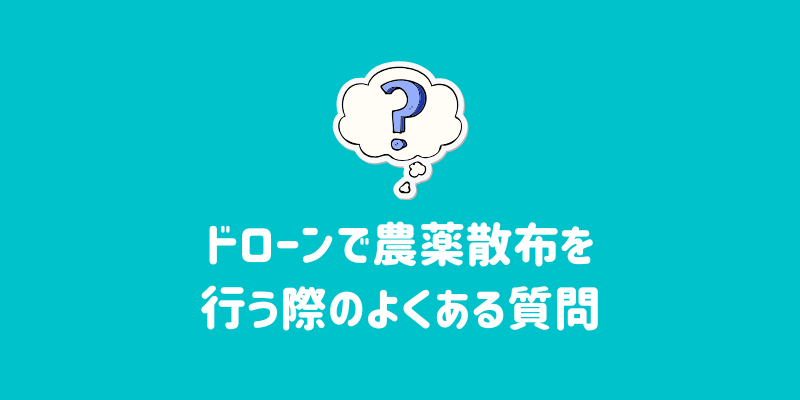
最後に、ドローンによる農薬散布についてよくある質問を回答と一緒にまとめました。
ドローンで散布できる登録農薬はどこで確認できる?
登録農薬は、農林水産省が提供している「農薬登録情報提供システム 」にて確認可能です。
農薬名・作物名・病害虫・有効成分など様々な項目から検索できるので、上手に活用してみましょう。
低価格の農薬散布用ドローンはある?
農薬散布ドローンの価格相場最低ラインである100万円を切る機体では、マゼックスの「飛助mini」やFLIGHTSの「FLIGHTS-AG V2」などが有名です。
より安く機体を入手したい場合は、中古品の購入やレンタルサービスの利用を検討しても良いでしょう。
農薬散布用ドローンのメーカーで有名なところは?
農薬散布用ドローンを提供しているメーカーでは、特に「DJI」や「クボタ」、「ヤマハ発動機」は農業の現場でも名前が挙がることが多いです。
各メーカーの特徴としては、以下の通りです。
| DJI | 世界最大のシェア率を誇る中国の大手ドローンメーカー。 農薬散布ドローンに関しては、大容量タンクや全方向デジタルレーダー、マルチスペクトルカメラなど革新的な機能改良を行い、高性能な機体を開発している。 |
| クボタ | 日本国内において有名な大手農機メーカー。 日本だけでなく世界の農機業界をけん引する存在。クボタの農薬散布ドローンはDJIを製造元としており、OEMに近い形で販売している。 全国のクボタグループ販売店を通じたアフターサービス体制が充実している点も特徴。 |
| ヤマハ発動機 | オートバイなどの輸送用機器製造メーカーとして有名な企業。 長年にわたる産業用無人ヘリコプター開発で培われたノウハウを活かした自社製品ドローンを販売しており、他社ドローンよりも優れた耐久性やパワフルなダウンウォッシュが特徴。 |
ドローンによる農薬散布と地上散布に効果の違いはある?
ドローンを使うことで、決められたルート上に一定のペースで農薬を散布することができるため手作業での地上散布よりもムラなく作物に農薬が届きます。
さらに、ドローンは1分間で約10aのペースで農薬を散布するため作業時間の大幅な短縮にも可能です。
ドローンの農薬散布に必要な免許・資格はある?
ドローンを飛ばすだけなら、免許・資格の取得は必須ではありません。
ただし、安全性の高い農水協認定機の農業用ドローンを使う場合は、農林水産省航空協会認定スクールを受講のうえ資格(技能認定証)の取得が必要です。
また、ドローンの国家資格または国土交通省認定のスクールで取得可能な民間資格を取得しておけば、飛行許可申請の手間を省くことができます。
農薬散布用ドローンの保険料の相場は?
農薬散布用ドローンの場合、メーカー側から機体購入者向けに保険プランを提供している場合も多いです。
メーカーで用意されている保険の場合、保険料は機種により異なりますが年間「30,000円~100,000円」が相場となっています。
農薬散布用ドローンの導入には補助金が出る?
高額な農薬散布ドローンの購入に対して使える補助金もあります。
以下のような補助金を利用すれば、高額な農薬散布ドローンの導入ハードルも下げられるでしょう。
| 経営継続補助金 | 新型コロナウイルスの影響を受けている農林漁業者が、感染拡大防止対策を行いながら販路や生産などの経営を継続していく取り組みを支援するための補助金制度。 「常時従業員数が20人以下の農林漁業者(個人・法人)」が支給対象。 |
| ものづくり補助金 | 中小企業や小規模事業者が申請可能な「ものづくり補助金」や地方自治体が独自に実施している補助金制度もある。 |
農薬散布用ドローンはどこで販売されている?
新品の農薬散布ドローンは、各メーカーの専門店や特約店、オンラインストアページなどから購入可能です。
また、講習と同時に機体の販売を行っているドローンスクールもあります。
中古品の場合は「ヤフオク」などのフリマサイトから購入可能です。
状態が良いものを新品よりも安く入手できるというメリットがありますが、整備が不十分で購入後すぐに故障してしまう可能性があるというリスクも潜んでいます。
中古品を購入する際は出品者や機体の状態などの情報を確認しながら慎重に選びましょう。
農薬散布用ドローンの新品・中古価格相場とは
農薬散布用ドローンの相場は以下のようになっています。
- 新品の価格相場:100万円〜300万円程
- 中古品の価格相場:50万円~100万円
機体によっては、新品でも100万円を下回る場合もあります。
しかし、タンク容量が5Lのみなど比較的小規模な圃場での使用に適しているタイプが多いです。
タンク容量が多かったり、機能が充実している機体ほど価格も高くなる傾向にあります。
まとめ
農薬散布にドローンを活用すれば、短時間かつ高効率での作業が可能になります。
人手不足や高齢化が問題視される農業分野において、ドローンはより一層注目される存在となるでしょう。
ドローンの操縦に関して、取得必須な免許や資格はありませんが、農薬散布を行う場合は技能認定証の取得が必要です。
農薬散布にドローンの導入を検討している方は、今回の記事を参考に必要な準備を整えて是非ご自身の業務に活かしてみてください。
この記事と一緒によく読まれている記事
-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント
-
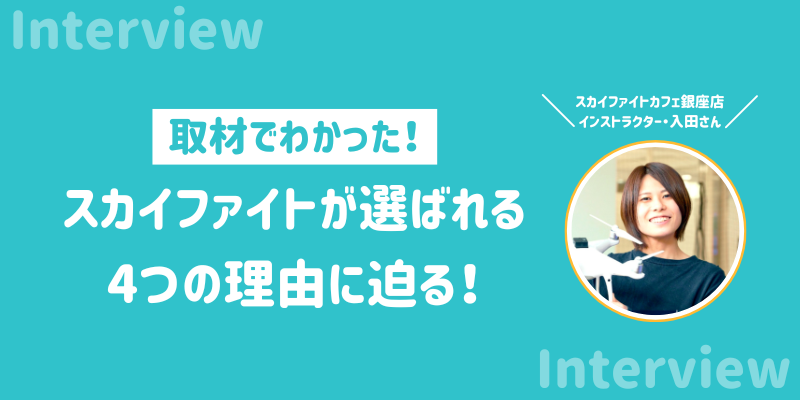
オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由
-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング
-
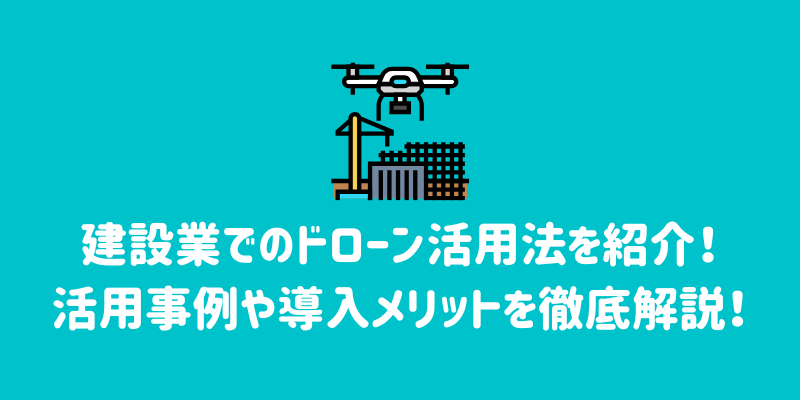
建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!
-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!
-
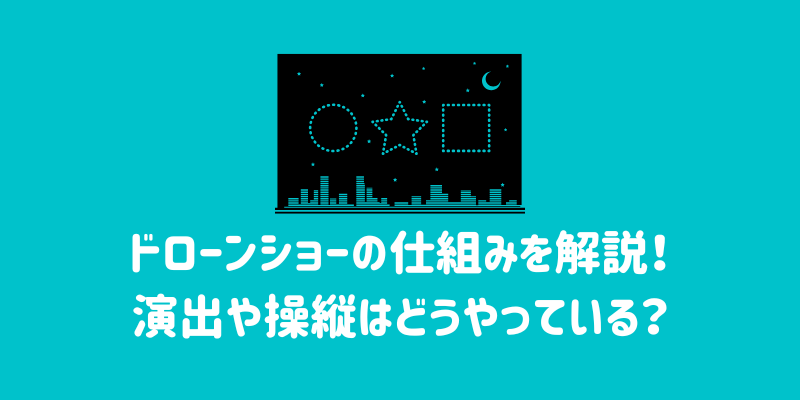
ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?
-
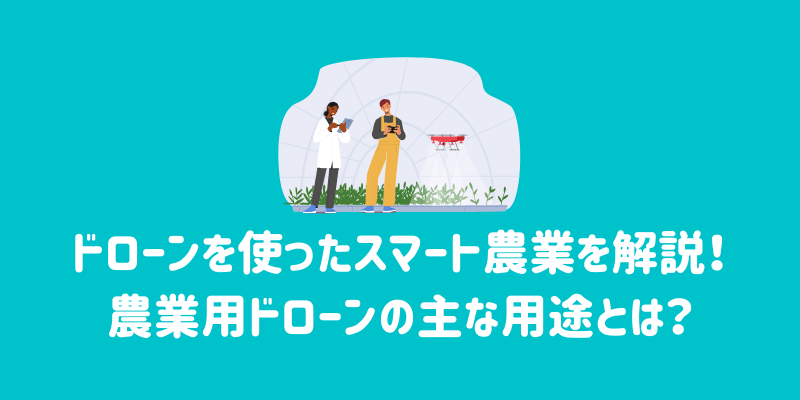
ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?
-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる
-
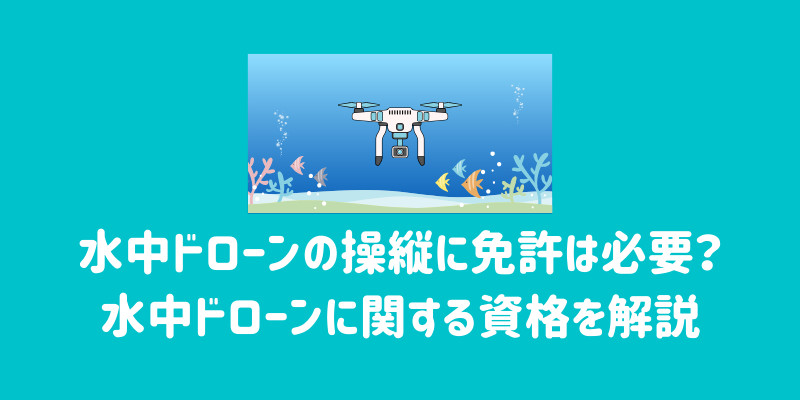
水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説
-
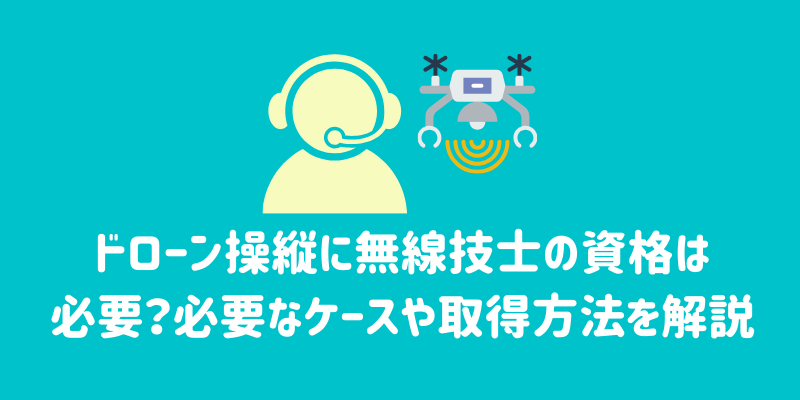
ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!
-
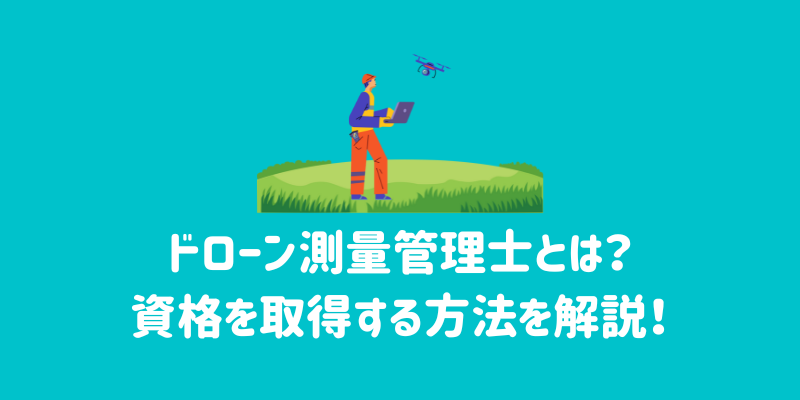
ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!
-
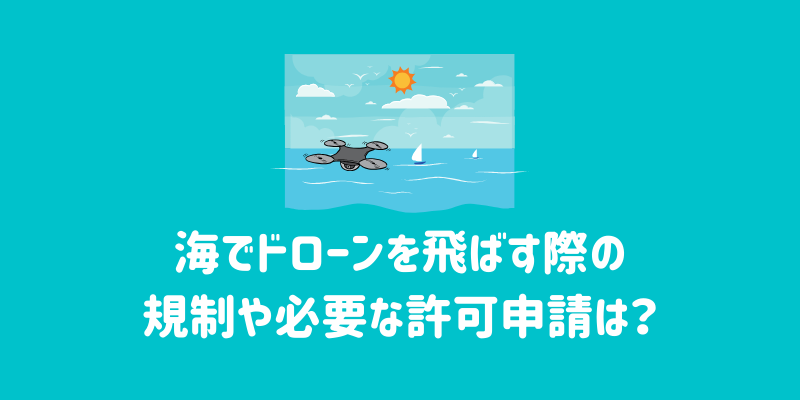
海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説