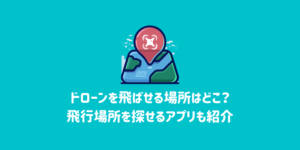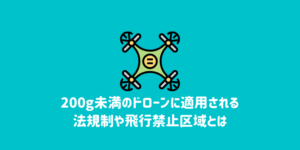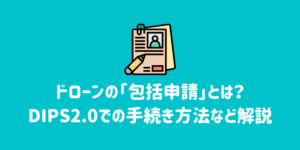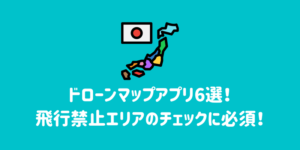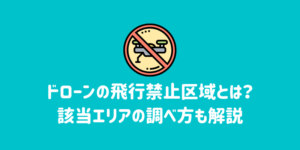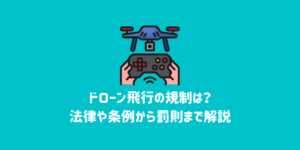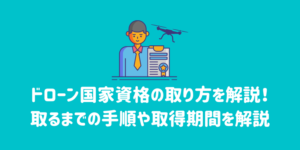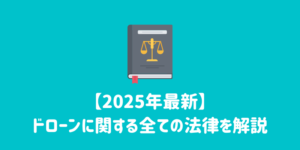ドローンの普及にともなって「趣味でドローンを飛ばしたい」「世界中の綺麗な景色を空撮してみたい」「将来、ドローンを使った仕事に就きたい」など、さまざまな夢を持つ人が増えています。この記事では、ドローンを飛行させるために免許や資格が必要なのかといった基礎知識から、おすすめの認定資格や、ぜひ取っておきたい国家資格まで徹底解説します。
ドローンを飛行させる際に知っておくべき法規制について
ドローンの飛行に関して、現在さまざまな法規制が定められています。飛行時にはそれらをしっかりと理解・把握しておかなければなりません。
2015年4月22日、東京都千代田区にある総理大臣官邸の屋上にドローンが墜落しているのが発見され、大きなニュースとなりました。以来、ドローンに関する規制が次々と誕生しています。まずは代表的な法律を見ていきましょう。
航空法
上記の総理大臣官邸の屋上にドローンが墜落しているのが発見された事件以降、急ピッチで航空法の改正が行われています。2015年以降に改正された内容を見ていきましょう。
2015年12月の改正
2015年12月に施行された改正航空法では、バッテリーを含めた機体重量が200gを超えるドローンについて、次の空域で飛行させる場合は、事前に地方航空局長や空港事務所長の「許可」が必要であると定めています。
1 空港等の周辺の上空の空域
2 人口集中地区の上空
3 地表や水面から150m以上の高さの空域
また、次のルールによらないケースでドローンを飛行させる場合は、地方航空局長の「承認」が必要になります。
1 日中(日出から日没までの間)に飛行させること
2 目視できる範囲内でドローンとその周囲を常に監視しながら飛行させること
3 第三者または物件(建物・自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4 祭礼や縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5 爆発物など危険物を輸送しないこと
6 ドローンから物を投下しないこと
航空法および、許可や承認の手続きについては、国土交通省のホームページに詳しく書かれています。ぜひとも目を通しておいてください。
2019年6月の改正
さらに、2019年6月13日に改正航空法が可決され、成立しました。
この法令改正において、200グラム以上のドローンなどの無人航空機に対しての安全対策に関する事項についても変化しました。
具体的には、以下の点について強化された形となっています。
1 アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2 飛行前確認を行うこと
3 航空機又は他のドローンとの衝突を予防すること
4 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
この中で、特筆すべきはアルコール又は薬物等の影響下で飛行させないという項目です。
法改正によって追加されたアルコール又は薬物等の影響下という点については、アルコールとはアルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指しています。
アルコールによる影響は、個人の体質やその日の体調によって大きく異なります。
体内のアルコール濃度の程度にかかわらず、体内にアルコールを保有する状態において無人航空機の飛行を行ってはならないという事を意味しているのです。
また、薬物とは麻薬や覚せい剤などの規制薬物に限った話ではなく、医薬品も含まれます。
良くある話として、風邪薬を飲むと眠くなるという症状がありますが、この眠気が発生した状態で操作をしてはいけないという事になります。
飲酒時の操縦禁止では、国土交通大臣の承認の対象とはならず、遵守が求められ、承認による例外は認められません。
2020年・2021年の改正
2020年から2021年にかけては、大きな改正案が成立しました。
大きく、以下の4つの制度内容が変更となります。
・機体認証制度
・操縦ライセンス
・運行管理のルール
・所有者の把握
現時点では、法律が成立したのみです。施行は2022年以降が予定されているため、今後の動きに随時注目しておく必要があるでしょう。
小型無人機等飛行禁止法
2016年3月に公布された法律で、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所といった国の重要施設から原子力事業所、外国公館等といった施設の周囲おおむね300mの地域の上空を飛行してはならないという法律です。ドローンの重量に関わらず規制されているため、注意が必要です。
電波法
Wi-FiやBluetoothでスマホと接続し、撮影したデータを伝送したり、カメラが捉えている映像をリアルタイムに観ることができたりするドローンが増えています。伝送には電波を使いますが、日本では周波数帯によって免許が必要な場合があります。
スマホやWi-Fiで多く使われている2.4GHz帯は免許が不要ですが、1.2GHz帯は「携帯局」、5.7GHz帯などは「携帯局」「陸上移動局」に分類されるため、免許が必要です。特に海外メーカーのドローンを飛行させる場合は、どの周波数帯を使っているのかを事前に確認しておきましょう。
道路交通法
道路交通法では、明確に「ドローンの飛行」を規制している訳ではありません。しかし、第76条において「交通の妨害となるような方法で物を道路に置いたり、通行人や車を損傷させる恐れがある物を投げたりする行為」を禁止しているなど、ドローンも当てはまる項目が複数あります。当然ですが、道路上をドローンの発着場にするといった場合、道路交通法に抵触する可能性が出てきます。
民法
民法も、道路交通法のように明確に「ドローンの飛行」を規制している訳ではありません。しかし、例えば民法207条「土地の所有権」のように、ドローンも関わる可能性がある規定は存在します。土地の所有権には、その土地の上空も含まれます(おおむね300m上空までというのが一般的な見解です)。つまり、他人の土地の上空で許可なしにドローンを飛行させた場合、民法207条に抵触する可能性があるという訳です。
これらのほかにも、重要文化財保護法、個人情報保護法など、ドローンの飛行にはさまざまな法律が絡んできます。国が指定している重要文化財を損傷してしまったり、ドローンに搭載されているカメラで個人のプライバシーを侵害してしまったり(故意かどうかを問わず、個人が特定できる情報が写り込んでしまい、動画共有サイトなどにアップしてしまったケース等)といったことも考えられます。
条例
県や市区町村といった自治体には、独自の条例があります。例えば東京都では、すべての都立公園、庭園でドローンの飛行が禁止されているなど、その地域によって細かく規制されています。法律を遵守していても、自治体の条例に抵触してしまい、何らかの処分を受ける可能性もあるため、自分がドローンを飛行させようと思っている場所の条例は、事前に確認しておくことが大切です。併せて、その施設や土地の管理者、所有者の許可が必要かどうかといったことも確認しておきましょう。
ドローン飛行に関わる規制については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
ドローン飛行における規制とは?法律や条例から罰則まで徹底解説
ドローンを飛行させるのに免許や資格は必要?

「法規制が関わってくるのは分かったけど、ドローンを飛ばすには、車やバイクのように免許や資格が必要?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか?
ドローン飛行の際に義務付けられている免許や資格はない
2021年10月現在、ドローンを飛行させるために取得および習得が義務付けられている免許、資格はありません。つまり、誰でも自由にドローンを飛行させることができます。
なお、現時点ではまだ免許制度化はされていませんが、2022年に免許制度が導入される見込みです。
登録制度、免許制度が導入される背景
先に紹介したとおり、ドローンが誕生して広く一般に普及している中で、2015年からドローン関連の事故発生数が増加しています。
2019年には、警察が摘発したドローンに関する事件が100件を超えるなど、年々発生数が増えているのが実情です。
圧倒的に多いのが、ドローンを無許可で飛ばしたというものであり、その理由として記念撮影、操縦の練習が次に多い摘発となっています。
また、およそ半数が中国人やアメリカ人などの外国人で、日本の法律を知らずに軽い気持ちでドローンを飛ばしてしまうという事案が多いのです。
このような状況下で、登録制度を採用することが重要となっているのです。
登録制度においては、200グラム以上のドローンの所有者が氏名、住所、機体の種類や型式をインターネットで国土交通省へ申請する必要があります。
申請を行うと、ID個別登録記号の通知を受ける事ができます。
IDは飛行運用時に機体にシールなどで表示しなければならず、飛行中は上空から電波で発信することも求められるのです。
これによって、個体識別できるために事故やトラブルに対応しやすくなるというメリットがあります。
また、テロなどの重大犯罪で使用されようとした場合、即座に無許可操縦を見つけ出し、未然防止できることも期待できます。
現時点で免許は必要ないが、正しい知識を身につける必要はあり
現時点で免許は必要ありませんが、それはあくまで「飛行させるため」の免許や資格であり、誰もが「好き勝手に」「どこでも」飛行させられるという訳ではありません。
前述したように、航空法で規制されていたり、各自治体が定めている条例によって規制されていたりします。ドローンを飛行させる前に、ドローンを規制している法律や条例を、しっかり身につけておく必要があります。
正しい知識を身につけるために、ドローンスクールへ通ったり、認定資格取得を目指すのも一つの手です。
免許制度運用直前に資格を取得する意味はある?
免許制度がスタートするのは間違いない状況ですが、そこで気になるのが民間のドローン資格がどのような位置付けになるかです。
まだ不確定な部分が多いのですが、もし民間資格を取得していたとしても、改めて免許は取得しなければならないのは、間違いない状況です。
但し、ドローン資格所有者は学科や実技が一部免除になったり、取得費用が優遇されるなど、完全に無駄になるわけではありません。
民間のドローン資格を取得していることで、一定のスキルがあることを担保されていることを証明できるので、まだ不確定要素の強い免許制度を待つよりも、取得しておくのは有効的と言えます。
民間によるドローンの認定資格とはどんなもの?

ドローンを飛行させるためには、免許や資格は必要ありません。しかし、いくつかの民間団体が、独自にドローンの認定資格を設けており、取得者が年々増えています。
民間によるドローンの認定資格とは?取得しておいた方が良い理由など
民間によるドローンの認定資格は、主に「ドローンの基礎知識」「法律や気象などに関する基礎知識」「ドローンの操縦技術」「安全に飛行させるための知識」などを認定しています。
認定資格の取得者が増えているとお伝えしましたが、それには次のようなメリットがあるためです。
資格取得という目標があることで知識や技術が身につく
資格を取得するためには、特定のカリキュラムを修了したり、テキストを読み込んで知識を蓄えたりした上で、最終的に認定試験に合格しなければなりません。短期間で集中的に習得するため、効率よく知識や技術を身につけることができます。
自分の技術や知識を客観的に証明してくれる材料になる
認定資格があれば「特定のカリキュラムを修了し、認定試験に合格した」ということが客観的に証明できます。口頭で「自分はドローンの操縦技術や知識がある」というよりも説得力があるだけでなく、ドローンを使った仕事に就くときに有利に働くこともあります。
ドローンの代表的な認定資格は?
ドローンの認定資格を設けている民間団体はいくつかありますが、その中でも代表的な団体を紹介します。
実技系
DJI(DJI JAPAN株式会社)
DJIは中国のドローンメーカーです。ドローン界では知らない人はいないというほど有名で、世界のドローン市場をリードする存在です。ドローンメーカーではありますが、独自の認定資格を設けています。
JUIDA(ジュイダ/一般社団法人日本UAS産業振興協議会)
東京都文京区に事務局を構えるJUIDAは、日本にあるドローン関連の民間団体の中で、最も古くから存在する団体です。全国にJUIDA認定スクールがあり、所定のカリキュラムを修了することで認定資格の取得を申請できるようになります。
DPA(ディーパ/一般社団法人ドローン操縦士協会)
東京都渋谷区に事務局を構えるDPAは、JUIDAに次ぐ団体として有名です。DPAも全国に多数の認定スクールを抱えており、その数はJUIDAの認定スクールをしのぎます。所定のカリキュラムを修了すると、認定資格の申請ができるようになります。
座学系
ドローン検定協会(ドローン検定協会 株式会社)
実技系がいわゆる「3強」であるのに対し、座学系は今のところドローン検定協会1強という構図になっています。座学のみのため操縦技術は身につきませんが、その代わり検定に向けて勉強することで、法律、気象学、力学、物理学、専門知識など、深く身につけることができます。
次章では、これらの団体が実施している講義、試験、資格などについて詳しく紹介していきます。
ドローン認定資格が取れる【DJI CAMP】とは?

民間のドローン認定資格について、ひとつずつ詳しく解説していきます。まずは、世界的なドローンメーカーDJIの認定資格が取得できるDJI CAMPについて見ていきましょう。
DJI CAMPの概要
DJI CAMPは、DJIのドローンをより正しく、安全に使いこなせるようになるために、DJI JAPAN株式会社が企業向けに独自に開催しているドローン操縦士養成プログラムです。ドローンに関わる正しい知識とドローンの確かな操縦技術、安全に対する高い意識などを習得し、評価します。筆記試験や実技試験、レポート作成などをクリアすると、「DJIスペシャリスト」としての認定証を発行してもらえます。
DJI CAMPでドローンの認定資格を取得するメリットとは?
DJIは、世界有数のドローンメーカーです。そのDJIが独自に認定資格を設けているということは、それなりのレベルでなければ試験をクリアすることが難しい内容になっています。逆を言えば、DJI CAMPを修了してDJIスペシャリストになれれば、対外的に自分のドローンに対する知識や技術を証明でき、企業の信頼性にもつながります。
DJIスペシャリストに認定されると、地方航空局長や空港事務所長宛に、航空法に基づく飛行許可申請を提出する際、有利になると言われています。そのほか、DJIユーザー向けのドローン保険(DJI賠償責任保険)が、約10%割引されるといったメリットもあります。
DJI CAMPでの資格取得までの流れ
DJI CAMPを受講するには「法人または個人事業主であること」「ドローンの飛行操縦経験が10時間以上あること」「DJI製品のマニュアルを熟知しており、ドローンを使った業務に従事できるレベルにあること」などの条件があります。
実際にDJI CAMPを開催しているのは「DJI CAMPインストラクター企業」になります。各インストラクター企業に直接申し込みます。申し込んだ日程で所定のカリキュラムを消化し、試験に合格することで、DJIスペシャリスト認定証の発行が申請できるようになります。
2日間の座学講義や筆記試験、実技試験といった講習や試験があります。座学では「操縦者の行動規範」「安全基準」「禁止事項」といった基礎的な部分から「電波や気象」「法律」についてまで、あらゆる範囲を網羅します。
技能テストも「機体のコンディションチェック」「離陸」「ホバリング」といった基礎的な部分から、「対面で離陸地点に戻ってくる」「ノーズインサークル×2」といった技術まで評価します。
認定テストは「飛行計画レポート作成」「飛行技能テスト」があり、いずれも合格した人は「最終オンラインテスト」を受講します。
DJI CAMPの受講費用は、インストラクター企業ごとに異なるため、確認が必要です。また、DJIスペシャリスト認定証の発行にかかる費用は16,200円です。なお、DJI CAMPは、全国各地にあるインストラクター企業によって多数開催されています。
JUIDAの認定スクールとは?どのようなドローンの認定資格が取得できる?

続いて、日本におけるUAS(Unmanned Aircraft System=無人航空機システム)の健全な発展と振興を目指して設立された、JUIDAが行っている認定資格をご紹介します。
JUIDA認定スクールの概要
JUIDAは、日本で初めて認定スクール制度を開始した団体です。全国にJUIDA認定スクールを構えており、好きな認定スクールでJUIDAの認定資格を取得するためのカリキュラムを受講することができます。JUIDAの認定資格は「無人航空機操縦技能」「無人航空機安全運行管理者」の2種類で、JUIDA認定スクールで所定のカリキュラムを修了し、試験に合格することで、各認定証の発行を申請することができます。
JUIDA認定スクールの証明書を取得するメリットとは?
JUIDA「無人航空機操縦技能証明証」を取得することで、自分に一定以上の操縦技術があることを証明できるようになります。ドローンを使った仕事に就きたいときはもちろん、自分でドローンビジネスを考えている人も信頼性の点で有利と言えます。
また、DJIスペシャリストと同様に、地方航空局長や空港事務所長に飛行許可を申請する際、手続きの簡略化が可能といったメリットもあります。さらに「安全運行管理者証明証」を取得していれば、安全に対する知識、意識が高いことも証明されます。
多くの人は、2つの資格を同時に取得するようですが、ドローンオペレーターのマネージメント職に就きたい人などは、特に取得しておいた方が良いかもしれません。なお、安全運行管理者は、操縦技能証明を先に取得しなければ受講できません。
JUIDA認定スクールの資格試験の流れ
JUIDA認定資格は、主に個人向けです。20歳以上であれば、ドローンの飛行経験などを問わず、誰でも受講することができます。各認定スクールに直接申し込むのですが、スクールによって開催日程、場所、費用、受講スケジュールなどが異なります。中には宿泊施設に泊まり込みで実施するといったスクールもあるため、事前にきちんと確認しておきましょう。
座学では概論、法律、気象から点検整備、安全管理、リスク管理まで幅広く、実技では離陸やホバリングといった基礎的なものから、GPSなし、自律航行まで習得できます。なお、安全運行管理者の場合は目視外飛行、夜間飛行、物件投下飛行なども学びます。試験に合格すると、JUIDAの定める流れに沿って証明証を申請し、発行してもらうことができます。
操縦技能証明証の申請費用は20,000円、安全運行管理者証明証の申請費用は15,000円となっていますが、申請にはJUIDA個人会員への入会が必須となっています。JUIDA個人会員の入会費、年会費は以下の通りです。
正会員(個人):入会金50,000円/年会費10,000円(ともに非課税)
準会員:入会金0円/年会費5,000円(ともに非課税)
正会員と準会員の違いは、JUIDA社員総会における議決権があるかないかです。それ以外のセミナー、情報提供といった案内は同じように行われます。
DPAのドローン資格認定制度とは?

ドローン航空の安全文化の構築、人命救助や環境、衛生、警備といった各分野とドローン航空の相互発展や融合、調和を目指して設立されたDPAの認定資格について見ていきましょう。
DPAのドローン資格認定制度の概要
2018年12月現在、DPAが行っているドローンの認定資格には「ドローン操縦士回転翼3級」「ドローン操縦士回転翼3級インストラクター」の2種類があります。「2級」「1級」「整備士資格」といった資格も制度を設計中とのことなので、近いうちに公開されるかもしれません。
現行の「ドローン操縦士回転翼3級」を取得すると、農薬散布、映像コンテンツのための空撮、橋梁や送電線等のインフラ点検といった現場で活かせる技術や知識が身につきます。DPAも全国に認定スクールを構えており、各スクールでカリキュラムを受講できます。
DPAのドローン資格を取得するメリットとは?
DPAは「ドローン操縦士協会」という名前からも分かるように、操縦士をメインにした団体です。そのため、DPAの認定資格はドローンの高い操縦技能や、操縦するにあたって必要な知識を身につけることができます。
例えば、現行の3級では、手動航行で目視外飛行ができるレベルの技術を習得できるとしています。2級になれば、自動航行による目視外飛行ができるレベルになり、精密農業、レーザー測量、外壁点検、ソーラーパネルの空中点検など、より幅広い分野で活躍できる技術、知識が身につきます。
1級になれば、補助者なしで無人地帯での目視外飛行ができるレベルになり、離島や山間部への荷物配送、災害時の被災状況の調査、行方不明者の捜索、河川測量や長大なインフラ点検などに活かせる技術や知識が身につくとしています。JUIDA同様、地方航空局長や空港事務所長に飛行許可を申請する際に手続きが簡略化されるメリットもあります。
DPAのドローン資格取得までの流れ
DPAの「ドローン操縦士回転翼3級」は、15歳以上、視力や色覚のほか身体的な要件などがありますが、ドローンの操縦初心者でも受講することができます。ドローンの飛行時間10時間以上を有することという要件もありますが、これはDPA認定校で別の講習を受けてクリアすることもできます。
一方「ドローン操縦士回転翼3級インストラクター」は、その「ドローン操縦士回転翼3級」の資格を持っていないと受けることができません。こちらは18歳以上、50時間以上の飛行経験など、ハードルが高くなっています。
資格取得までの流れはほぼ同じです。
DPA認定校に直接申し込み、DPAが定めるカリキュラムを修了したうえで筆記、実技両方の試験に合格したあと、オンライン講座を受講、修了すると認定証の申請ができるようになります。
上記いずれの資格も、申請費用は25,000円、以降、2年ごとに更新料として12,000円が必要になります。
座学で認定資格を取るならこれ!ドローン検定とは?

座学系のドローン認定資格は、今のところ「認定者数業界No.1」とされている、ドローン検定が存在感を示しています。ドローン検定協会 株式会社の認定資格をご紹介します。
ドローン検定の概要
空の産業革命と言われるドローンが急速に普及し始め、さまざまな分野の産業に導入され始めたものの、一方では事故や事件が続発しています。そうした背景を受け、ドローンを扱う人たちの知識レベルを客観的に評価することで、資質の向上と同時に、周囲への理解を広めることを目的として実施されているのがドローン検定です。
ドローン検定は座学のみでおこなわれ、1級〜4級までランクが分かれています。3級、4級は誰でも受講できますが、2級を受講するには3級を、1級を受講するには2級を取得していなければなりません。
2015年の第1回から2018年11月までに20回の検定が行われています。合格者数が最も多いのは3級の8,377人、次いで2級の2,620人、1級の1,449人、4級の475人と続きます(2018年5月時点)。
2020年6月1日現在では、延べ認定数は1級が2,471人、2級が4,640人、3級が16,595人、4級が890人と確実に増加中です。
3級と4級には、受験資格が無いのに対して、2級の場合は3級取得者、1級の場合は2級取得者のみが対象となるので、2級以上の資格を取得するためにまずは3級の資格取得を目指すという方が多いというのが、この数字から見て取れますね。
ドローン検定で資格を取得するメリットとは?
業界でも認知度が高い認定資格であることから、個人なら自分自身、企業であれば自社のPRにつながります。検定に向けて勉強していく中で、ドローンの基礎知識はもちろん、物理学、工学、気象、専門知識、法令など、幅広い分野の知識を身につけることができます。
実技系の認定資格と同じように、航空法に基づく飛行許可申請をおこなう際、認定資格の証明証を添付することができるため、手続きを簡略化できることもあります。実技系の認定資格と併せて、ドローン検定を受講する人も多いようです。
ドローン検定の条件や流れ
ドローン検定への申し込みは、ドローン検定のホームページから行えます。年齢といった条件は特になく、誰でも申し込むことができます。日程もドローン検定のホームページに掲載されているので、迷うことはないでしょう。
ただし、前述のように1級、2級はそれぞれ、ひとつ下の級を取得していなければ申し込めませんので注意が必要です。申し込み後は案内に従って受験料を入金し、試験を受けることになります。受験料は次の通りです。
1級 18,000円
2級 12,000円
3級 5,500円
4級 3,000円
合否は郵送で通知されるほか、ドローン検定のホームページからでも確認できます(無料の会員登録が必要です)。1級合格者には合格証(カード)、合格者ピンバッジが付与されるほか、希望すればドローン検定協会ホームページにプロフィールを掲載してもらえます。
2級の合格者には合格証とピンバッジのみ、3級、4級の合格者には合格証のみ、付与されます。なお、ドローン検定のホームページでは、検定に向けた「ドローン検定 公式テキスト」を購入することもできます。検定を受けたい人はもちろん、検定は受ける予定はないけど、知識を蓄えたいという人も、ぜひ一度、チェックしてみてはいかがでしょうか?
他にもドローンを操縦するなら持っておいた方が良い資格はある?

ドローン操縦といった技能や知識に対する免許や資格はありませんが、ドローン操縦士として活躍する夢があるなら、ぜひ取得しておきたい国家資格というものがあります。最後に、その国家資格をご紹介していきます。
ドローン操縦に役立つ資格① 第4級アマチュア無線従事者免許
使用できる周波数帯は、国ごとに規格が定められています。日本では、電波法によってスマホや電化製品などに使われている周波数帯2.4GHzであれば、免許不要で使用することができます。2.4GHzに対応しているドローンも多くあるものの、海外メーカーのドローンの中には5.8GHzを使用するものもあります。
代表的なものは、FPV(First Person View)対応のドローンやゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)です。日本で5.8GHzを使用するときに必要となるのが「第4級アマチュア無線従事者免許」で、第4級アマチュア無線技士と言われることもあります。
無線従事者の免許は1級〜4級に分かれており「第4級アマチュア無線従事者免許」は、その中でも最もハードルが低い資格です。とはいえ、しっかりと基礎知識を身につけ、試験に備えておかなければ簡単に合格できるものではありません。
公益財団法人 日本無線協会が開催している「第4級アマチュア無線従事者免許国家試験」に合格する方法と、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会または、キューシーシー企画といった団体が主催する講習会を受講したのち、修了試験に合格すれば取得できます。
この資格があれば、5.8GHz対応のゴーグルを装着して、FPVを楽しんだり、ドローンレースに参加したりすることができます。
試験にかかる費用は、試験申請書の用紙代120円、試験手数料4級4,950円、免許申請の際にかかる費用は、申請書の用紙代170円、手数料2,100円です。養成講座、講習会なども開催されており、受講料は1〜2万円程度が目安となります。
「ドローンでFPVを楽しみたい!」「いつかはドローンレースに参加したい!」と思っている人は、ぜひとも取得しておきたい資格です。
ドローンに関連する国家資格② 第3級陸上特殊無線技士免許
陸上で、無線局の無線設備に関する技術的な操作を行う際に必要となるのが「第3級陸上特殊無線技士免許」です。身近な例で言えば、タクシーに使われている無線の基地局において、設備など、技術的な操作を行う際に必要です。
このことからも分かるように、趣味というよりはドローンを使った仕事に就きたい人におすすめの資格です。ドローンパイロットのマネジメントをしたい、測量、インフラ点検、警備、物流といった分野で働きたいという人は、ぜひチェックしておきましょう。
「第3級陸上特殊無線技士免許」は、公益財団法人 日本無線協会が開催している国家試験を受けて合格するか、トライアロー株式会社、キューシーシー企画などが開催している養成講座や講習会に参加して修了試験に合格する、e-ラーニングを受講して修了試験に合格するといった方法があります。
費用は、国家試験を受ける場合は6,480円、その他の団体が主催する養成講習の受講料は2〜2万5,000円程度が目安となります。
将来、ドローンを使った仕事に就くことを考えている人、ドローンでビジネスを考えている人は、「第4級アマチュア無線従事者免許」と併せて、取得しておいて損はない資格です。
免許制度開始後のドローン業界はどう変わる?

ドローンの免許制度導入は2022年に開始される見込みとなっていますが、実際に運用がスタートすると、どのような変化をもたらすのでしょうか?
まずはじめに、履歴書の資格欄にドローン免許を記載できるようになるかもしれない可能性が高いです。
これによって、就職や転職で有利に働く可能性が十分考えられます。
現時点でも、運転免許書などが採用条件となるケースがありますが、業種によってはドローン免許が必須というケースも出てくることでしょう。
ドローン免許制度化でより活躍が期待できる分野とは?
では、ドローンの操縦におけるライセンス制度が運用されると、どのような分野で活躍できるのでしょうか?
ここでは、ドローン免許があると役に立つ可能性がある分野を紹介します。
農業分野
TPPや地産地消、6次産業化など、近年急激に関心が高まっているのが農業の分野です。農業分野では、ドローン免許制度化を前にすでにドローンの活用が普及しています。
というのも、ここ数年農業分野においては、農業従事者の高齢化が問題となっていました。農業従事者の平均年齢は60歳を超えており、労働力不足や担い手不足による耕作放棄地の増加、農業人口の減少が大きな課題とされています。
そこで活用されているのが、ドローンです。
ドローンを取り入れることで、今まで人間が行っていたことを機械化し、労働の負担軽減や作業効率化が期待できます。
農業分野にドローンを取り入れるメリット
短時間での作業が可能
ドローンを活用して農薬散布を行う場合、作業時間を比較しても、10aを1分程で散布することができ、人が散布するよりも1/5の時間で作業を完了させることができるため、効率よく、労働力を抑えての作業が可能となります。
狭い農地での農薬散布も楽に行える
ドローンは小回りが利くために、中山間などの小さい10a程の圃場においても、人の手を煩わせることなく農薬散布を行うことができます。
労働者の負担を少なく作業が可能に
ドローンを活用することで作業時間が短くなるだけでなく、なによりも高齢者であってもドローンの操作さえ覚えれば猛暑などの過酷な環境下でも辛い思いをすることなく作業ができます。
このように、効率的に楽して作業できるドローンによる農薬散布は、これからも広く普及することは間違いありません。
他にも、農業分野ではドローンの導入が進む動きが加速しています。
農薬と同じように、散布が必要になる肥料や種まき、受粉作業に活用されています。
農業分野での具体事例
具体的な事例1:梨の溶液授粉の実証実験
梨は作業適期が3〜4⽇と短く、多くの⼈⼿を必要となる梵天を⽤いた⼈⼯授粉は、作業者の⾼齢化等を背景に⼈材確保が年々難しくなっている実情が有りました。
そこで、授粉作業の省⼒化や軽労化を図ることを目的として、農業⽤ドローンを活⽤して溶液授粉の実験が行なわれました。
2019年に和梨、洋ナシで試験的に実施され、2020年は新潟県農業⼤学校からの協⼒を得て和梨(幸⽔)も加えた3品種で実施されています。
溶液授粉は、花粉を混ぜた溶液を樹上約2mの⾼さから散布する実験が行なわれて、これにより4⼈の作業員が10アールを約1⽇かかる授粉作業が、1機1分程度で終了しています。
2019年の検証結果として、着果率が3割程度と決して高くない状況であるため、2020年は6〜7割の着果率を⽬指して改良が進んでいるのです。
具体的な事例2:ドローンに搭載した散布装置を使用しての種まき
農業分野では農薬散布だけでなく、散布装置を使用して鉄コーティング種子などの散播が行なわれています。
これまでは空中からの播種として、無人ヘリを利用して行っていましたが、ドローンを使うことで、コストを大幅に抑えて労力の削減が実現可能となる見込みです。
また、一般的な播種で使用される湛水直播機では困難であった、中山間地域の作業においてもドローンを使うことで容易かつ短時間で播種が行えるようになったのです。
更に、積極的に試験が行われているのは米の播種であり、大分県日田市、広島県東広島市、福岡県楢葉町などで試験が実施されています。
日本の食を支えるお米作りにも広く生かされようとしているのがすばらしいです。
物流分野
身近なところでは、ドローンを使用した宅配サービスも発展が見込まれています。
離島や山間部など配送が困難だったり、日数がかかっていた場所への配送において、ドローンを活用することで少ない人材かつ短期間での配送が可能となります。
配送料等については今後の普及によって大きく変動する可能性はありますが、従来のように飛行機や船を活用した運搬をする必要はないため、低価格での運用が期待できるでしょう。
実際に以下のような実証実験も行われています。
楽天ドローン、離島配送プロジェクト
楽天ドローンという会社がドローン配送事業を展開しているのですが、2019年7月4日から国内初となる離島配送プロジェクトをスタートさせています。
舞台となっているのは、東京湾唯一の無人島である猿島で、年間20万人もの観光客が訪れる人気の観光地です。
猿島対岸にある西友LIVIN横須賀店で取り扱っている商品を、スマートフォンで簡単に注文して配送できるサービスとなっています。
対象商品は約400品目もあって、生鮮食品や飲料などバラエティー豊かな品ぞろえとなっており、バーベキューで必要な食材なども取り寄せることが可能です。
配送料金は500円で積載量は5kgまでと制限がありますが、時間指定も可能です。
毎週木、金、土曜日限定で、一日最大8便が運航しています。
千葉県千葉市ドローン宅配
一企業だけでなく自治体レベルでの技術実証も進んでいます。
千葉県千葉市において、ドローン物流の本格化に向けて制度整備や改革、規制改革について話し合う千葉市ドローン宅配等分科会が設立されました。
ここでは、実証実験の具体的な実施方法や、実証実験に係る技術的課題を抽出して分科会に報告することを目的としている技術検討会が立ち上がっています。
技術検討会には、Amazonやイオン、NTTドコモ、佐川急便、日本電気、三井物産、ヤマトロジスティクスなどの物流や商流の大手企業が名を連ねています。
目的として、人口集中地区におけるドローン宅配を実現させることがメインテーマとなっています。
過疎地域におけるドローン物流ビジネスモデルの模索
国土交通省でも、過疎地域におけるドローン物流ビジネスモデルを模索しています。
実際に、2018年度に長野県白馬村、福島県南相馬市、浪江町、福岡県福岡市、岡山県和気町、埼玉県秩父市で行なわれた検証実験が行なわれているのです。
過疎地では、どうしても食料品などの購入においても一苦労するのが実情であり、この実験がうまくビジネスに繋がる事が期待されています。
「空飛ぶクルマ」でドローンタクシー
自動運転の技術開発が進む一方で、ドローンタクシーというものが実用化されつつあります。
初めてドローンタクシーが話題になったのは、2016年のCESにおいて中国のEHang社が出展したEHANG 184のコンセプトモデルです。
その後、2019年8月5日には、日本企業であるNECが空の移動革命に必要となる交通整理や管制、管理基盤の構築を本格的に開始すると宣言しました。
そのファーストステップとして、空飛ぶクルマと称する旅客ドローンのプロトタイプを開発し、浮上実験に成功したと発表しました。
推進装置や自律飛行やGPSの情報を得て飛行を制御するソフトウェアなどが新規開発して搭載されているのが特徴です。
空の移動革命に向けた官民協議会が示したロードマップによると、2020年代半ば、特に2023年を目標に事業をスタートさせて2030年代から実用化をさらに拡大することが示されています。
巡回警備やインフラ点検、日常生活でもドローンの活用が期待されている
この他にも、365日24時間の巡回警備やインフラ点検、ドローンを使った犬の散歩などなど、すでに導入されているサービスから実証実験段階のものまで、ドローンの可能性がより広がっています。
特に、少子化によって人口減少が課題となっている日本では、ドローンによる機械化が積極的に進められるのは間違いありません。
一方で、先に紹介したドローンタクシーのように人間を載せて操縦しなければならないものは、より操縦に対してのスキルと同時に、責任感がついて回ります。
そこで、重要となるのがドローンの免許制度です。
免許制度導入によって、ドローン免許は注目の資格になるとともに、更なる利便性の向上が見込めます。
一人前のドローンパイロットになるために!資格取得以外の大事なこと

今回は、ドローンにまつわる資格や免許について詳しく解説してきました。2018年12月現在、ドローンを飛行させるために免許や資格は必要なく、この記事でご紹介した民間資格も、あくまで「ドローンの飛行許可申請に有利」「自己PRの際の材料になる」といった位置付けにすぎません。
資格の取得を目指すことで、知識や技術が身につくことは確かですが、一人前のドローンパイロットとして活躍するために、忘れてはいけないことがほかにもあります。
一つは、ドローンパイロットとしてのモラルや知識です。1章でも紹介したように、ドローンにはさまざまな法律や条例が関わってきます。
その全てを理解する必要はありませんが、第三者に危害を与えてしまう、あるいはプライバシーや肖像権を侵害してしまうといった行為は、ドローンの健全な発展に寄与しません。
併せて、ドローンをどんな形で活用していきたいのかというビジョンも、ある程度明確に持っておくと良いでしょう。
最初は趣味、空撮など大雑把なものでも構いませんが、ドローンの活用方法をより具体的にイメージすることで、自分に本当に必要なスキルは何かが見えてきます。それは必ずしも免許や資格ではなく、ビジネスをするためのスキルであったり、時代を読むスキルであったりするかもしれません。
ドローンにまつわる免許や資格だけに捉われず、自分のライフプランも含めて、ドローンと自分のビジョンを考えておくことが大切です。
同時に、ドローンの健全な発展のためにもぜひ、確かな操縦技術、モラルや安全、リスクに対する知識、法律や条例に関する知識なども蓄えておくように心がけましょう。
この記事と一緒によく読まれている記事
-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント
-
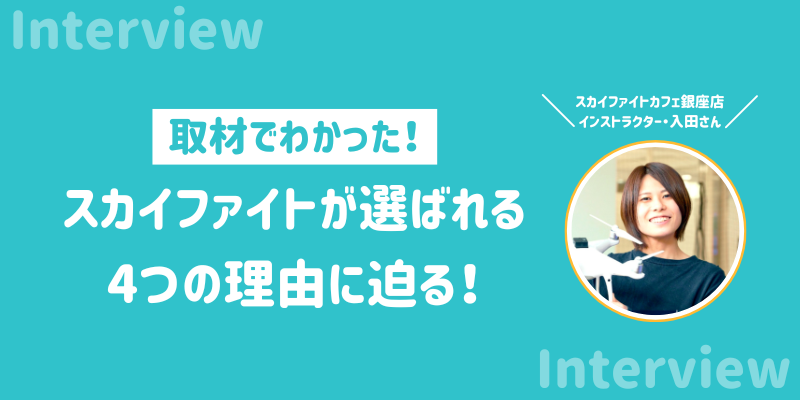
オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由
-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング
-
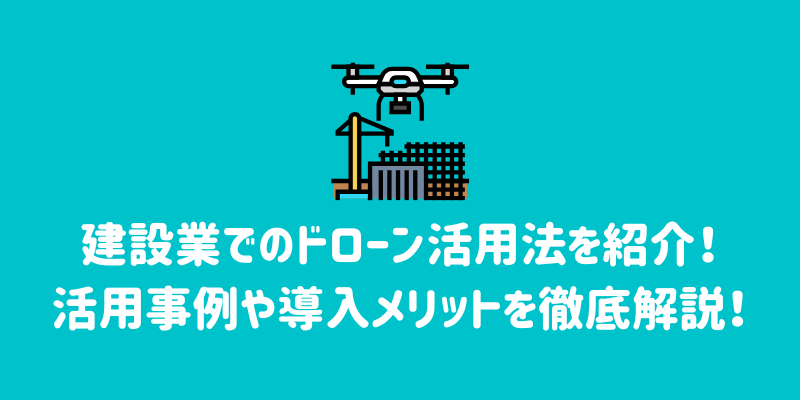
建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!
-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!
-
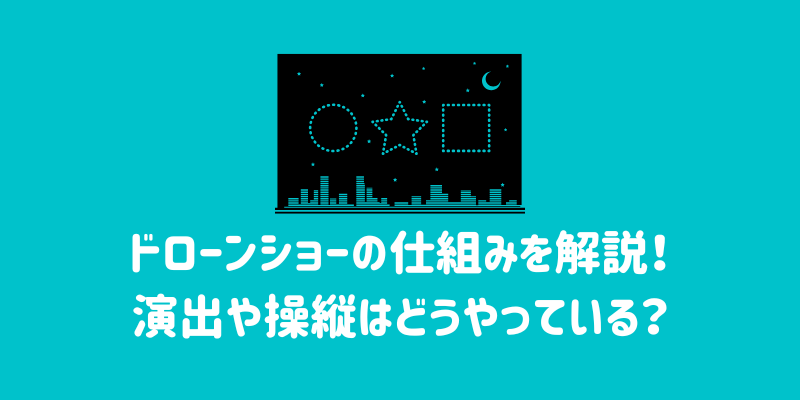
ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?
-
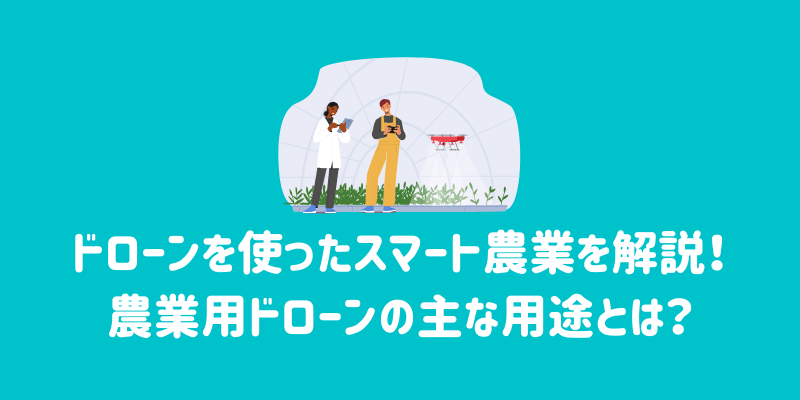
ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?
-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる
-
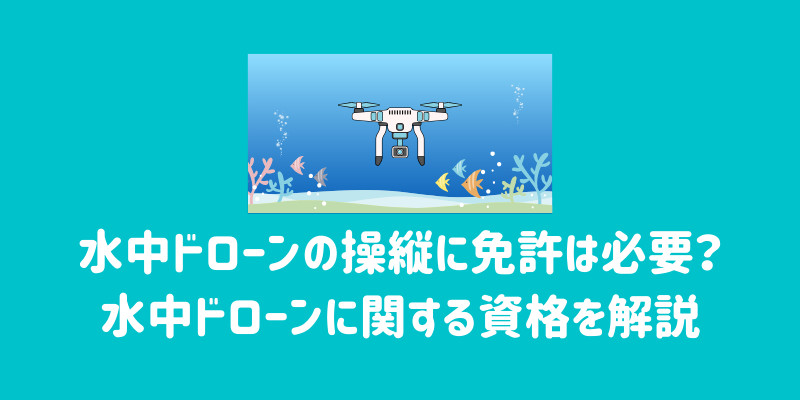
水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説
-
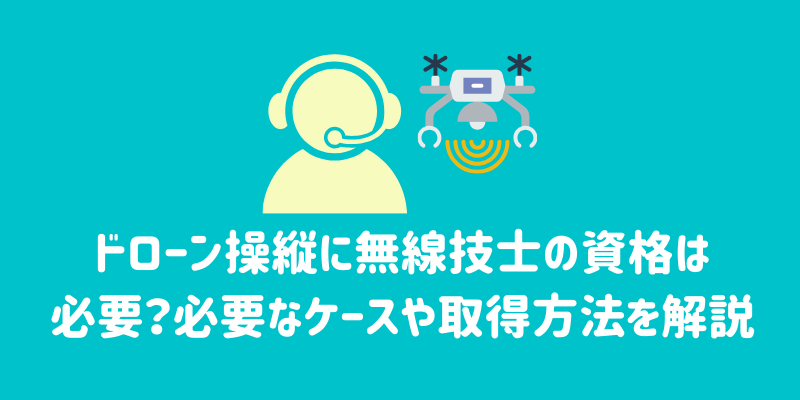
ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!
-
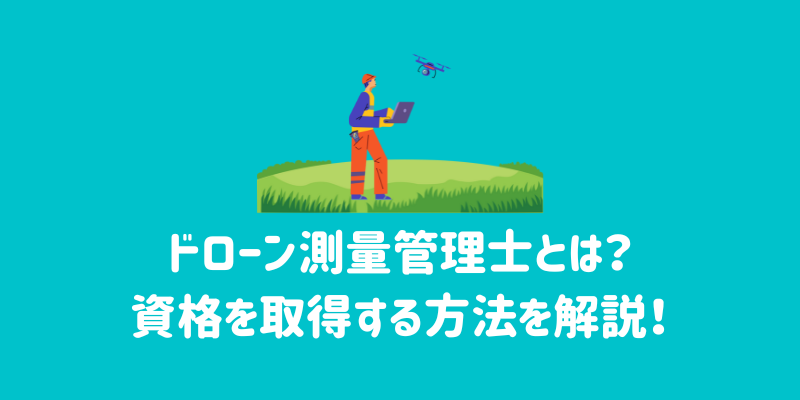
ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!
-
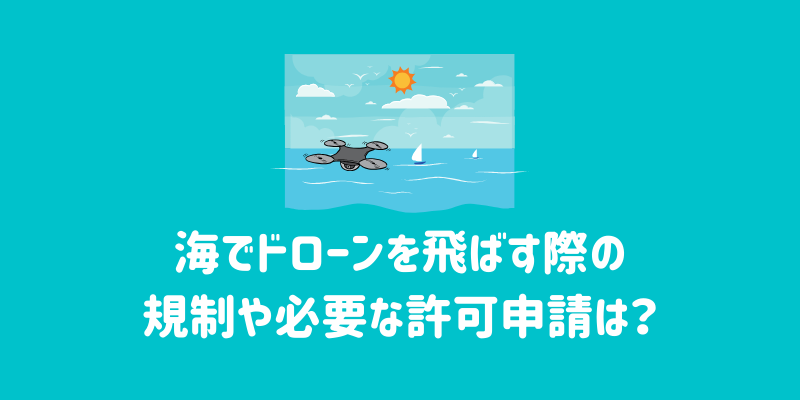
海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説