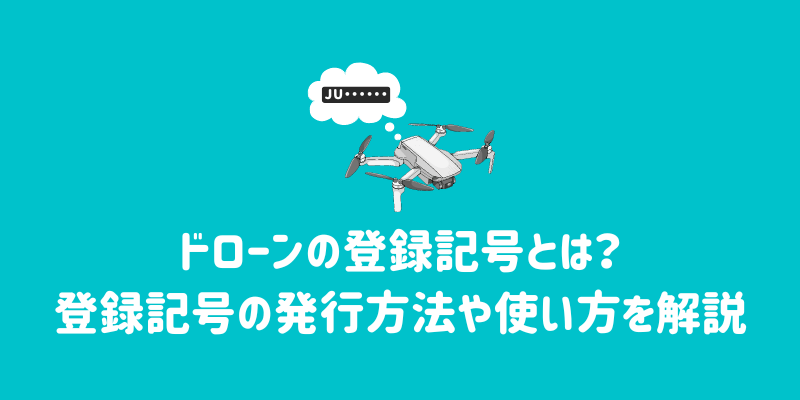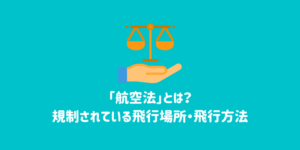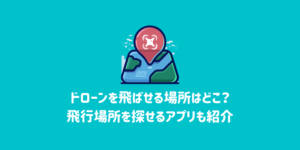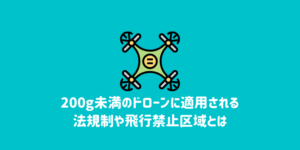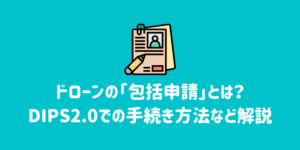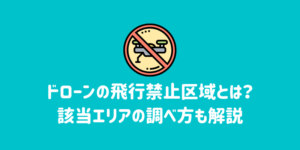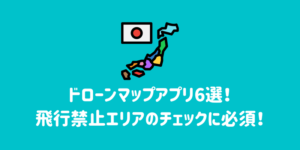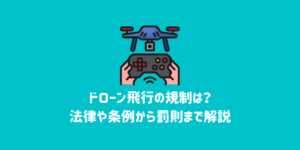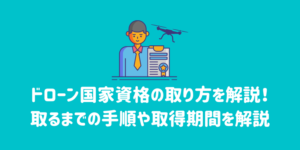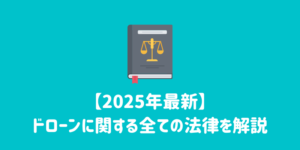機体登録制度が適用されるドローンを屋外で飛ばす場合、「登録記号」の取得と機体への表記が義務付けられています。
今回はドローンにおける登録記号とは何か、発行の手順・使用する場面・貼り付け方などと共に徹底解説いたします。
確認方法や登録記号の表記なしで飛ばした場合のペナルティなど、気になる情報も記載していますのでぜひ最後までご覧ください。
ドローンの登録記号とは?

ドローンの登録記号とは、ドローンの機体登録制度で登録を受けたドローンに付与される記号です。
機体制度は2022年6月から施行されたもので、DIPS(ドローン情報基盤システム)または書類の郵送で手続きを済ませる必要があります。
手続きを済ませると「JU」から始まる独自の登録記号が発行され、それを登録した機体に表記しなければなりません。
当該の機体情報や所有者情報などを速やかに割り出せる登録記号は、車に例えるとナンバープレートのような位置づけにあります。
リモートIDの登録も必要
登録記号の取得・表記と併せて、「リモートID」の搭載と登録も義務付けられています。
リモートIDとは、ドローンの識別情報を遠隔発信する装置のことです。
100g以上のドローンを屋外で飛ばすなら、外付けタイプの機器を機体に搭載するか内部にリモートID機能が組み込まれた機体を使う必要があります。
登録記号の発行申請の際、リモートIDの有無や情報を記載する項目があるため、あらかじめリモートID機器を手元に用意のうえ手続きに着手するとスムーズです。
重量100g以上のドローンは機体登録が必要

従来の航空法で「無人航空機」と分類されるのは重量200g未満の機体でしたが、改正航空法により対象となる機体の重量が100gまで引き下げられました。
これにより100g以上のドローンも無人航空機として扱われ、無人航空機を対象とする機体登録制度が適用されます。
以前は各種手続きが不要だった100~199g未満のトイドローンでも、現在は屋外へ飛ばす際に機体登録手続きと登録記号の取得、そしてリモートIDの実装が義務付けられているため注意が必要です。
機体登録に必要なもの
機体登録手続きに必要なものは、以下の通りです。
- 登録したいドローンとその詳細情報
- リモートIDとその詳細情報
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートのどれか)
- 登録手数料(900~2,400円)
なお、登録手続きはWEBから好きなタイミングで手続きを完了できるDIPSの利用がおすすめです。
WEB申請の際はアカウント開設が必要になるため、あらかじめDIPSにアクセスのうえ、案内に従い開設を済ませておきましょう。
また、アカウント開設に際して本人確認も必要です。
マイナンバーカードを使う場合は、必要情報入力と併せてマイナンバーカードの連携も済ませましょう。
ICカードリーダーを使うか、スマートフォンでバーコードを読み取れば連携できます。
機体登録の手順
ここでは、DIPSを使って機体登録の手続きを済ませる手順をご紹介いたします。
機体登録は、主に以下の手順で手続きを行います。
登録申請とメール認証後、手数料納付の案内メールは1~5開庁日後に届きます。
また、手数料納付から登録完了メールが届くまでの日数も1~5開庁日後が目安です。
登録の際はスケジュールに余裕を持ち、10日前後はかかると見積もっておきましょう。
ドローンの登録記号を使う場面

ドローンの登録記号を取得する意味は、ただ法律に則り登録した機体の識別情報を示すだけではありません。
他にも、以下のような場面で登録記号が役立ちます。
DIPS2.0上での飛行許可申請で記入する
航空法では、以下の場所・方法にて無断でドローンを飛ばすことは禁止されています。
【飛行場所】
- 150m以上の高さの上空
- 空港周辺
- 人口集中地区(DID地区)上空
- 緊急用務空域
【飛行方法】
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人・物・車などから30m未満の距離での飛行
- 催し場所での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
ただし、事前に国土交通大臣へ申請のうえ許可・承認を得た場合は飛行が可能となります。
混同されがちですが、ドローンの機体登録と飛行許可申請はまったく異なる手続きなので注意しましょう。
その飛行許可申請には、手続きに際して使用する機体の登録記号の記入が必須です。
所有者不明のドローンを拾得した際に持ち主を特定する
ドローンの機体登録制度が新設された主な理由は、ドローンの飛行中に万が一のトラブルが発生した際に所有者情報などを迅速に把握できるようにするためです。
飛行中に機体が制御不能となりロストしても、誰かにその機体を拾って届け出てもらうことで、機体に表記された登録記号からすぐに持ち主が特定できるようになります。
ドローンの登録番号はステッカーやシールで機体に貼る
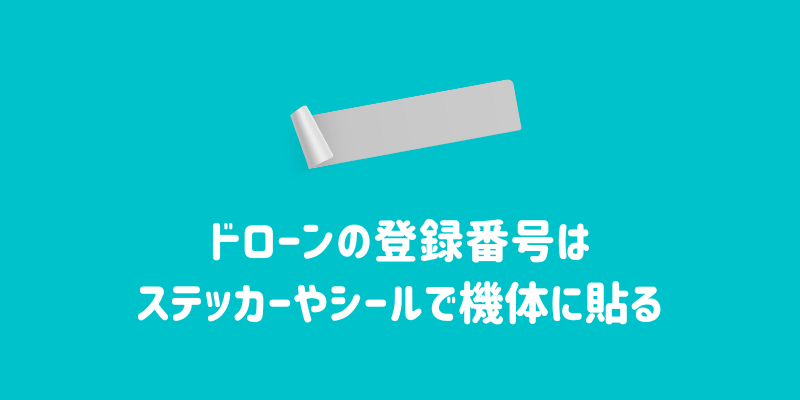
ドローンの機体登録後、取得した登録記号は自分で機体に表記する必要があります。
表記の手段としては、登録記号を記載したステッカーやシールを機体に貼り付けるというのが一般的です。
以下より、登録記号をドローンに貼り付ける2通りの方法について詳しくご紹介いたします。
市販のステッカーで作る方法
ドローン関連の販売店によっては、ドローン専用の登録記号ステッカーを販売している場合があります。
例えばドローンのスキン用シールやリペアパーツなどを販売している「WRAPGRAD」では、所有機体の登録記号を入力のうえ購入するとその登録記号が印字されたステッカーを入手できます。
登録記号の表記方法や記号のサイズなどの規定に準じたステッカーを作製してくれるため、自分で調べながら用意する手間を省くことが可能です。
また、屋外で飛行するドローンに貼り付けることを前提とした作りなので、耐久性が高く汚れや劣化による剥がれの心配もありません。
自作する方法(テプラ)
より安く身近なもので登録記号を表記したいなら、テプラを使ってステッカーを自作するという手もあります。
文字の大きさを調整し、規定の通りに正しく登録記号を記したうえで機体に貼り付けることができます。
また、自宅にテプラがない場合はコンビニのコピー機を利用しても良いでしょう。
その際は事前にパソコンからWord・PowerPoint・画像編集ソフトなどを使って、必要な分だけ登録記号を記載します。
次にUSBメモリーなどにファイルを保存し、コンビニのコピー機に接続してシール用紙で印刷します。
あとは登録記号の部分を切り取れば、ステッカーの完成です。
ドローンの登録記号を貼る場所

ドローンの登録記号は、万が一のトラブルが発生した際に明確に把握できるように表記する必要があります。
ステッカーを使う場合は、機体の胴体部分に貼り付けましょう。
国土交通省が公開している無人航空機登録ハンドブックでは、ドローンの登録記号の表示場所について以下の条件を設けています。
- ドライバーなどの工具を用いずに容易に取り外しができない部分
- 墜落時に飛散する可能性の低い部分
- 外部から確認しやすい部分
プロペラやアームなど簡単に着脱できる部分、機体の内部など外側から簡単に確認できない部分などは、トラブル発生時に確認や安全管理が滞る原因になるため表示できません。
外れにくく確認しやすいという条件を考えると、胴体部分への貼り付けが理想的です。
ドローンの登録記号に関する注意点
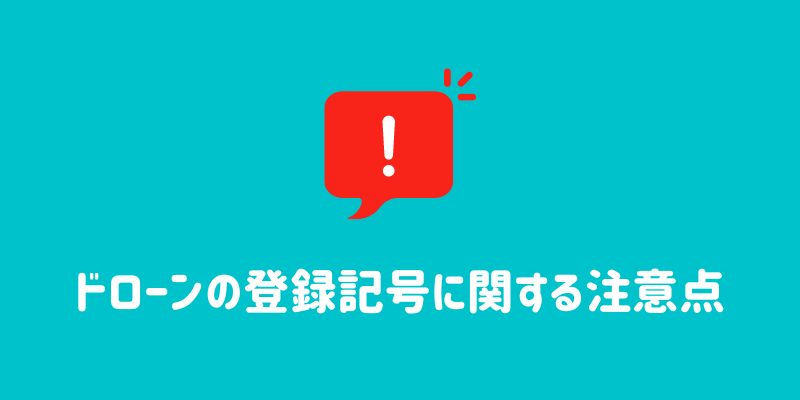
登録記号を表記するにあたって、場所以外にもいくつか覚えておくべきルールがあります。
以下の点に注意して、登録記号を正しく表記しましょう。
表記する数字の大きさを確認する
無人航空機登録ハンドブックでは、機体に表記する数字の大きさも指定されています。
重量25kg未満のドローンには3mm以上、重量25kg以上のドローンには25mm以上の大きさで記号を記載する必要があります。
WRAPGRADから販売されているステッカーを使うならあらかじめ記号の大きさが調整されているため、確認は不要です。
一方でステッカーを自作する場合は、フォントサイズに注意のうえ画像データを作成しましょう。
雨風に晒されても耐えられるものを使用する
基本的に雨天時や強風が吹いているときなど、天候が荒れているタイミングはドローンの飛行に向いていません。
しかし飛行中に予期せぬ雨風に見舞われたり、業務により雨風の中でも飛行させる必要があったりと、ドローンが雨風に晒されるリスクは完全に回避できません。
そのため、雨風に晒されても簡単に消えない登録記号の表記方法を検討しましょう。
主な方法としては、耐水性と耐久性のあるステッカーやシールを使う、油性マーカーを使うなどが挙げられます。
なお、先述したコンビニのコピー機で印刷できるシールも光沢があり水を弾くため、規定から逸れずに登録記号を表記できます。
視認しやすいように機体と区別できる色にする
適切な場所・大きさで登録記号を表記しても、目立たなければ確認が困難になります。
ひと目ではっきりと登録記号を認識できるように、登録記号は機体との区別が容易かつ鮮明な色で表記しましょう。
例えば白い機体には黒色、赤い機体には緑色など相対する色のステッカーを使って表記すると分かりやすいです。
ドローンの登録記号に関するよくある質問
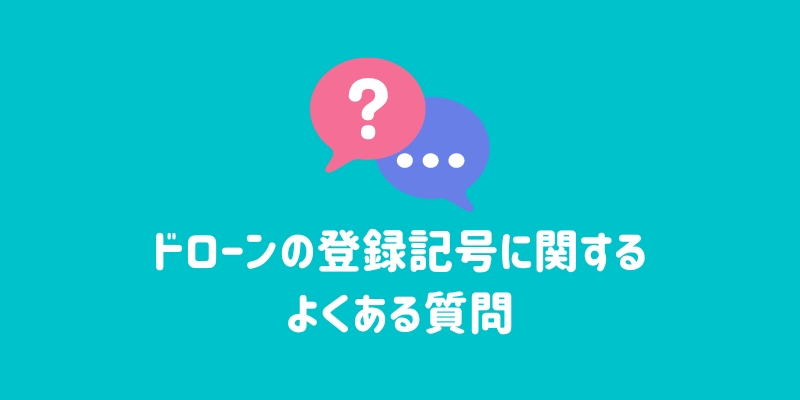
最後に、ドローンの登録記号に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
登録番号の確認方法は?
ドローンの登録記号や登録情報は、DIPSの「申請状況の詳細画面」または「所有機体情報の詳細画面」で確認が可能です。
それぞれ以下の手順で登録記号・情報を確認することができます。
【申請状況の詳細画面から確認】
【所有機体情報の詳細画面から確認】
ドローンの機体登録はなぜ必要?
ドローンの機体登録制度が新設された主な理由は、「ドローン(無人航空機)の利活用拡大における安心・安全の確保」のためです。
従来の法規制では、ドローンをはじめとする無人航空機の不適切な飛行事案が発生しても機体の所有者が特定できず、適切な対策を講じることができないという問題がありました。
さらに近年におけるドローンの事業活用のニーズ拡大も相まって、万が一の事態に備えて無人航空機の所有者を把握できる体制の重要性が高まっています。
このような背景から、安心・安全なドローンの利活用を可能とするために、所有者情報の事前登録を義務付ける機体登録制度が設けられました。
登録記号を機体に表記をせずにドローンを飛ばすとどうなる?
登録記号を機体に表記しないと、事故などのトラブルが発生した際に適切な対応を取ることが難しくなります。
また、航空法で義務付けられている機体登録を済ませているかどうかの事実確認も遅れ、事態が複雑化するリスクも考えられます。
なお、機体登録そのものを怠り屋外でドローンを飛ばすと、航空法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
登録番号はシールではなくマジックなどで書いてもいい?
登録番号の表記は、場所・大きさ・色などの条件を満たせばマジックで直接書き込む形でも問題ありません。
ただし雨風などで消えることがないように、水性ペンや鉛筆などではなく油性のマジックを使いましょう。
まとめ
ドローンの登録記号とは、航空法で義務付けられている機体登録の完了後に取得できる独自の記号です。
万が一トラブルが発生した場合、機体に表記された登録記号を元にドローンの所有者を速やかに特定できます。
機体にドローンの登録記号を表記するには、専用のステッカーを使う・自分でステッカーを自作する・油性ペンで機体に直接書き込むといった方法があります。
表記方法についてもルールが定められているため、よく確認しておきましょう。
重量100g以上のドローンを屋外で飛ばす際は、機体登録や登録記号の表記を含め、飛行前に必要な各種手続き・準備を済ませて適切に飛行を実施しましょう。
この記事と一緒によく読まれている記事
-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント
-
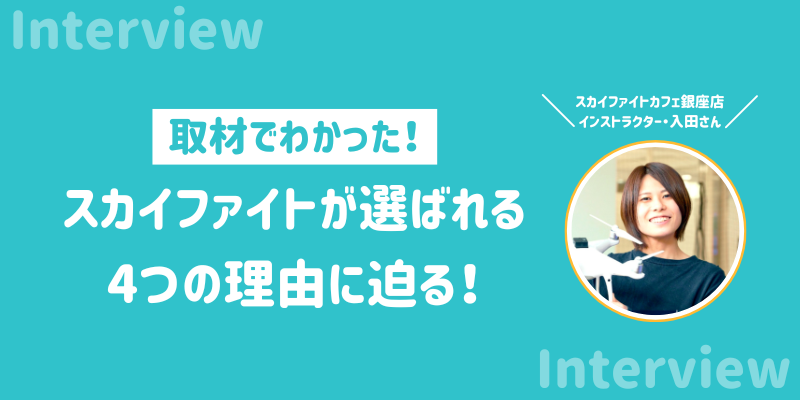
オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由
-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング
-
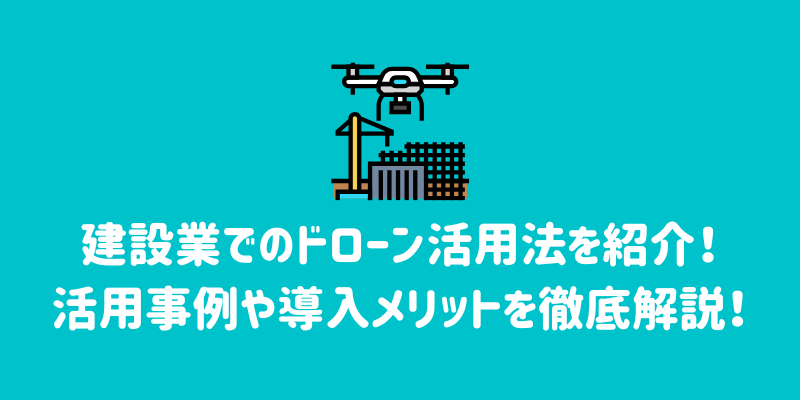
建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!
-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!
-
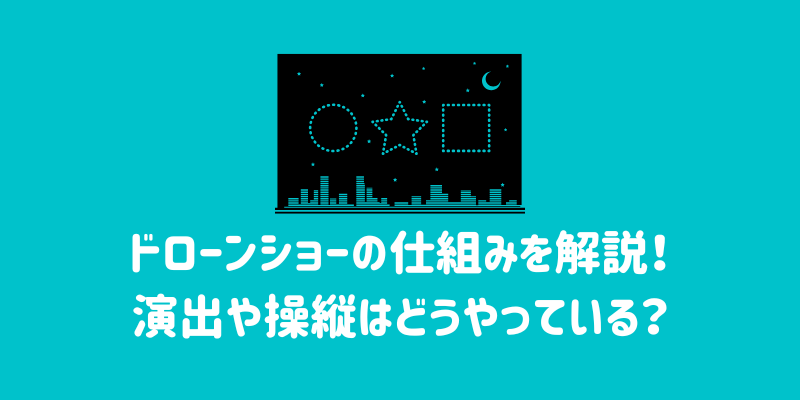
ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?
-
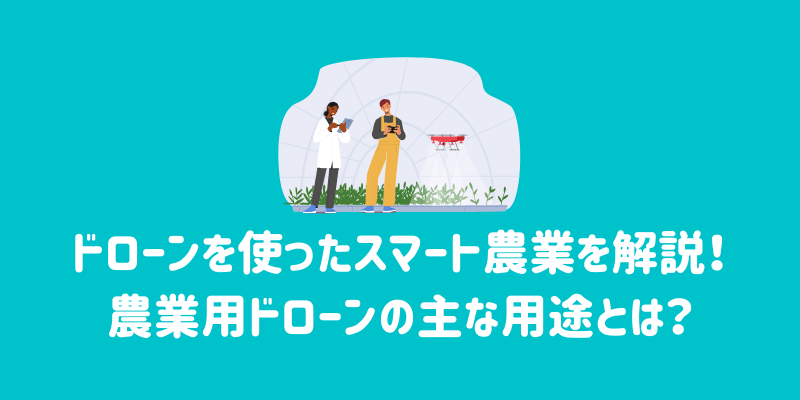
ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?
-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる
-
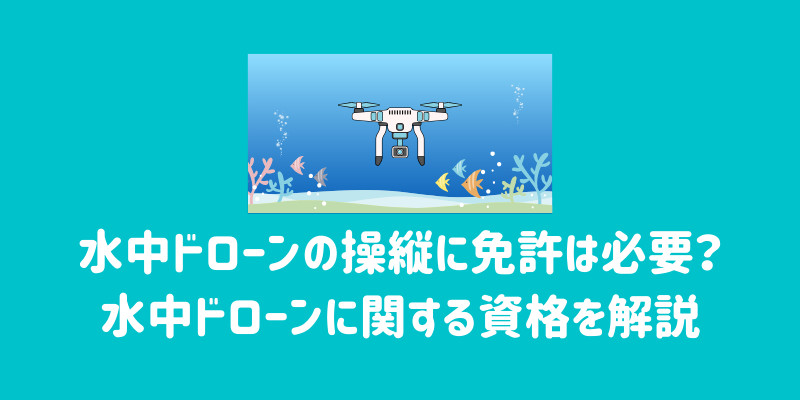
水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説
-
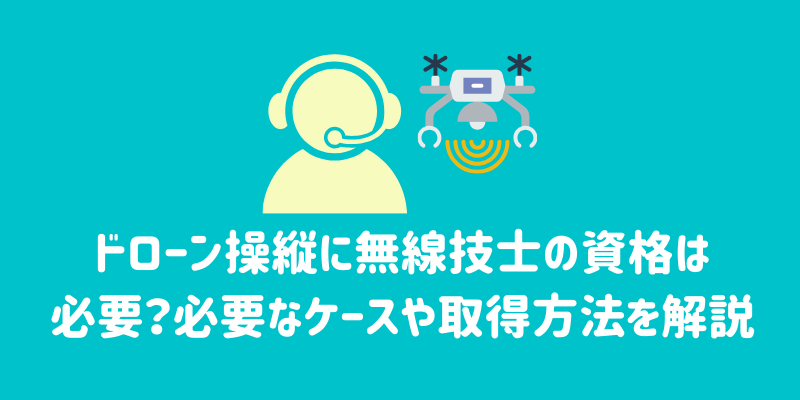
ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!
-
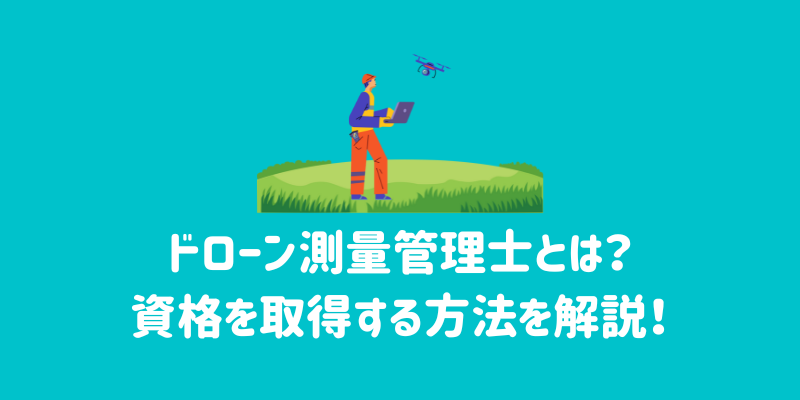
ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!
-
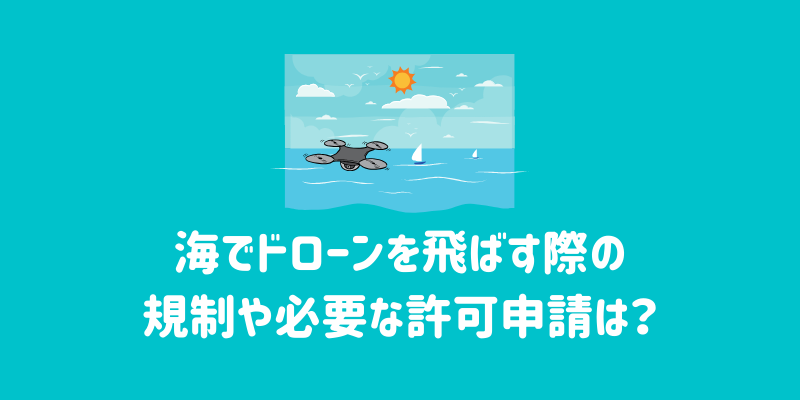
海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説