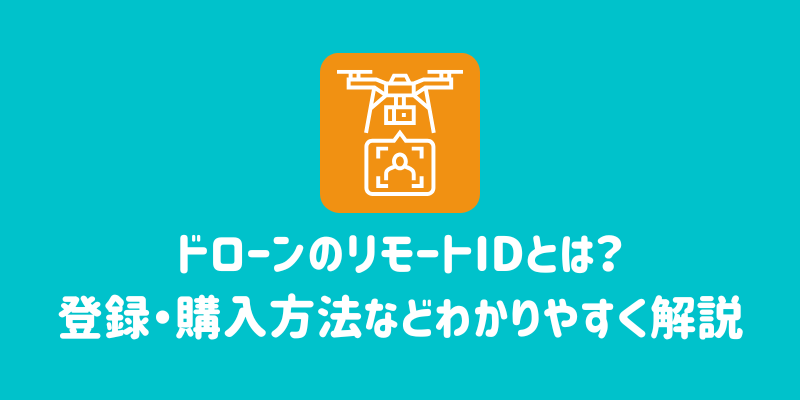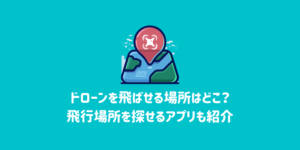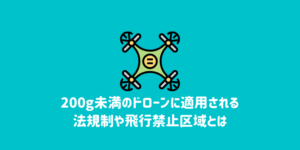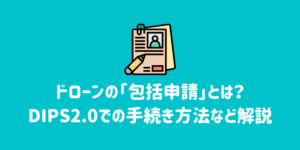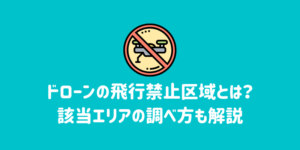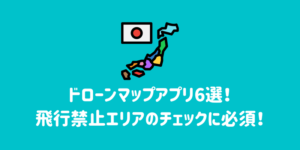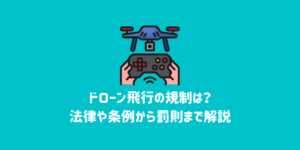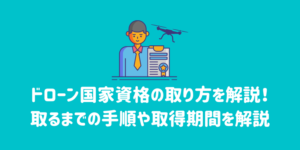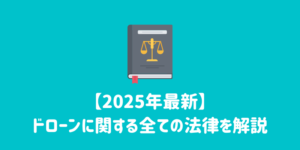2022年6月20日より、ドローンに「リモートID」の搭載・登録を義務付ける制度が新設されました。
DJI製ドローンなどはリモートIDを搭載している機種もありますが、非搭載機種の場合は自分で購入のうえ実装する必要があります。
今回はドローンのリモートIDとは何なのか?という基礎知識に加え、リモートIDの搭載機種やリモートIDの種類、購入時の選び方、主なメーカーと機種などを分かりやすく解説いたします。
100g以上のドローンを飛行させる方には必見の知識となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
リモートIDとは

リモートIDとは、ドローンが持っている識別情報を遠隔発信する機器のことです。
自動車に例えるとナンバープレートにあたるもので、機体ごとに固有のIDを付与して遠隔発信させることで、「どんな機体なのか」 「誰が所有しているのか」などを識別できるようになります。
リモートIDが発信する情報は、主に警察・重要施設関係者・航空局・機体の所有者など特定の機関や人物が受信装置を通して確認可能です。
なお、所有者自身の個人情報が発信されることはありません。
リモートIDの発信情報
リモートIDから発信される情報は、大きく分けて「動的情報」と「静的情報」の2種類があります。
それぞれに含まれる具体的な項目は、以下の通りです。
| 動的情報 | 静的情報 |
|---|---|
| ・位置 ・速度 ・高度 ・時刻 など | ・登録記号(国土交通省から発行される番号) ・製造番号(メーカーの製造番号) |
上記の情報が、1秒に1回以上発信されています。
リモートIDの搭載義務
リモートIDは、2022年6月20日より所有ドローンへの搭載と登録が義務化されました。
同年12月に施行された改正航空法に伴い新設された制度で、万が一事故が起きても迅速な原因究明と対処を可能とすることが目的となっています。
リモートIDの搭載・登録義務は機体重量100g以上のドローンが対象で、搭載・登録せずに100g以上のドローンを屋外で飛行させると罰則が科せられます。
リモートIDの免除条件
ただし、機体重量100g以上のドローンでも以下に該当するケースはリモートIDの搭載免除の対象です。
- 「リモートID特定区域内」かつ安全措置を講じて飛行させる場合
- 係留して飛行させる場合
「リモートID特定区域」とは、事前の届け出によりリモートID未搭載の機体の飛行が認められる区域のことです。
管轄の航空局へリモートID未搭載の機体やその機体の飛行区域、代表者の情報などを記載した届出書を提出することで、届出が完了します。
リモートID特定区域の届出を行い、なおかつ目視で監視する補助者の配置や特定区域を明示する標識の設置など、必要な措置を行えばリモートID未搭載でも罰せられません。
リモートID特定区域の届出方法については、こちらをご覧ください。
また、十分な強度を有する長さ30m以内の紐などで係留し、飛行させるドローンについてもリモートIDの搭載義務が免除されます。
リモートIDの免除期間
2022年6月20日にはドローンの機体登録制度も運用開始となりましたが、その前に「事前登録期間」が設けられていました。
事前登録期間は2021年12月20日~2022年6月19日となっており、その間に機体登録を済ませたドローンはリモートIDの搭載義務が免除されます。
搭載義務が免除されるのは2022年6月20日からの3年間で、それ以降もドローンを屋外で飛行させたい場合はリモートIDを搭載させる必要があります。
なお、すでに機体登録制度の事前登録期間は過ぎているため、これからドローンを始める方はこの免除措置を利用できません。
リモートIDが内蔵された機体を購入するか、別途購入したリモートIDを搭載のうえ、機体登録を済ませてから飛行させましょう。
リモートIDを登録をしない場合の罰則
リモートIDの搭載・登録は、航空法という法律で定められた義務です。
機体重量100g以上かつ免除の条件に該当しないケースで、リモートIDの搭載・登録をせず、屋外でドローン飛行させた場合は50万円以下の罰金が科せられます。
なお、詳細は後述しますがドローンの中には内蔵型リモートIDを搭載した機種もあります。
所有しているドローンがリモートIDを搭載している場合、実装のための対応は不要です。
ドローンのリモートIDの種類
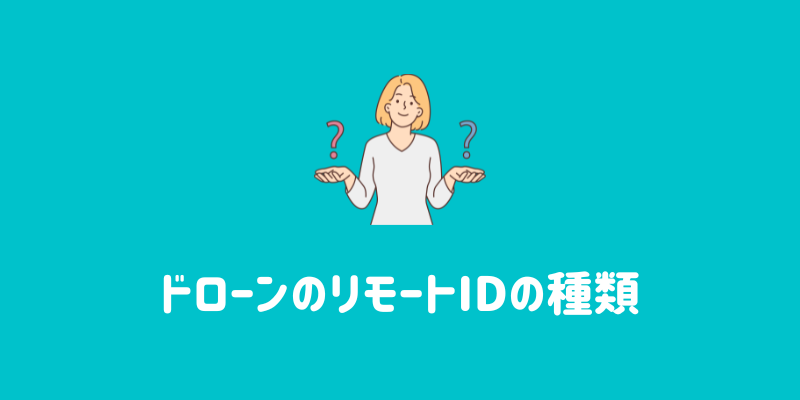
リモートIDを実装する方法としては、「内蔵型リモートID」を搭載した機種を購入するか、非搭載の機種に「外付け型リモートID」を搭載するかの2種類があります。
それぞれの特徴を理解し、実装方法を決めることから始めましょう。
内蔵型リモートID
内蔵型は、メーカー側が各機種の内部に組み込まれているタイプのリモートIDです。
製造段階でリモートID機器を組み込んでいることもあれば、アップデートで対応するものもあります。
例えばDJI製ドローンの場合、一般向け・産業向けの一部機種がリモートIDに搭載されており、ファームウェアアップデートによりリモートIDを機体にインポートすることが可能です。
外付け型リモートID
外付け型は、リモートID未搭載・非対応の機体に装着して機体情報を発信させる機器のことです。
機器を別途購入する必要があり費用がかかりますが、機体の所有者が変わらない場合は複数の期待に使い回すことが認められています。
なお、使い回す場合はその都度リモートID機器に装着予定の機体情報を再設定する必要があります。
ドローンのリモートID搭載機種と対応状況

リモートIDの購入費用を抑えたい場合、内蔵型リモートIDに対応した機種を購入することをおすすめします。
ただし、現状として主要なドローンメーカーでもすべての機種にリモートIDが搭載されているわけではないため、購入前の確認が必要です。
内蔵型リモートID機種
メーカーから内蔵型リモートIDを搭載しているとして公表されている主な機種は、以下の通りです。
| メーカー | 機種 |
|---|---|
| DJI | ・DJI Air 3S ・DJI Mini 4K ・DJI Neo ・DJI Avata 2 ・Matrice 3TD ・Matrice 3D ・DJI FlyCart 30 ・DJI Mini 4 Pro ・DJI Air 3 ・DJI Mavic 3 Classic/Pro Cine/Pro ・DJI Inspire 3 など |
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | ソニーグループ式ARS-S1型 |
| Holy Stone Toys | HS360E |
| Potensic | RID-916 |
| Autel Robotics | ・Autel Alpha ・EVO MAX ・EVO 2 Pro V3 ・EVO 2 Dual 640T V3 ・EVO 2 Dual 640T RTK V3 ・EVO 2 Pro RTK V3 ・EVO 2 Dual 640T Enterprise V3 ・EVO 2 Pro Enterprise V3 ・EVO Nano ・EVO Lite |
| 株式会社クボタ | ・T25K ・T30K ・T10K |
外付け型リモートID機器
外付け型リモートID機器については、基本的にどの機種にも取り付けが可能です。
ただし安全のため、プロペラやプロペラガードに接触しない位置に取り付けることは覚えておきましょう。
機種によって仕様が異なる場合もあるため、ドローンの製造メーカーや購入先に取り付け位置について問い合わせるのもおすすめです。
各メーカーごとのリモートID対応状況
リモートID対応機種があるドローンメーカーとして届出があった企業や対応機種については、国土交通省が一覧表を公表しています。
その一覧表に掲載されている主なメーカーは、以下の通りです。
- DJI
- SONY(ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 、ソニーグループ株式会社)
- Potensic
- ACSL
- AUTEL
- 双葉電子工業
- Braveridge
- TEAD
- エアロエントリー
- クボタ
- ヤマハ発動機
- プロドローン など
参考:適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧
ドローンメーカーの最大手であるDJIの他、国内企業を中心に様々なドローンメーカーがリモートIDに対応しているようです。
今後開発される機種、特に国産ドローンについては、実装の手間が省けるとして需要の高い内蔵型リモートID対応機種が増えていくと思われます。
ドローンのリモートIDを実装する方法
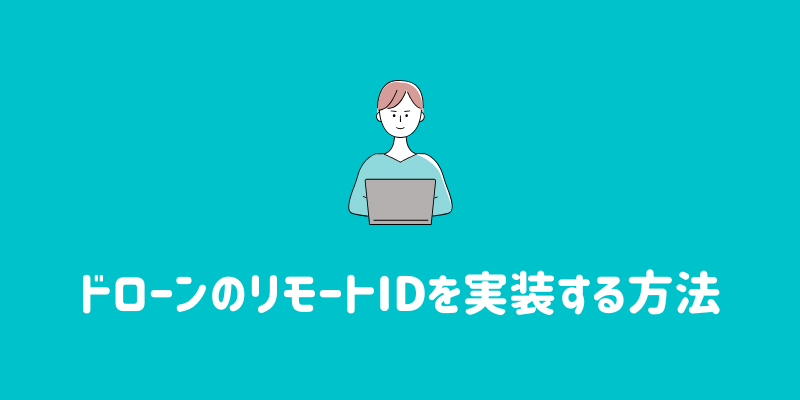
リモートIDは、内蔵型リモートID対応機種を購入または外付け型リモートID機器を搭載するだけで終わりではありません。
ドローンの機体登録を済ませたうえで、リモートID機器の設定や機体のアップデートを行う必要があります。
ここでは、リモートIDに対応するための実装・設定方法について詳しく解説いたします。
リモートIDの設定前に必要な機体登録の方法
リモートIDの設定は、DIPSでの機体登録を済ませていることが前提です。
まずはマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を用意のうえ、アカウント開設を済ませましょう。
アカウントを開設したら、以下の手順で機体登録の手続きを行います。
機体登録を入力する際、リモートIDの有無を問われる箇所があります。
内蔵型リモートID搭載機種を利用するなら「あり(内蔵型)」、外付けリモートID機器をすでに搭載している場合は「あり(外付け型)」を選択しましょう。
この時点でリモートIDを搭載していない機体を登録する場合は「なし」を選び、書き込み作業の際に情報を変更します。
なお、登録完了メールが届くのは、手数料の納付完了から1~5開庁日後となります。
機体登録を即日完了できない場合があるため、スケジュールに余裕をもって手続きを始めましょう。
リモートIDの書き込み方法は2種類
リモートIDを実装するドローンの機体登録を済ませたら、リモートID機器に機体の識別情報を書き込む必要があります。
外付け型リモートIDはもちろん、内蔵型リモートID搭載機種を使う場合にも必要な作業です。
ただしリモートIDのタイプによって書き込み方法は変わるため、自分が利用したいリモートIDのタイプを決めたうえで正しい書き込み方法を理解しておきましょう。
内蔵型リモートIDの場合
内蔵型リモートIDが搭載されている機種を使う場合、各メーカーが提示している方法に従って情報を書き込む必要があります。
メーカーごとに書き込み方法の詳細は異なるため、公式サイトなどを確認しましょう。
例えばDJIが公開している、DJI製リモートID搭載機種の大まかな書き込み方法は以下の通りです。
なお、機体登録の際にリモートIDについて「なし」と選択した場合はDIPSから情報を変更しなければなりません。
あらかじめ以下の手順で情報の編集を行いましょう。
また、アップデートやDIPSとの連携作業は機体だけでなくプロポも必要です。
ただしスマートフォンなどの端末を装着するタイプのプロポとDJI Fly内蔵型のプロポで連携の方法が変わります。
以下より、プロポのタイプごとにDIPSと連携させる方法をご紹介します。
スマートフォンを装着するタイプのプロポの場合
まずはスマートフォンやタブレットなど、プロポに装着したい端末にインストール済みのDJI Flyのバージョンを確認しましょう。
バージョン1.6.5以前の場合は、1.6.6以降へのアップデートが必要です。
iOSの場合は、App Store上にあるDJI Flyのページにある「アップデート」をタップします。
Androidならアプリ内の「詳細」画面にある「アプリバージョン」から現在のバージョンを確認し、1.6.5以前の婆はDJI公式サイトのダウンロードセンターからアップデートを済ませておきます。
アップデートを済ませたら、以下の手順でDIPSとの連携を行いましょう。
これで機体・プロポともに連携完了となります。
アプリが内蔵されたプロポの場合
スマートフォンなどの端末を装着する場合は事前にアプリをアップデートする必要がありますが、アプリ内蔵型のプロポはアプリ・機体・プロポの同時アップデートが可能です。
機体とプロポを接続し、前項の2~10の手順を実施すればアップデート・連携が完了します。
外付け型リモートIDの場合
外付け型リモートID機器を搭載した機体の場合、DIPSにリモートID機器の情報を入力のうえ書き込みを行います。
事前準備として、アプリ版のDIPSをスマートフォンにインストールしておきましょう。
iOSはApp Storeから、AndroidはGoogle Playからインストール可能です。
また、ドローン本体のファームウェアや専用アプリも最新の状態にアップデートしておく必要があります。
実際の書き込み作業は、機体登録時にリモートID有無について「あり(外付け型)」を選んだ場合と「なし」を選んだ場合で手順が変わります。
以下より、あり・なしそれぞれを選んだ場合の書き込み手順をご紹介します。
リモートID「あり(外付け型)」を選んだ場合
機体登録の際にリモートID「あり(外付け型)」を選んだ場合は、以下の手順で書き込みを行います。
リモートID機器を書き込み可能な状態とする方法は、機器によって変わります。
詳しくは搭載している機器の取扱説明書などを参考にしましょう。
リモートID「なし」を選んだ場合
リモートID「なし」を選んでいた場合、書き込みに際してリモートID機器の情報をDIPSに登録する必要があります。
以下の手順で機体の登録情報を変更し、リモートID機器の情報を追加しましょう。
上記の作業を終えたら、あとは前項と同じくアプリ版のDIPSを利用してリモートID「あり(外付け型)」を選択した場合と同様の手順で書き込み作業を行いましょう。
ドローンに搭載したリモートID機器の発信情報を確認する方法
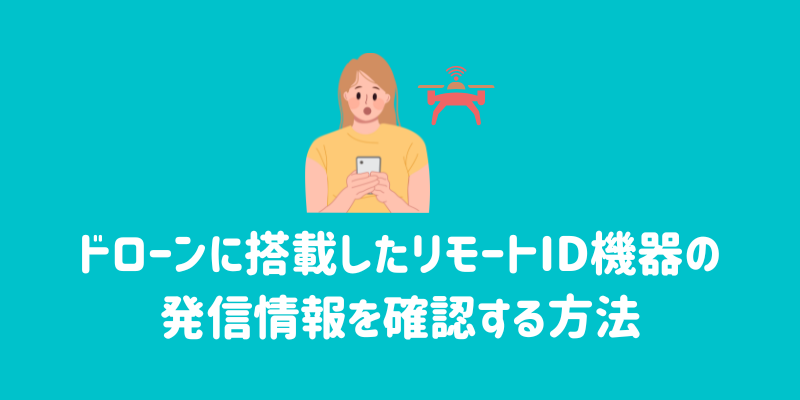
所有している機体に搭載したリモートID機器から発信される情報は、DIPSを通して確認が可能です。
確認方法の大まかな流れとしては、「機体詳細の表示」→「発信情報詳細の確認」という2段階のステップになっています。
具体的な手順は、以下の通りです。
なお、リモートID情報を受信のうえ確認するには以下のうちいずれかの通信規格に対応した端末でなければなりません。
- Bluetooth 5.x Bluetooth LE Long Range
- Wi-Fi Neighbor Awareness Networking
- Wi-Fi Beacon
利用している端末で対応していない通信規格がある場合は警告メッセージが表示され、いずれの通信規格にも対応していなければ発信確認ボタンが非表示となります。
ドローンのリモートID機器の選び方
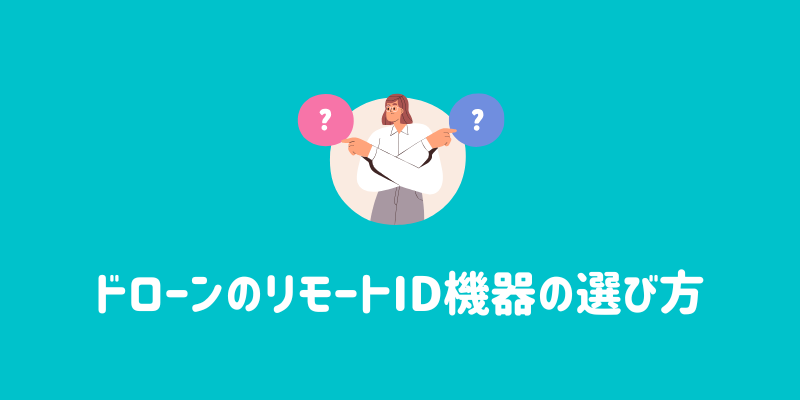
外付け型リモートID機器を利用するなら、自分で機器を選ぶ購入する必要があります。
しかしリモートID機器にも様々な種類があり、初めて購入する方は迷ってしまう可能性が高いです。
ここではリモートID機器を選ぶ際に注目したいポイントをはじめ、「そもそも自分は内蔵型リモートID搭載機種と外付けリモートID機器の利用のどちらを選ぶべきなのか」の判断基準もご紹介いたします。
仕様
機種によって、リモートID機器の仕様(スペック)は変わります。
趣味として空撮を楽しむ程度の使い方であれば細かな仕様を気にする必要はありませんが、業務活用などを目的としたドローンなら通信距離・連続稼働時間・必要充電時間はよく確認のうえ購入しましょう。
特に、自分で電波を受信のうえモニタリングをしながら飛行履歴を管理したい場合、ドローンを長時間稼働させたい場合は目的に合ったスペックを備えた機種を選ぶことが重要です。
なお、一般的な空撮であれば通信距離300m程度でも問題なく飛行することができます。
価格
リモートIDの価格は10,000円~50,000円程度が相場となっており、ドローンと同じくスペックの高さと価格の高さは比例しています。
安価なものだとバッテリーがついておらず基盤のみだったり、通信距離が短かったりすることもあるため注意が必要です。
一方で高価なものは防水仕様となっていたり長距離通信が可能だったりと利便性に優れていますが、価格によっては最初から内蔵型リモートID搭載機種を購入した方がお得になる可能性もあります。
重量
価格だけでなく、機器本体の重量もドローンのスペックに応じて変化するポイントです。
大きさはいずれの製品も手のひらに収まる程度のサイズ感となっていますが、重量は10g~35gと機種によって差があります。
軽量なものはスペックが低い傾向にある、またはバッテリーが搭載されていない機種の可能性があるためよく確認しましょう。
重量のある機種はスペックが高い傾向にある反面、100g~200g台の小型ドローンの搭載には向いていません。
ドローンは総重量が数g変わるだけでも飛行時間や安定性に影響が出ることも多く、小型な機体に対して重いリモートID機器を組み合わせると本来の飛行性能が発揮されにくくなります。
通信距離
リモートID機器は無線通信でドローンの識別情報を発信するため、通信可能な距離もチェックしておくと良いでしょう。
通信距離は機種によって様々ですが、多くの機種は1km以上の距離での受信を可能としています。
リモートID搭載義務に従って搭載するだけならさほど重要ではありませんが、飛行データの管理などで自身もドローンの飛行履歴を確認したい場合は、通信距離の長い機種を選びましょう。
ドローン別おすすめのリモートIDのタイプを解説

航空法に則ってドローンのリモートIDの対応を進めようにも、リモートID内蔵機種と外付け型リモートIDのどちらを購入すべきか悩む方も多いことでしょう。
どちらの方法でリモートIDの搭載義務に対応すべきかは、使用するドローンによっても変わります。
ここでは、小型ドローン・大型ドローンの2通りに分けて、おすすめのリモートIDの搭載方法をご紹介いたします。
小型ドローン:リモートID内蔵のドローンへ買い替えがおすすめ
手のひらサイズのトイドローンや一般向けの空撮ドローンなど、ホビー用ドローンに多い小型機種を使う場合、リモートIDを内蔵しているドローンへの買い替えがおすすめです。
その理由は、主に以下の2つが挙げられます。
- 外付け型リモートIDは小型ドローン1台分の価格であることも多いから
- 飛行性能に影響が出る可能性があるから
外付け型リモートID機器の中には、一般向けドローン1台分に近い価格で販売されている機種もあります。
ドローンとリモートIDの本体価格を合計すると、リモートID内蔵型のドローンを購入できる金額となることも珍しくありません。
そのため、リモートIDへの対応に伴いドローン本体ごと買い替えてしまった方が、コストパフォーマンスが高いといえます。
また、小型ドローンは大型ドローンに比べて発揮される機体性能が限られる傾向にあります。
リモートID機器を後付けすると、重量の増加が飛行性能の低下を招く可能性も考えられます。
機体の総重量増加による飛行時のバランスの悪化や、機体への負荷の増加といったリスクを回避するという意味でも、リモートID内蔵型ドローンへの買い替えはおすすめです。
大型ドローン:外付け型リモートIDの購入がおすすめ
大型ドローンとは、主に重量1kg程度の産業用に開発されたドローンのことを指します。
産業用なだけに一般的な空撮ドローンよりもスペックが優れており、ペイロードも大きく確保されているため外付けリモートID機器も余裕で搭載することが可能です。
先述したように国産の産業用ドローンであれば内蔵型リモートID搭載機種も販売されていますが、農業・点検・測量など機種によって特化している分野は異なるため、「搭載していればどれでも良い」という感覚で選ぶことはできません。
ドローンの用途によっては、リモートID非搭載の機種が必要となる場合もあることでしょう。
そのため、主に業務目的で大型ドローンの導入を検討している人、すでに大型ドローンを所有している人は外付けリモートID機器を搭載するという手段がおすすめです。
外付け型リモートIDのおすすめ機種5選
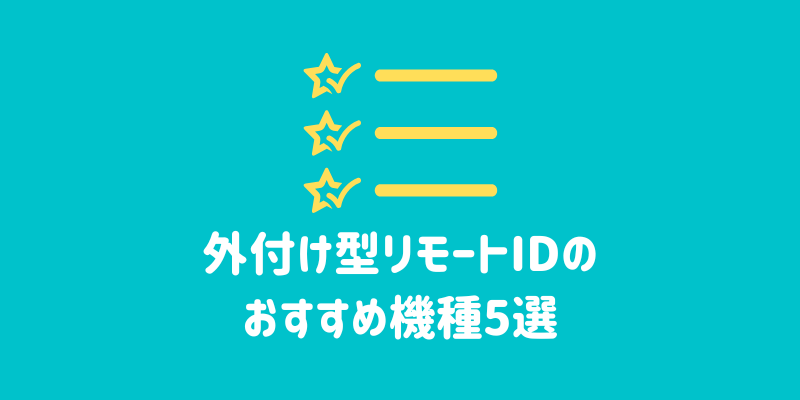
ここでは、2023年現在で外付け型リモートID機器を販売している主なメーカーと機種の特徴をご紹介いたします。
TEAD社「TD-RID」
TEADが販売している外付けリモートID機器は、「TD-RID 外付けタイプ」と「TD-RID 軽量タイプ」の2種類です。
外付けタイプはバッテリーが内蔵されており、重量は12gと比較的軽量な機種です。
サイズは40×30×14mmと小さく、産業機だけでなく小型機・ホビードローンへの搭載にも対応しています。
動作時間6~8時間・充電時間は約2時間・通信距離は300mとなっています。
軽量タイプは本体重量7.5gのバッテリー内蔵タイプと、本体重量4.5gのバッテリーレスタイプがある機種です。
バッテリーレスタイプは本体に給電用のリード線が取り付けてあり、無人航空機のRC受信機に接続して機体から給電を行いながら稼働します。
バッテリーレスタイプは最大動作時間8時間と長く、本体の軽さとスペックのどちらもこだわりたい人におすすめです。
どちらにも装着用テープが付属しており、ワンタッチで機体に着脱することができます。
イームズロボティクス「リモートID送信機 RID-UAV100EJ」
イームズロボティクス製リモートID機器(送信機)は、送信可能距離が1,500mと驚異の長距離通信が可能な点が特徴です。
遠方の地でドローンを飛行させる場合にも、各機関へしっかりとリモートID情報を送信しながら安全に運用することができます。
また、防塵・防水性能も有しており、農薬散布ドローンなどでうっかり薬剤を付着させてしまっても問題なく使用が可能です。
サイズは60×30×22mm、重量は33g程度と先述したTEAD製リモートID機器よりも大型で重いため、産業用ドローンへの搭載がおすすめです。
Braveridge社「BVRPA」

Braveridge製の「BVRPA」は、バッテリーレス仕様で基盤のみとなっている外付け型リモートIDです。
外形寸法40×40mm、本体重量8.5gと小型かつ軽量な機種となっています。
機体識別信号を発信するBluetooth LEモジュールと位置情報を取得するGNSSモジュールには自社製モジュールを採用しており、無線通信技術に特化したメーカーならではのノウハウが凝縮されています。
さらに設計開発から生産まで自社で行うことで、リーズナブルな価格も実現している点が魅力です。(価格は販売店にて要確認)
軽量かつ基盤タイプなので小型ドローンやFPVドローンにも搭載できますが、配線作業が必要になるため上級者向けのリモートID機器です。
Braveridge社「BVRPN」

「BVRPN」は全体的なスペックとしてはBVRPAと同様ですが、アンテナが内蔵されておらず外付けアンテナを接続するタイプとなっています。
所有してる機体へ取り付ける位置、機体の構造・材質などに併せて最適なアンテナで利用が可能です。
AEROENTRY「AERO-D-X1」

「AERO-D-X1」は サイズ36.4×32×14mm・重量11.5gの小型で軽量なリモートID機器です。
30分という短時間の充電で6時間の稼働が可能となっており、利用前の準備に時間がかからないことが特徴です。
IP54相当の防水・防塵設計となっており、通信距離は300mのため屋外でも問題なく利用できます。
価格は税込で19,800円と比較的リーズナブルな設定で、コストパフォーマンスに優れている機種と言えます。
外付け型リモートID機器を搭載する方法
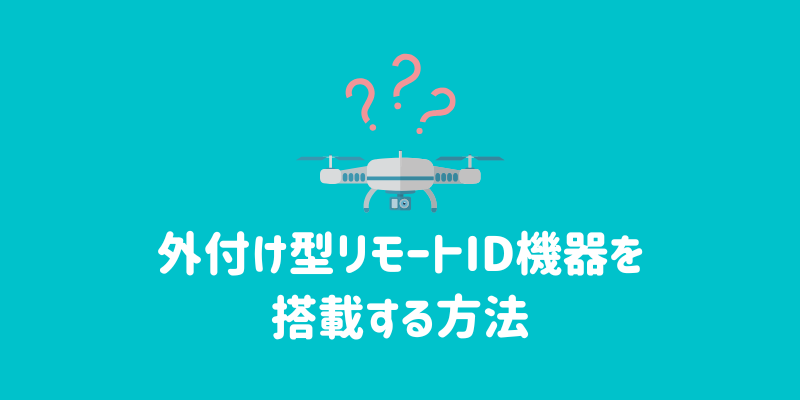
外付け型リモートID機器を使用する場合、具体的にどのような方法でドローンに搭載すべきなのでしょうか。
以下より、リモートID機器の一般的な搭載位置と搭載方法を詳しく解説いたします。
搭載位置
外付け型リモートID機器の搭載位置に、法的な決まりはありません。
ただし、安全のために以下の場所に取り付けることは避けましょう。
- 金属に面した位置
- 機体バランスに影響が出る位置
- センサーの位置
- その他飛行に影響が出る位置
リモートID機器の取扱説明書も確認しながら、プロペラやセンサー類などと接触しないことを確認のうえ取り付けましょう。
一般的には、機体の上部に取り付けます。
搭載方法
具体的な搭載方法はリモートID機器の種類によって変わるため、搭載する前に説明書を確認しましょう。
一般的な取り付け方法としては、両面テープか面ファスナーで固定する場合が多いです。
搭載以降は着脱する予定がなければ両面テープ、取り外す機械がある場合は面ファスナーを使いましょう。
機種によっては、ネジで固定できる取付穴もついている場合があります。
使用するドローンに合った方法で、リモートIDが落ちないように固定しましょう。
また、取り付け後はリモートID機器やドローンの落下を防ぐため、飛行前にその都度リモートID機器が固定されているか確認することも大切です。
ドローンのリモートID搭載を免除するための届出
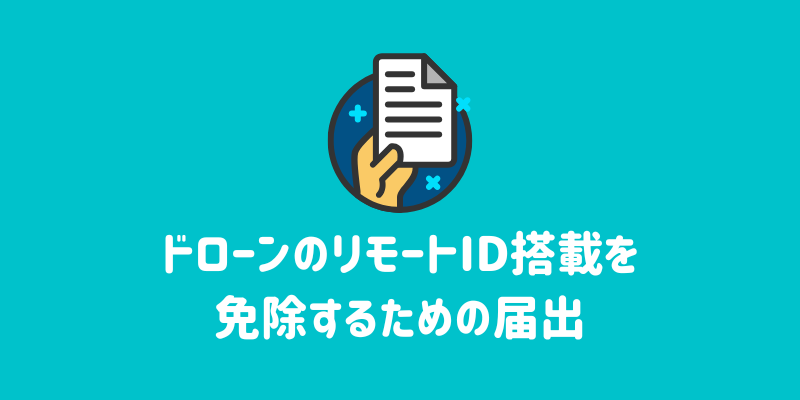
先述したように、ドローンのリモートID搭載義務が免除される条件のひとつに「リモートID特定区域」の届出があります。
この届出は、主にドローンサークルやドローンスクールといった、飛行専用の敷地を確保できる団体に適した手段です。
ここでは、「リモートID特定区域」の届出に必要な基礎知識と届出のやり方を解説いたします。
「リモートID特定区域」の届出とは
リモートID特定区域の届出とは、リモートIDを搭載していない機体とその機体が飛行する区域を事前に届け出ることです。
届出が受理されれば、指定した機体と飛行区域におけるリモートIDの搭載義務が免除されます。
なお、すでにリモートIDを搭載しているドローンや事前登録期間中に登録したドローンを使う場合、この届出は不要です。
「リモートID特定区域」の届出のやり方
リモートID特定区域の届出は、事前の機体登録が必要です。
まだ機体登録が完了していない場合は、先述したリモートIDの設定前に必要な機体登録の方法をご覧ください。
機体登録が完了したら、以下の手順で届出を行います。
届出が受理されたら届出書が発行されるため、DIPSからダウンロードしましょう。
なお、届出に手数料などはかかりません。
地図画像・地図データの作成方法
リモートID特定区域の届出では、飛行場所を示す地図とGeoJSON形式の地図データの提出も必要です。
どちらも、国土地理院ホームページの地図から取得できます。
地図画像・地図データの作成と取得までの流れは、以下の通りです。
あとは、ダウンロードした地図の画像とデータを届出の作成時にアップロードするだけです。
ちなみに、飛行経路の緯度経度はGeoJSONファイル内に10進法で記載されています。
この緯度経度はクリックした順に記載されているため、クリックした順番と方角を照らし合わせれば、東西南北それぞれの緯度経度を入力する際に役立ちます。
「リモートID特定区域」の届出における注意点
リモートID特定区域の届け出に際して、以下2つの点に注意が必要です。
指定の安全確保措置が必要
リモートID特定区域の届出をして飛行を実施する場合、以下の安全確保措置の実施が必要になります。
| 安全確保措置 | 内容 |
|---|---|
| 補助者の配置 | 以下の対応を行う補助者を配置すること ・ドローンの飛行状況を監視し、特定区域からドローンが逸脱しそうになったら操縦者に助言する ・無届または未確認のドローンが飛来したら必要に応じて操縦者に中止等の指示を行う ※上記の措置が難しい場合は補助者の支持に従ってドローンの飛行を中止する |
| 区画の明示 | 以下のいずれかの措置でリモートID特定区域であることを示すこと ・操縦者からの目視内において、塀・柵・縁石などの目印で特定区域の外縁をすべて示す ・標識(コーンや看板など)を、それぞれの位置から両隣の標識が操縦者から視認できるように設置する ・物理的な外縁措置が難しい場合、空域の範囲を明示した届出書の写しを提示する(目視内での飛行形態に限る) |
届出が受理されても機体登録や許可申請は必要
リモートID特定区域の届出は、特定の区域におけるリモートIDの非搭載を認めてもらうために行うものです。
受理されたからといって、航空法に定められた機体登録や飛行許可・承認の義務は免除されないため注意が必要です。
特定区域や飛行方法が航空法で規制されている場合は、別途許可申請の手続きも行いましょう。
ドローンのリモートIDに関する注意点
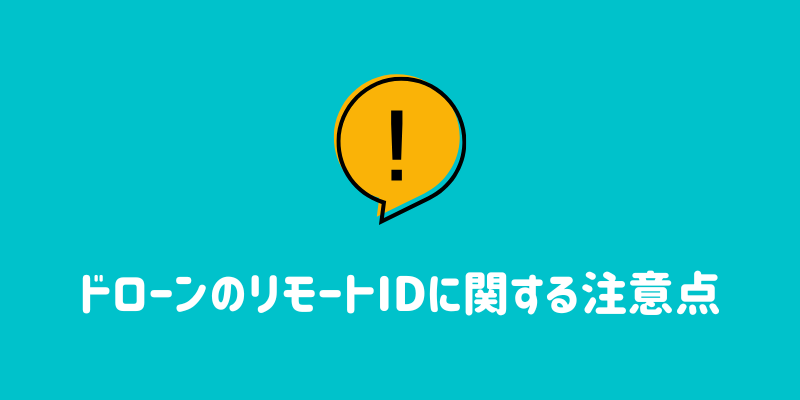
リモートIDを搭載するにあたって、以下の点に注意が必要です。
リモートID機器を使い回す場合は機器情報を変更する
先述したように、外付け型リモートID機器は他の機体に使い回すことも可能です。
しかし他の機体に搭載する場合、DIPSを通して登録済みのリモートID機器情報を変更する必要があります。
変更方法については、リモートIDの実装と設定方法でご紹介した『リモートID「なし」を選んだ場合』の手順で情報を変更しましょう。
ドローンを譲り渡す際は登録情報の変更が必要
また、内蔵型リモートID搭載機種・外付け型リモートID機器のどちらにおいても、DIPS上に登録された情報は所有者本人しか変更できません。
リモートIDが搭載された機種やリモートID機器を譲り受けた場合は、前の所有者に登録情報の変更か削除をしてもらう必要があります。
海外サイトで購入すると非適合と見做される可能性あり
内蔵型リモートIDを搭載したドローンの中には、海外サイトで購入可能な機種もあります。
しかし、リモートIDを搭載しているからといって日本の国土交通省が定めた規定を満たしているとは限りません。
国土交通省の規定に適合している内蔵型リモートID搭載機種は、「適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧」で確認が可能です。
この一覧表に記載されていない機種は、リモートIDを搭載した機種でも非搭載扱いとなり、別途外付け型リモートID機器を用意する必要があります。
受信機はドローンに搭載しない
リモートID機器は、送信機と受信機の2つがあります。
送信機はドローンの識別情報を発信するもの、受信機は送信機から情報を受信するためのものです。
ドローンに搭載する必要があるのは送信機の方なので、購入時と機体に搭載するときはよく確認しておきましょう。
リモートIDに関するよくある質問
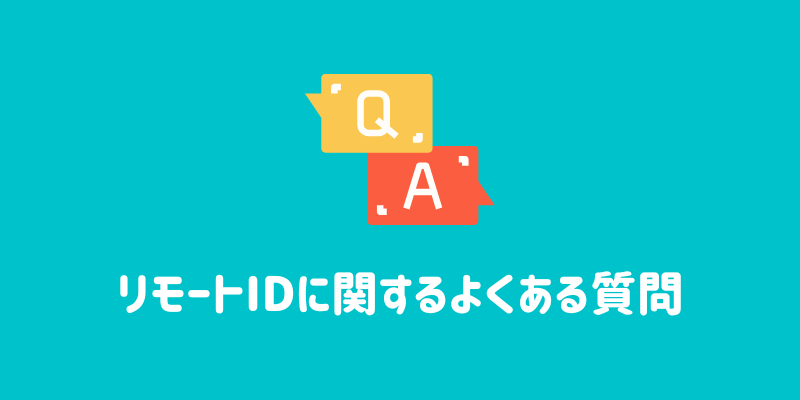
最後に、リモートIDに関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
ドローンにリモートIDは義務ですか?
航空法の適用対象となる、機体重量100g以上のドローンにはリモートIDの搭載が必須です。
対象の機体であるにもかかわらずリモートIDを搭載せずに屋外を飛行させると、航空法違反として50万円以下の罰金が科せられます。
ドローンのリモートIDを調べるには?
リモートIDは、DIPSに情報を登録することで確認できます。
アプリ版のDIPSから登録済みの機体の詳細画面を開き、「発信確認」をタップすると発信情報を確認できます。
ドローンのリモートIDの価格は?
ドローンのリモートID機器は、10,000円~50,000円程度が価格相場です。
安価な機種は多くの場合バッテリーが搭載されていないため、仕様をよく確認のうえ購入しましょう。
リモートIDは使いまわしできますか?
外付け型リモートID機器は、他のドローンにも使い回すことができます。
ただし使い回すときは、DIPSを通して機体情報の変更手続きを行う必要があります。
また、所有者が変わる場合は前の所有者にDIPS上の情報を変更してもらうか、削除してもらいましょう。
ドローンの機体登録をしないとどうなる?
機体重量100g以上のドローンは、機体登録をせずに屋外を飛行させると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
私有地内での飛行も罰則の対象となるため、対象のドローンを屋外で飛行させる場合は必ず機体登録を済ませておきましょう。
ドローンのリモートIDが免除される条件は?
ドローンのリモートIDの搭載義務が免除される条件は、以下の3つです。
- 事前登録期間中(2022年6月19日まで)に機体登録を済ませている場合
- 「リモートID特定区域」で届出済みの区域内で安全措置を講じて飛行させる場合
- 十分な強度を持つ紐で係留飛行する場合
なお、「リモートID特定区域」の届出は誰でも可能ですが、区域内の外縁を塀や柵などで完全に覆い、特定区域であることを分かりやすく示す措置が必要です。
そのため、一般の方が飛行の度に届出をすることは現実的ではありません。
事前登録期間が過ぎた今となっては、個人かつ趣味目的でドローンを飛ばしたい場合、実質的にリモートIDの搭載が必須と考えて良いでしょう。
ドローンが内蔵型リモートID搭載機種かどうか確認する方法は?
すでに所有しているドローン、または購入を検討しているドローンが内蔵型リモートID搭載機種かどうかを確認する方法は、以下の2通りがあります。
- 国土交通省が公表しているリモートID機器一覧表を見る
- メーカーの公式サイトで確認する
国土交通省は、適合していると届出があったリモートID機器のメーカー・型式名の一覧を公表しています。
その一覧表で、備考に「機体へ内蔵」の旨と共に掲載されている機種であれば内蔵型リモートID搭載機種です。
登録記号とリモートIDの違いは?
登録記号とはドローンの機体登録が完了すると発行される、「JU」から始まる記号です。
自動車でいうナンバー(自動車登録番号)の役割があり、機体に物理的な方法で明示するだけでなく、リモートID機器にも登録のうえ飛行時に発信する必要があります。
つまり、登録記号は「ドローンに付与される識別情報のひとつ」、リモートIDは「登録記号を含む識別情報を発信する機能」です。
機体登録の際にリモートID機器の情報を入力しておくと、登録記号が発行された際にスムーズに情報を紐づけることができます。
リモートIDの発信情報には個人情報が含まれる?
リモートIDの発信情報には、個人の特定につながる情報は含まれません。
発信される情報は、機体の識別に必要な情報と飛行時の位置・高度・速度といった情報のみです。
まとめ
ドローンにおける「リモートID」とは、機体の識別情報を発信する機器のことです。
発信情報は警察・重要施設関係者・航空局など特定の機関の他、対応している通信規格の端末を所有していればドローンの所有者本人も確認できます。
リモートIDは100g以上かつ屋外で飛行させるドローンならほぼ搭載が必須であり、搭載しないと罰則の対象となるため注意しましょう。
リモートIDには内蔵するタイプと外付けするタイプがありますが、趣味程度の飛行を楽しむなら全車、産業用ドローンを活用するなら後者がおすすめです。
これからドローンを始める人、リモートIDの搭載義務が開始されてから初めてドローンを使う人は、本記事を参考に正しくリモートIDを実装して安全な飛行を実施しましょう。
この記事と一緒によく読まれている記事
-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント
-
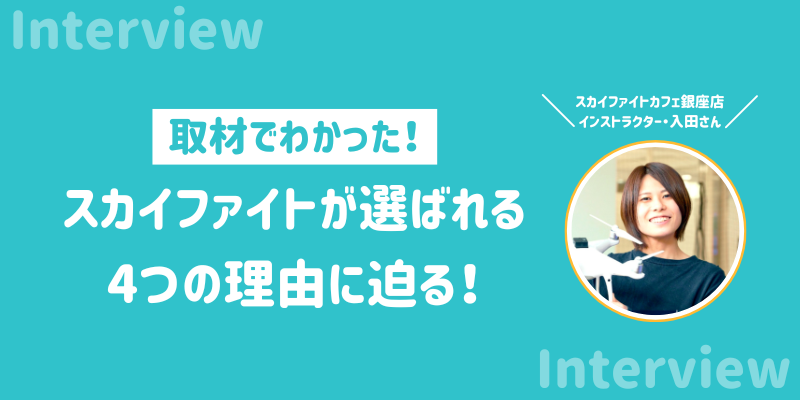
オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由
-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング
-
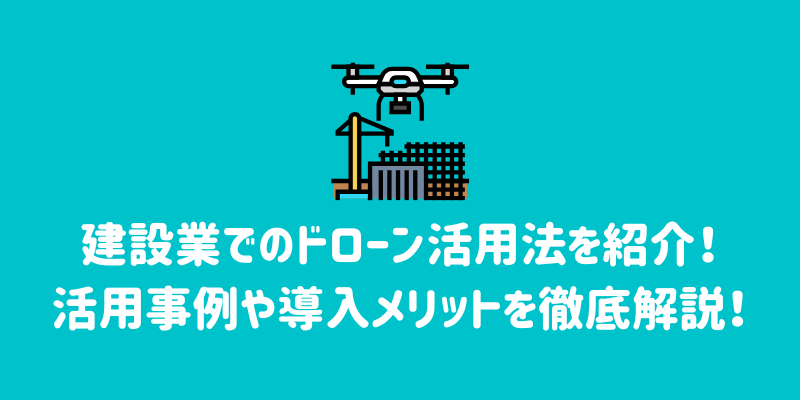
建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!
-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!
-
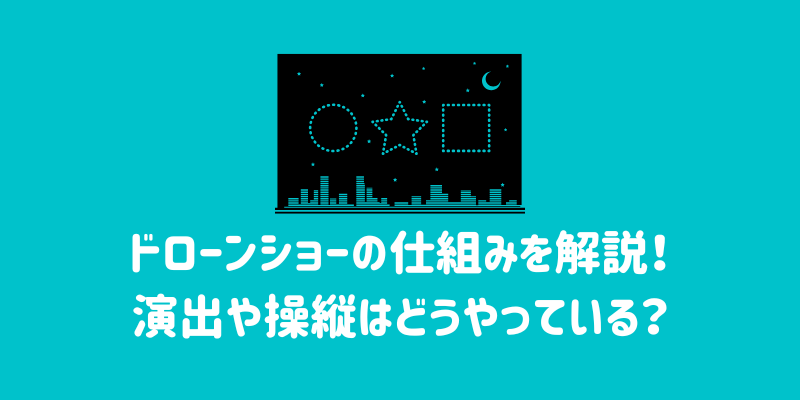
ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?
-
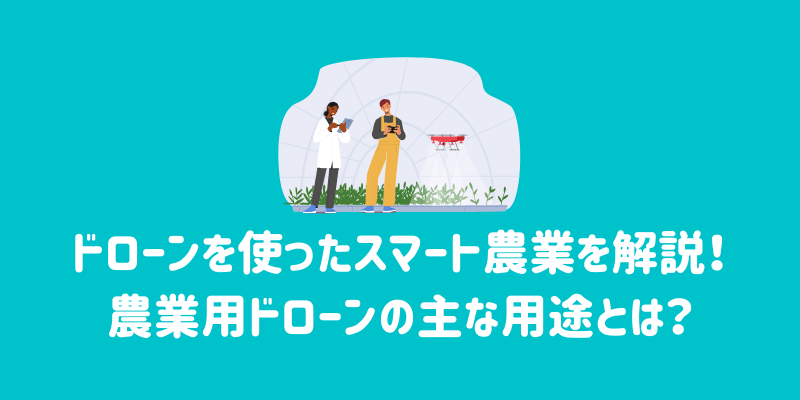
ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?
-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる
-
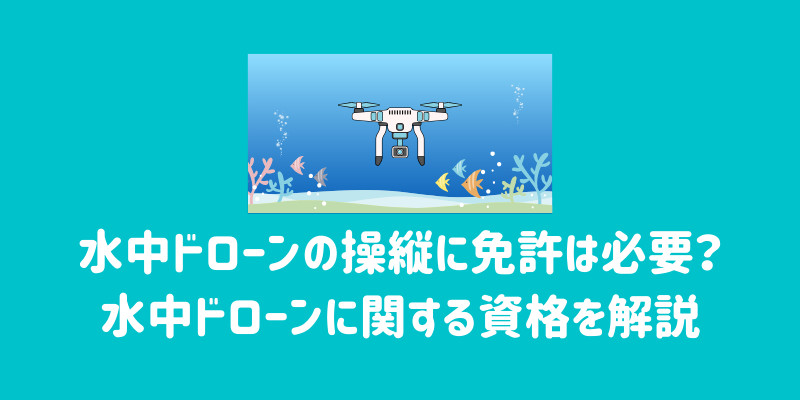
水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説
-
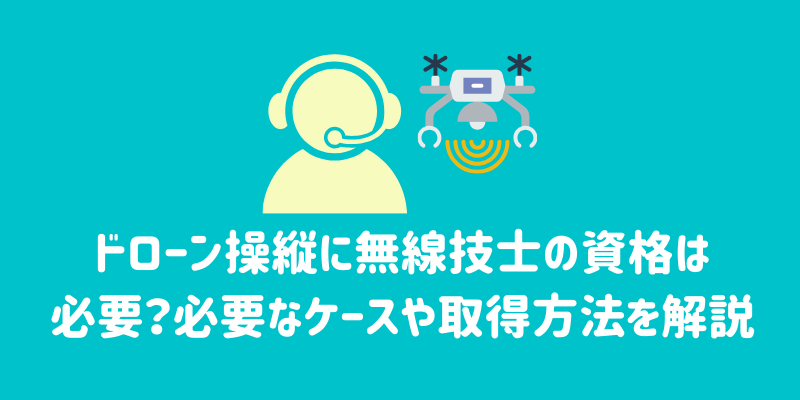
ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!
-
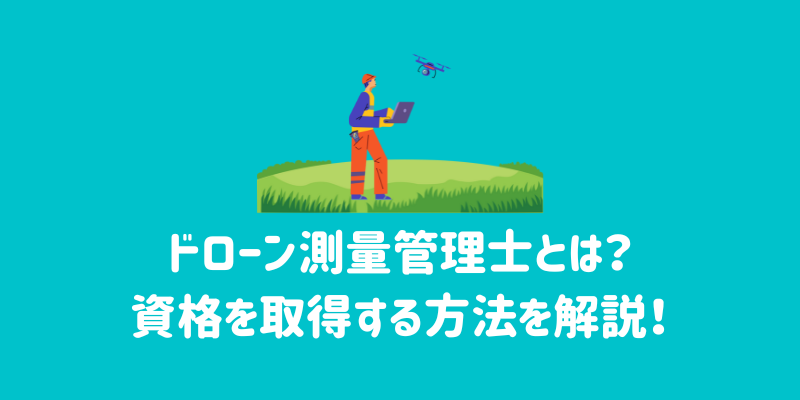
ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!
-
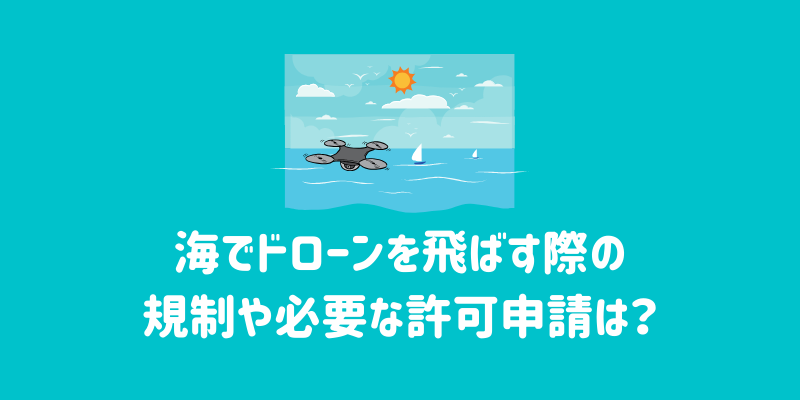
海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説