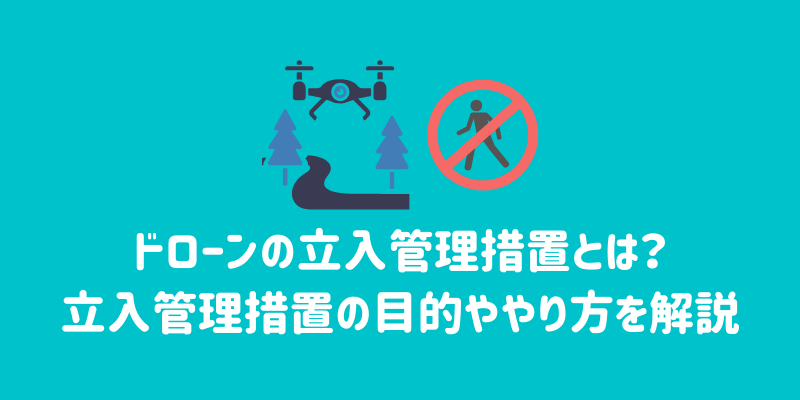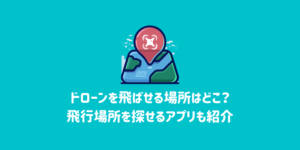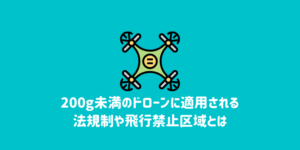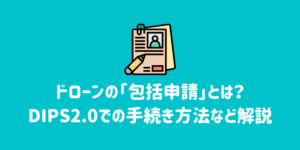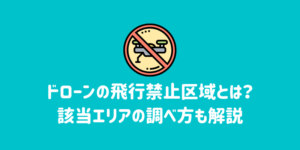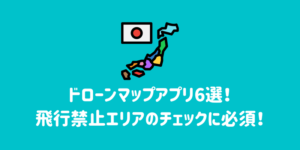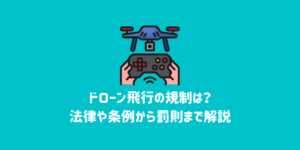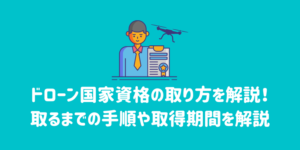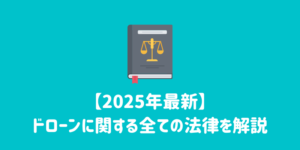ドローンの飛行場所・飛行方法によっては、「立入管理措置」を実施する必要があります。
しかし立入管理措置という言葉だけでは、具体的に何をすべきなのかイメージできない方も多いことでしょう。
今回はドローンの立入管理措置とは何か、必要なケースや具体的な方法、DIPSでの設定方法などについて詳しく解説いたします。
ドローンの立入管理措置とは?
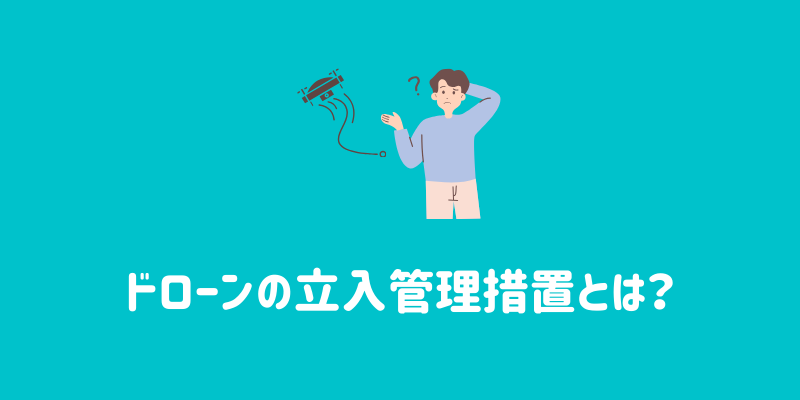
ドローンの立入管理措置とは、ドローンの飛行経路に第三者が立ち入らないようにするために管理する措置のことです。
航空法で規制されていない場所・方法でドローンを飛ばす場合は不要ですが、規制対象となっている一部の場所・方法でドローンを飛ばすなら、立入管理措置の実施が義務付けられています。
まずは、航空法で規制されている場所・方法や第三者の定義について理解しておきましょう。
飛行カテゴリーの分類
航空法では、ドローンを含む無人航空機の飛行場所・飛行方法に応じて「カテゴリー」という区分を設けています。
カテゴリーはⅠ~Ⅲの3つが設けられており、数字が高いほど許可・承認や資格取得などが求められる高度な飛行です。
各カテゴリーの具体的な内容は、以下の通りです。
| カテゴリー | 内容 |
|---|---|
| カテゴリーⅠ飛行 | 航空法で規制されていない場所・方法での飛行。 国土交通大臣からの許可・承認や立入管理措置は不要。 |
| カテゴリーⅡ飛行 | 航空法で規制されている場所・方法での飛行。 国土交通大臣からの許可・承認と立入管理措置が必要 ※二等無人航空機操縦士・第二種機体認証の取得で許可・承認が不要になる場合がある |
| カテゴリーⅢ飛行 | 航空法で規制されている場所・方法での立入管理措置を行わない飛行、「レベル4飛行」に該当する飛行。 国土交通大臣からの許可・承認と一等無人航空機操縦士・第一種機体認証の取得が必要 |
立入管理措置が必要となるのは、カテゴリーⅡ飛行に該当する場所・方法での飛行です。
第三者とは?
ドローンの飛行における「第三者」については、国土交通省から明確に定義が示されています。
第三者とはドローンの飛行に直接または間接的に関与していない人のことです。
逆に、無人航空機の操縦者・補助者(飛行の安全確保に必要な人)や操縦者と共通の飛行目的を持っている人は第三者に該当しません。
第三者に該当しないとみなされるには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 飛行の安全上従うべき明確な指示や注意を受けていること
- 上記を適切に理解(確認)していること
- 飛行の全部または一部に関与するかどうかを自ら決定できること
立入管理措置が必要なのは「特定飛行のうち有人上空を飛行しないもの」
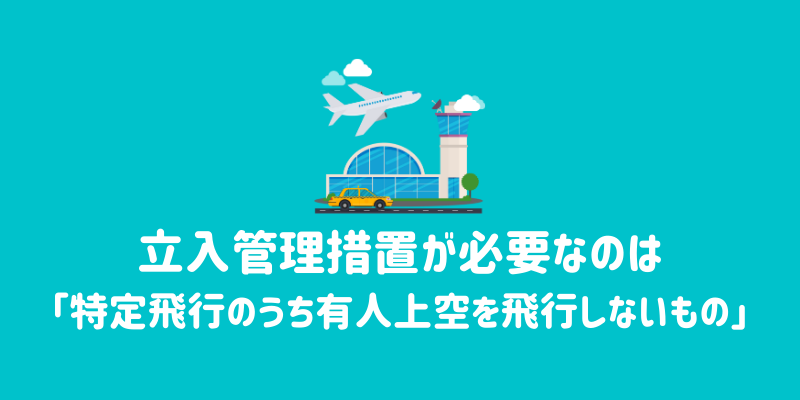
立入管理措置が必要とされる、カテゴリーⅡ飛行について詳しく解説いたします。
カテゴリーⅡ飛行とは、「特定飛行」と呼ばれる航空法で規制された場所・方法を有人地帯上空で実施しない場合を指します。
特定飛行の一覧
特定飛行には、場所と方法を合わせて10通りあります。
| 場所 | ・空港周辺の空域 ・上空150m以上 ・DID(人口集中地区)上空 ・緊急用務空域 |
| 方法 | ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・30m未満 ・イベント上空 ・危険物輸送 ・物件投下 |
上記を立入管理措置を講じたうえで実施するならカテゴリーⅡ飛行、立入管理措置を講じないで実施するならカテゴリーⅢ飛行になります。
なお、カテゴリーⅢ飛行を実施するなら取得難易度の高い一等無人航空機操縦士・第一種機体認証が必要です。
これらの取得が難しい一方で特定飛行を実施したいなら、カテゴリーⅡ飛行とするために立入管理措置が必須となります。
新設された「レベル3.5飛行」では立入管理措置が不要
ドローンの飛行における分類には、カテゴリーの他に「レベル」もあります。
レベルとは主に「目視内か目視外か」「操縦か自律か」「無人地帯か有人地帯か」という観点から、飛行の難易度を1~4の区分に分けたものです。
- レベル1飛行:目視内の操縦飛行
- レベル2飛行:目視内の自律飛行
- レベル3飛行:無人地帯の目視外飛行
- レベル4飛行:有人地帯の目視外飛行
上記のうち、レベル3飛行の実施には立入管理措置が必要です。
しかし2023年12月に「レベル3.5飛行」が新設され、以下の条件を満たせば立入管理措置なしでもレベル3に該当する飛行が実施できるようになりました。
- 無人航空機操縦者技能証明の保有
- 第三者賠償責任保険の加入
- 機上カメラで歩行者の有無を確認できるドローンの使用
なお、レベル3飛行の実施には立入管理措置以外にも必要な要件があります。
レベル3.5飛行に必要な条件を満たしても、立入管理措置以外の要件までもが撤廃されるわけではないため注意が必要です。
ちなみに、カテゴリーとしてはレベル3とレベル3.5のどちらも「カテゴリーⅡ飛行」に該当します。
ドローンの立入管理措置の具体的な方法
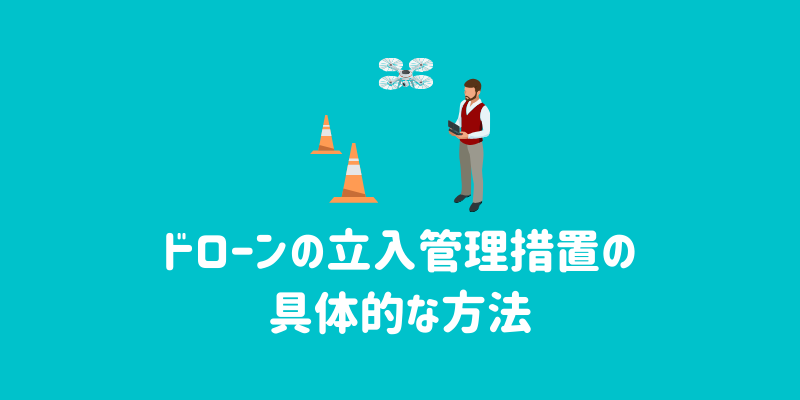
立入管理措置が必要な飛行を実施する際、飛行許可申請にて具体的な管理方法の申告が求められます。
その際に選択できる立入管理措置の方法は、以下の通りです。
補助者(人)を配置する
ドローンの飛行における補助者とは、飛行経路周辺に第三者や有人機などが侵入していないことを常に監視するための人員です。
補助者は必要に応じて、第三者やドローンの操縦者に注意喚起をして事故を未然に防ぎます。
また、飛行中の自機や自機周辺の気象状況も監視し、安全運航に必要な情報をドローンの操縦者へ助言することも役割です。
航空局標準マニュアル02では、安全を確保するために必要な体制として「安全確保に必要な人数の補助者を配置して相互に確認を行うこと」と明記されています。
つまり、立入管理措置の中でも補助者の配置は最も必要性の高い措置として扱われています。
看板やフェンス(物)などを配置する
看板やフェンス、第三者の立ち入りを制限する旨の看板やコーンなどの物を飛行経路・周辺環境に併せて配置する方法です。
上記で立入管理区画を明確に示し、第三者の立入を確実に制限できる場合、補助者の配置に代えることが可能と航空局標準マニュアル02に記されています。
広範囲に及ぶ飛行や住宅街での飛行など、物だけでは第三者の立ち入りを制限しきれない環境なら補助者の配置も検討すべきです。
ネットやポスターなどで飛行に関する情報を周知させる
無人地帯での目視外飛行(レベル3飛行)にかかる要件のひとつに、「立入管理区画又は機上装置・地上設備」があります。
ドローンの飛行に関する情報の周知は、その要件を満たすために必要な立入管理措置です。
具体的には、立入管理区画に看板などの物理的な目印で第三者への注意喚起を行うとともに、インターネットやポスターでその事実を近隣住民・地域関係者などに対し広く周知します。
周知の際は問い合わせ先も明示しましょう。
立入管理区画に第三者が存在する可能性が排除できない場合は?
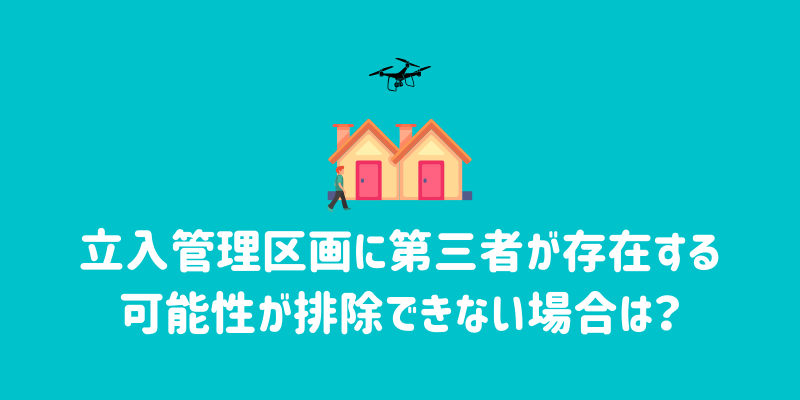
ドローンを飛ばす場所によっては、上述した立入管理措置を講じても区画内に第三者が入る・存在することを免れられない場合があります。
レベル3飛行の実施要件としては、そのような場合追加の立入管理措置を講じるように記されています。
以下より、道路・鉄道・家屋が含まれる立入管理区画における追加措置の例をご紹介いたします。
立入管理区画に道路が含まれる場合
立入管理区画に道路が含まれており、歩行者・自転車・自動車などが区画内に入ると予想される場合は、当該場所にカメラや補助者を設置します。
そのうえでドローンの飛行中は状況を常に監視し、必要に応じて飛行の中止や経路の変更など適切に対応しましょう。
立入管理区画に鉄道が含まれる場合
立入区画に鉄道が含まれる場合は、当該の鉄道事業者と事前に調整を行い、鉄道の運行時間にはドローンを飛行させないようにします。
もちろん飛行経路全体を監視できる補助者も配置し、列車の時刻表を持参のうえ列車が通過しない時間帯を把握したうえで飛行を実施しましょう。
立入管理区画に家屋が含まれる場合
立入管理区画に家屋が含まれる場合、当該家屋の各住民や関係者へ個別に説明を行います。
すべての住民や関係者から理解を得ると共に、看板などで飛行日時などを掲示のうえ飛行を実施しましょう。
DIPS2.0で立入管理措置の設定をする方法
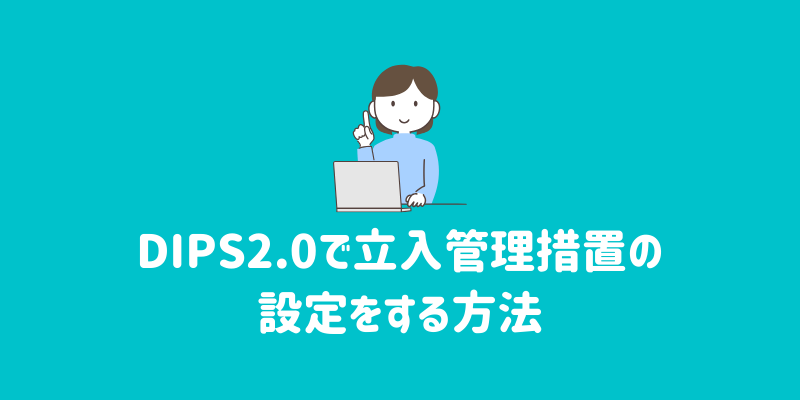
先述したように、国土交通大臣への飛行許可申請を行う場合はその飛行における立入管理措置の方法を申告する必要があります。
許可申請には窓口へ必要書類を提出・郵送する方法とDIPS(ドローン情報基盤システム)からオンライン申請する方法がありますが、好きなタイミングで比較的簡単に申請できる後者がおすすめです。
DIPSで飛行許可申請する場合、システム上に表示される必要項目の入力を進めていくと立入管理措置を設定できます。
具体的な手順は、以下の通りです。
立入管理措置の有無と具体的な方法については、以下の選択肢が表示されます。
- 補助者の配置
- 立入管理区画の設定
- 立入管理区画の設定(レベル3飛行を行う場合)
- 立入禁止区画の設定
- その他
基本的には補助者の配置を選択しますが、看板やフェンスなどの物を設置する場合は立入管理区画を選択します。
ただしレベル3飛行を行うためにその要件を満たす立入管理区画を設定するなら、(レベル3飛行を行う場合)とある立入管理区画を選択しましょう。
飛行カテゴリーが判明したら、同じくDIPS上で飛行許可申請を行います。
飛行許可申請の際も表示されている必要項目の入力を進めていきますが、その際に改めて立入管理措置の方法について問う項目があります。
カテゴリー判定の際に回答した内容が反映されており、変更できない箇所もある点は留意しておきましょう。
ドローンの立入管理措置に関するよくある質問
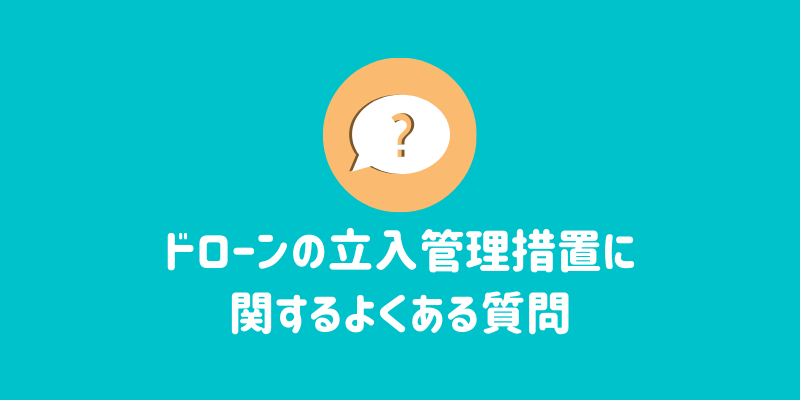
最後に、ドローンの立入管理措置に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
立入管理措置はどれぐらいの範囲が適切?
立入管理措置が必要とされるレベル3飛行では、基本的に「第三者が存在する可能性が低い場所」のうち、実際の飛行経路に応じて立入管理区画を設定します。
具体的には、ドローンが落下し得る範囲を考慮のうえ設定する必要があります。
メーカーが算出・保証した距離や機体の性能・形状・運用方法などを踏まえ、落下範囲が最大となる条件下で算出した距離を立入管理区画と定めましょう。
立入管理措置を行わずに特定飛行を行うとどうなる?
レベル3飛行を含むカテゴリーⅡ飛行において、立入管理措置を講じずに飛行を実施すると航空法違反となります。
航空法第157条に基づき、50万円以下の罰金が科せられる恐れがあるため注意が必要です。
立入管理区画に第三者が近づいてきたら?
万が一ドローンの飛行中に立入管理区画へ第三者が近づいてきたら、ただちに安全処置が必要です。
安全処置の例としては、以下の対応が挙げられます。
- 飛行の停止
- 安全な場所への着陸
- 飛行経路の変更
- その他必要な措置
立入管理措置を行わずに特定飛行を行うには?
立入管理措置を行わずに実施する特定飛行は、「カテゴリーⅢ飛行」に該当します。
カテゴリーⅢ飛行を実施する場合、国家資格である一等操縦者技能証明の取得と、飛行させる機体の第一種機体認証の取得が必要です。
さらに飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づくマニュアル作成を含む、運行管理を適切に行っていることを確認し、その都度国土交通大臣の許可・承認を得ることで実施できます。
まとめ
立入管理措置とは、ドローンの飛行経路に第三者が立ち入らないよう管理するための措置です。
航空法で規制されている場所・方法を無人地帯であれば立入管理措置などの要件を満たすことで実施できるようになります。(カテゴリーⅡ飛行)
立入管理措置の具体的な方法としては主に補助者の配置が挙げられますが、他にも看板やフェンスなどの物で区画を明示したり、近隣住民や関係者へネットやポスターなどを通じて周知したりといった方法もあります。
カテゴリーⅡ飛行であるにもかかわらず立入管理措置を怠ると、航空法違反として罰則の対象となるため注意が必要です。
その他要件や関連する法令をしっかりと把握のうえ、安全で適切な運行管理のもとドローンを飛行させましょう。
この記事と一緒によく読まれている記事
-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント
-
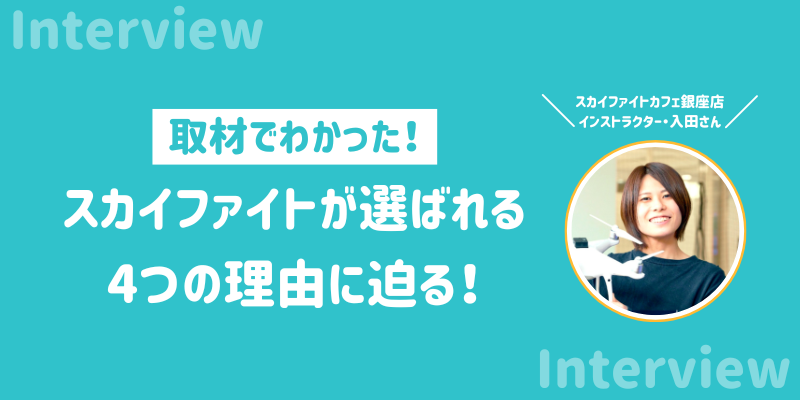
オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由
-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング
-
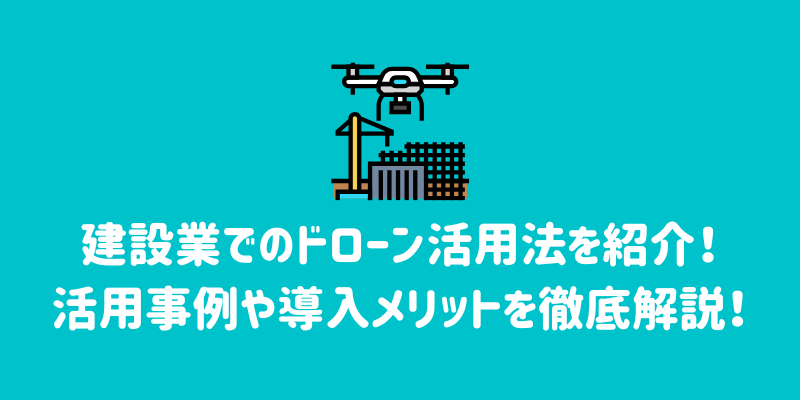
建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!
-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!
-
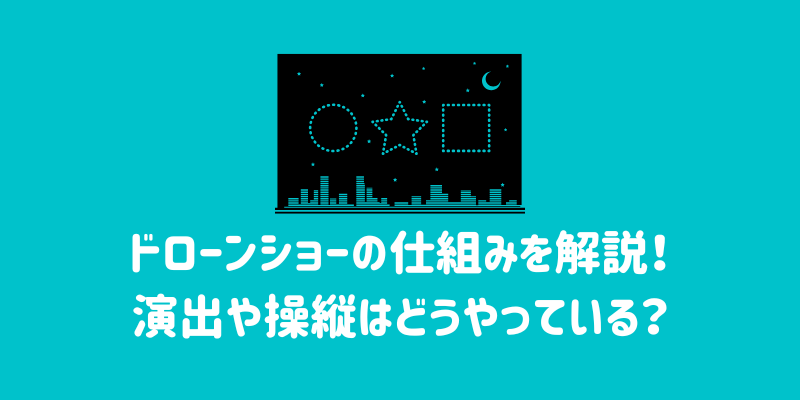
ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?
-
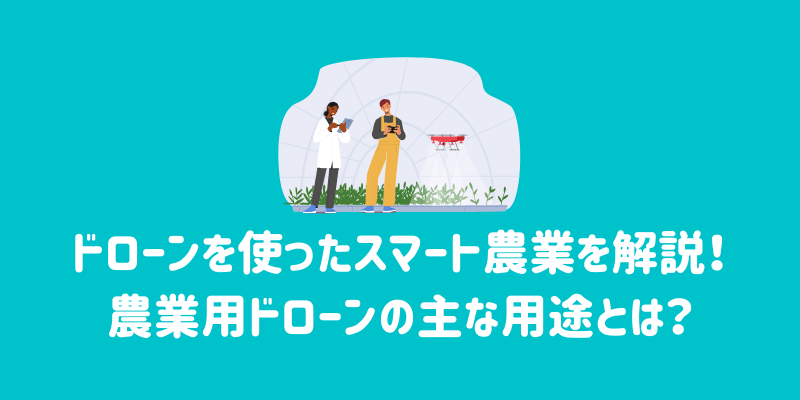
ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?
-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる
-
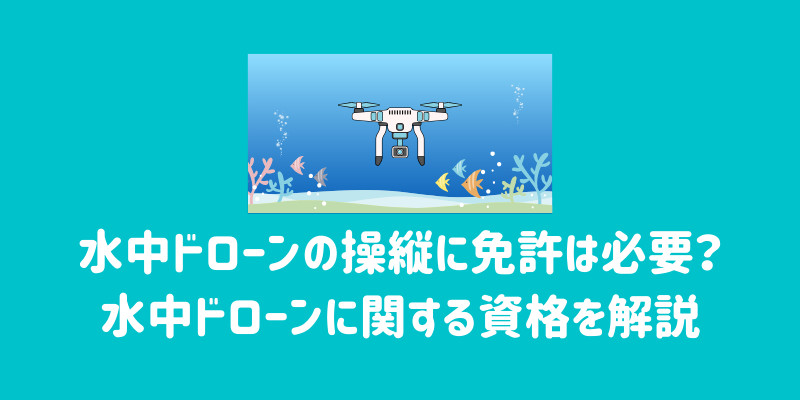
水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説
-
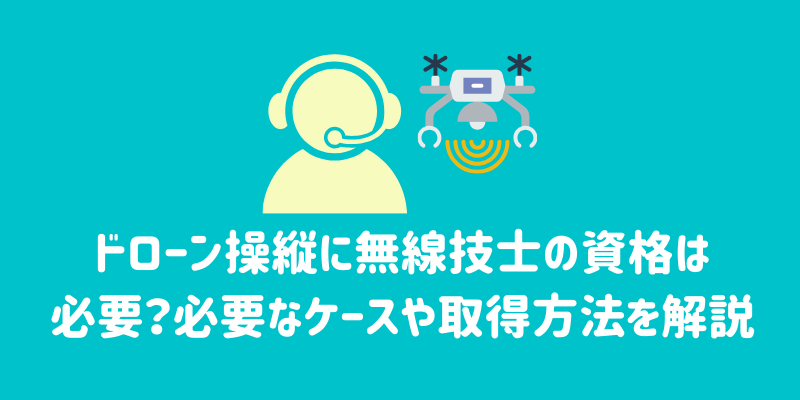
ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!
-
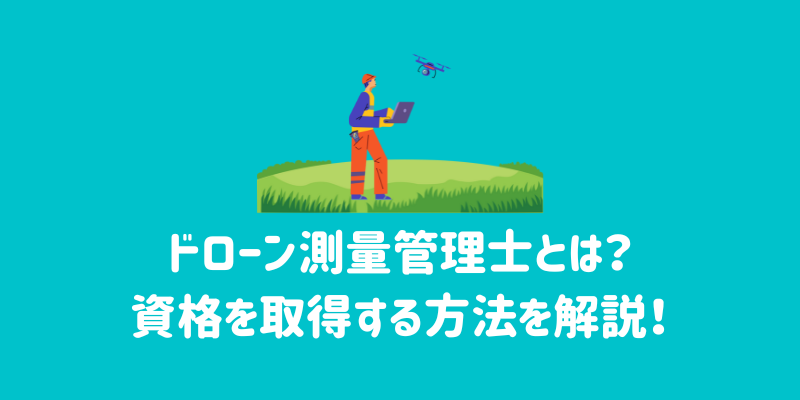
ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!
-
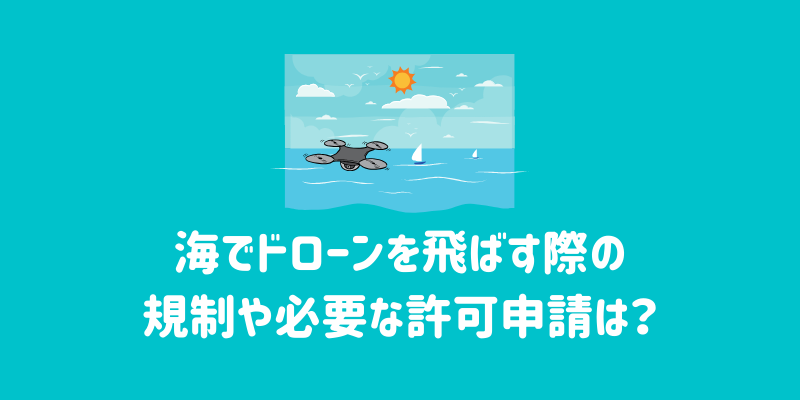
海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説