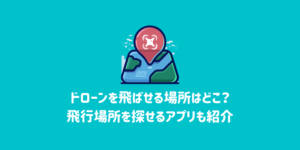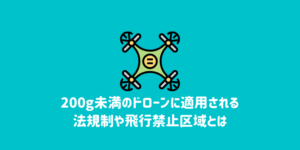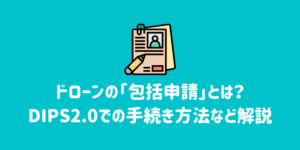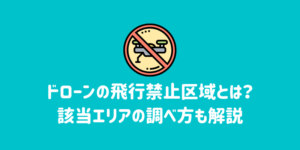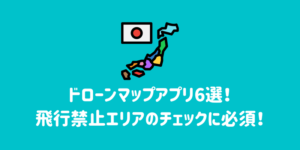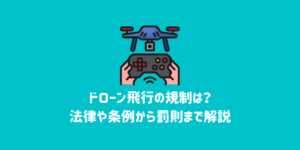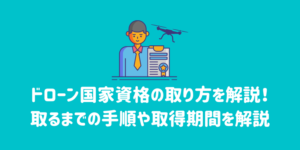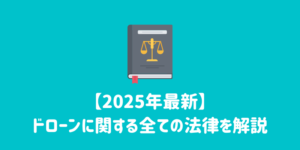従来の航空法では、ドローンの飛行技術についてレベル1~4までの4区分が設けられていました。
しかし2023年12月にレベル3飛行の要件を緩和した「レベル3.5飛行」が新設され、よりドローンを業務活用しやすい環境へと変化しています。
今回はレベル3.5飛行とは具体的に何なのか、定義・運用方法・必要な資格などのポイントから分かりやすく解説いたします。
他にも他レベルとの違い・申請方法・レベル3.5飛行が新設された今後の展望などについても解説していますので、ぜひ本記事でレベル3.5飛行の理解を深めてください。
レベル3.5飛行とは
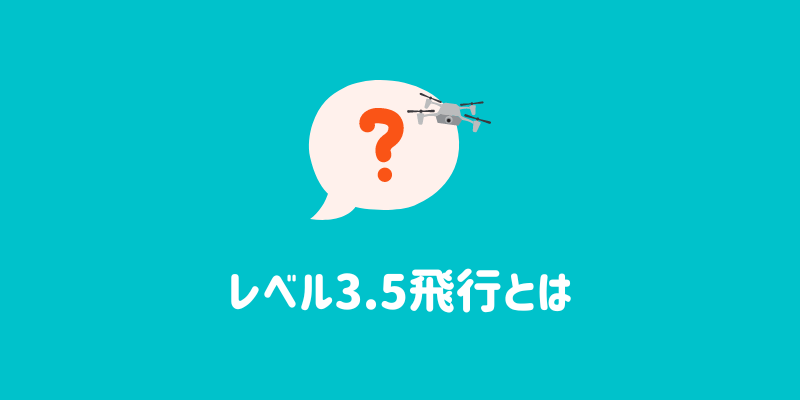
航空法では、ドローン(無人航空機)の飛行技術についてレベル1~4の区分を設けています。
従来は4つの区分となっていましたが、2023年12月にレベル3から派生した「レベル3.5」という区分も新たに設けられました。
まずは、レベル3.5飛行の具体的な内容について紐解いていきましょう。
レベル3.5飛行の定義
レベル3.5飛行の定義を知るには、レベル3飛行の要件を把握しておく必要があります。
レベル3飛行とは、「無人地帯(山林・河川・利用など)での目視外による自律飛行」を指すドローンの飛行の区分です。
十分な飛行実績を持つ機体の使用や飛行に応じた安全対策の実施、第三者の立入管理措置(補助者の配置や看板での周知など)などの要件を満たすことで、レベル3飛行の実施が可能となります。
しかしある条件を満たすことで、一部の要件を満たさなくてもレベル3飛行の実施が認められるというものがレベル3.5飛行です。
つまりレベル3.5飛行は、レベル3飛行における緩和措置制度と認識して良いでしょう。
レベル3.5の特徴と運用方法
レベル3.5飛行では、以下の条件を満たせばレベル3飛行の要件である「立入管理措置」が不要になります。
- 無人航空機操縦者技能証明の保有
- 第三者賠償責任保険の加入
- 機上カメラで歩行者の有無を確認できるドローンの使用
さらに道路や線路の上空を横断する際は一時停止のうえ車両が通らないか確認する必要がありましたが、その確認も不要になります。
なお、厳密には条件を満たすことで従来のレベル3飛行に必要だった、補助者の配置や看板での周知などによる立入管理措置が撤廃されるというルールです。
第三者の立ち入り制限自体はレベル3.5飛行でも必要となり、従来の手段の代わりとしてカメラを備えたドローンの使用という条件が設定されています。
レベル3.5飛行に必要な証明・資格
レベル3.5飛行の条件として定められている「無人航空機操縦者技能証明」とは、いわゆるドローンの国家資格のことです。
国家資格には一等資格・二等資格という2種類の区分がありますが、レベル3.5飛行であればどちらを取得しても問題ありません。
ただし、目視内飛行の限定解除を受けたものである必要があります。
ちなみに、機体認証の取得は従来のレベル3飛行と同じく不要です。
レベル3.5が新設された背景
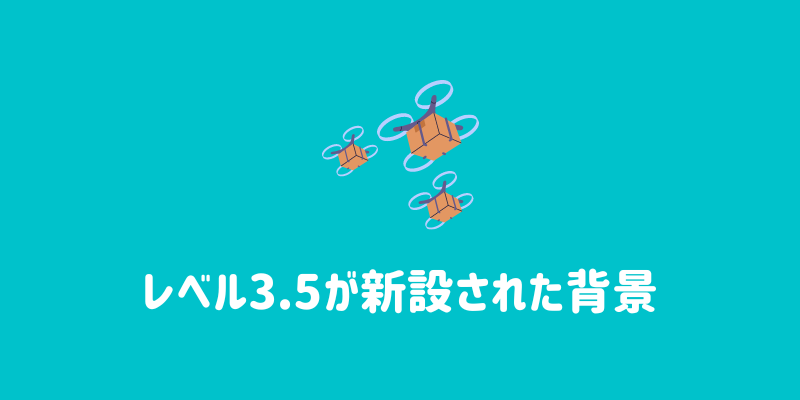
なぜ後になってレベル3.5飛行が新設されたされたのか、その主な理由としては以下の2つが挙げられます。
ドローン技術の進化による安全性の向上
近年のドローン、特に産業用機種の開発技術は国内でも着実に進化を遂げています。
カメラ性能や映像伝送技術の向上に伴い、補助者による監視や看板による物理的な立入制限をしなくても無人地帯が確保できると認められました。
そのため機上カメラから伝送される映像を地上に設置したモニターで監視するという措置を取れば、従来の立入管理措置に代わる安全策とみなされ、レベル3に該当する飛行が可能となるのです。
商業利用の促進
ドローンに関わる法整備が進み、国内でも商業分野におけるドローンの普及が少しずつ拡大しています。
特に物流業界では、深刻化する人手不足問題をドローンの導入で解決に導けると期待されています。
しかしドローンを用いた配送の多くはレベル3以上の飛行が必須となる一方で、要件のひとつである立入管理措置を講じる手間がハードルとなっていました。
事業者にとってドローンを導入するハードルとなり得る立入管理措置を、一定条件のもと撤廃することでさらに商業利用を促進させることも、レベル3.5飛行新設の目的です。
レベル3.5の導入によって変わること

レベル3.5飛行が導入されたことで、無人地帯でドローンを自動飛行することが比較的容易になりました。
また、道路や鉄道上空でのスムーズな飛行も可能となっています。
これにより、従来は難しいとされていた物資輸送や道路・線路の点検といった分野にもドローンを活用しやすくなりました。
また、レベル4飛行が可能になること(一等資格の場合)や飛行許可申請の簡略化以外にも、ドローンの国家資格を取得するメリットが生まれたことも変化のひとつです。
レベル3.5飛行と他レベル飛行との比較
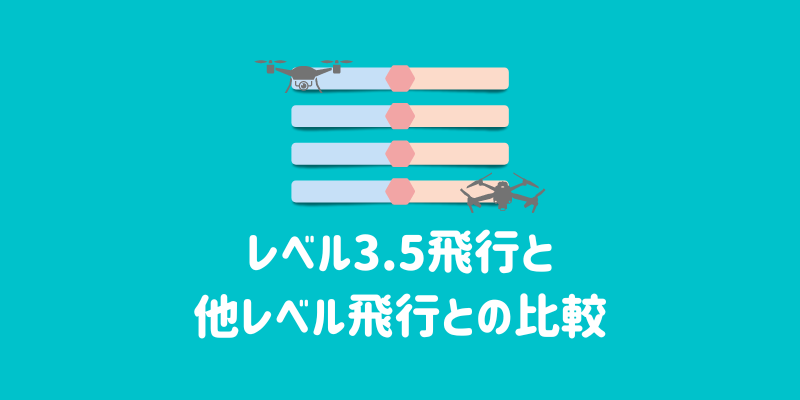
レベル3.5飛行は他のレベルと具体的に何が違うのでしょうか。
レベル4とレベル3以下の2通りに分けて、他レベルとの違いについて解説いたします。
レベル3.5とレベル4の違い
レベル4飛行とは、「有人地帯の目視外飛行」を指します。
レベル3.5飛行と同じく目視外飛行ではありますが、実施場所が有人地帯であることが特徴です。
また、必要資格は無人航空機操縦者技能証明の一等資格に限られること、第一機体認証の取得が必要なことも大きな違いです。
レベル3.5とレベル3以下の違い
レベル3.5飛行とレベル3飛行の内容は同一ですが、先述したように立入管理措置や道路・線路上空での一時停止の有無が主な違いです。
レベル2飛行は目視内での自動飛行、レベル1飛行は目視内での操縦飛行を指し、どちらも目視内でドローンを飛行させる必要がある点がレベル3.5飛行と異なります。
レベル3.5飛行の申請方法
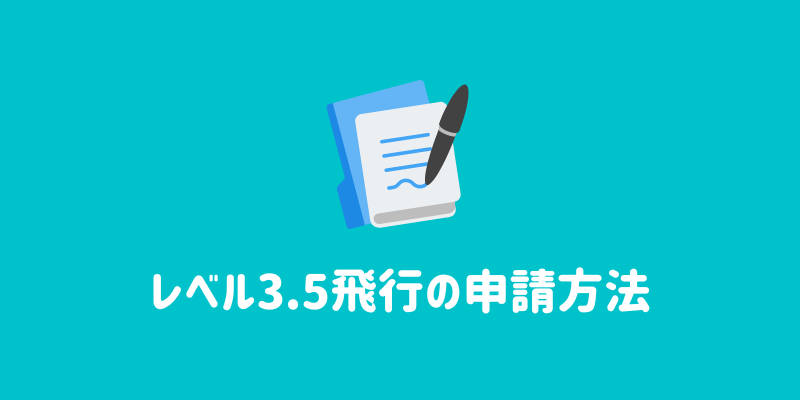
レベル3.5飛行の実施には国土交通省航空局への許可申請が必要ですが、当面の間は通常と異なる申請方法が適用され、より簡単に許可・承認を得ることができます。
必要書類についても、通常の申請に必要だった資料の一部が不要・簡素化されています。
レベル3.5飛行の実施に必要な書類は、以下の通りです。
- 様式1:無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(カテゴリーⅡ飛行)
- 様式2:無人航空機の機能・性能に関する技術適合確認書
- 様式3:無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 別添資料:無人航空機の追加基準への適合性
- 別添資料:無人航空機を飛行させる者一覧
- 別添資料:無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
ただし、上記以外にも航空局から求められた書類があれば必要になります。
必要書類を用意したら、以下の手順で申請手続きを行います。
運航概要宣言書とはレベル3.5飛行の概要・操縦ライセンスの保有・保険加入・機上カメラなど実施に必要な要件を満たしていることを、航空局に宣言するものです。
航空局相談窓口へ相談のうえ、受け取った書式を元に運航概要宣言書を作成・提出・調整することで、通常よりも手続きを簡素化することができます。
今後の展望

レベル3.5飛行の新設により、商業分野におけるドローンのさらなる普及拡大が見込まれます。
ドローンの商業活用を促進させる法整備が進んでいるのは、年々拡大しているドローン市場の傾向が要因として大きいです。
インプレス総合研究所が公開した「ドローンビジネス調査報告書2024」では、2023年度における国内のドローンビジネスの市場規模は3854億円と推測されており、前年度比23.9%増という結果になりました。
2028年度には9,340億円にまで達すると予想されており、成長し続けるドローン市場と着実に進む法整備が相まって、国内の各所で産業用ドローンが上空を飛ぶ光景が当たり前となる未来に期待できます。
レベル3.5に関するよくある質問
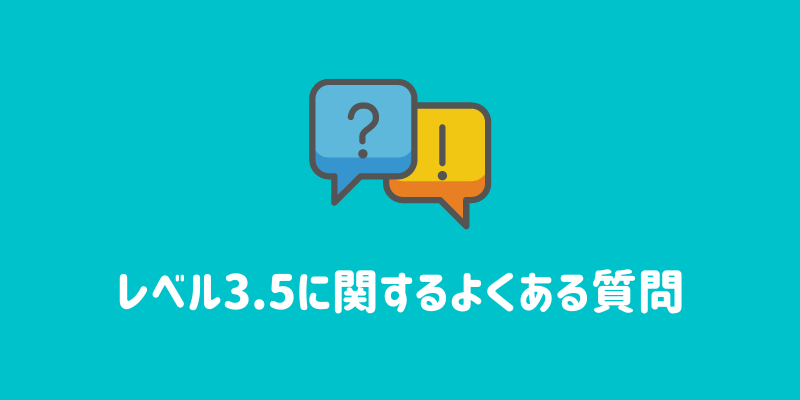
最後に、レベル3.5飛行に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
ドローンのレベル3では何ができますか?
ドローンのレベル3飛行は、立入管理措置など必要な要件を満たすことで「無人地帯での目視外飛行」が可能になります。
レベル3.5飛行の導入後は、国家資格の取得・保険の加入・機上カメラによる監視により、立入管理措置なしでレベル3飛行を実施することができます。
レベル4飛行とは何ですか?
レベル4飛行とは、「有人地帯での目視外飛行」を指す区分です。
実施には国家資格(一等資格)や第一種機体認証の取得、飛行ごとの許可申請が必要になります。
まとめ
2023年12月に新しく導入されたレベル3.5飛行とは、一定の条件を満たせば立入管理措置をしなくてもレベル3飛行の実施が可能になるという、要件緩和制度のようなものです。
これにより過疎地をはじめとする国内各所での物資輸送や、道路・線路の点検にドローンが導入しやすくなり、さらなる普及拡大と市場の成長が見込まれます。
従来のレベル3飛行では実施のハードルが高く事業のドローン活用を躊躇していた事業者にとっても、レベル3.5飛行の導入は良い機会となることでしょう。
この記事と一緒によく読まれている記事
-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント
-
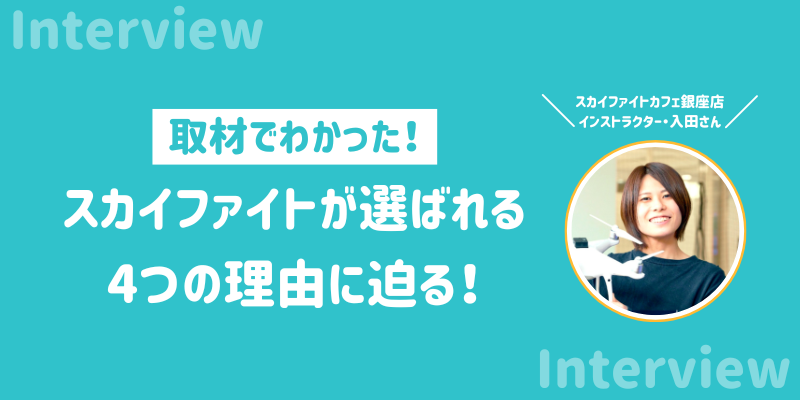
オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由
-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング
-
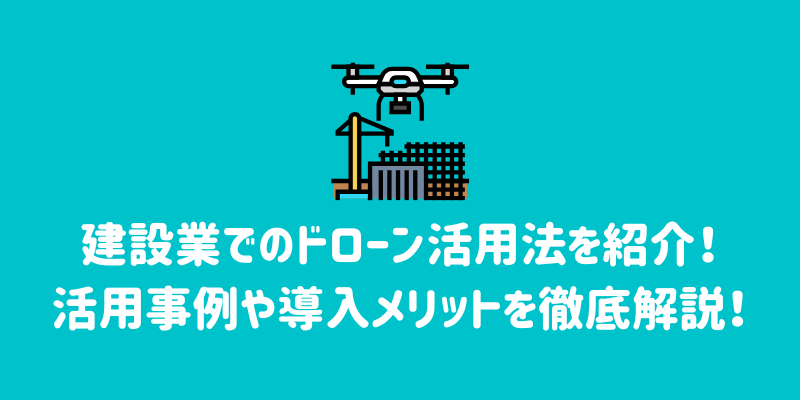
建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!
-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!
-
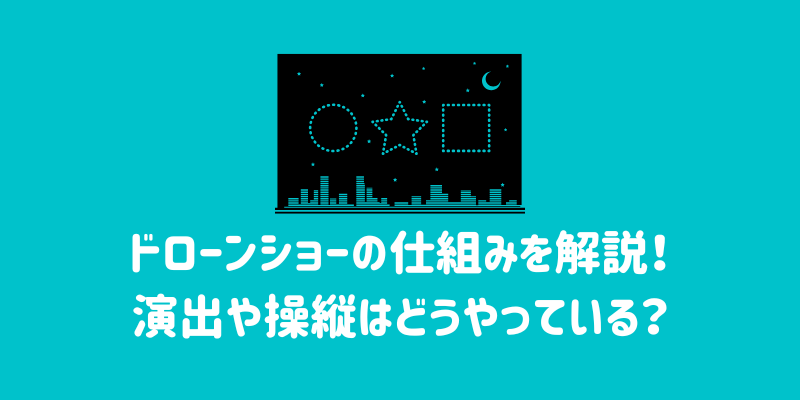
ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?
-
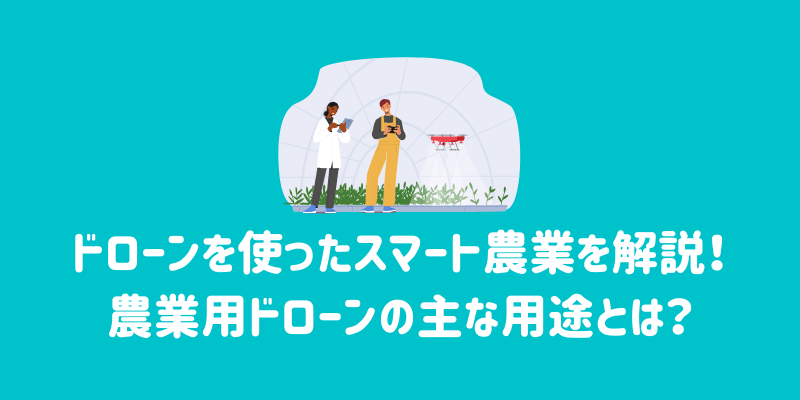
ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?
-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる
-
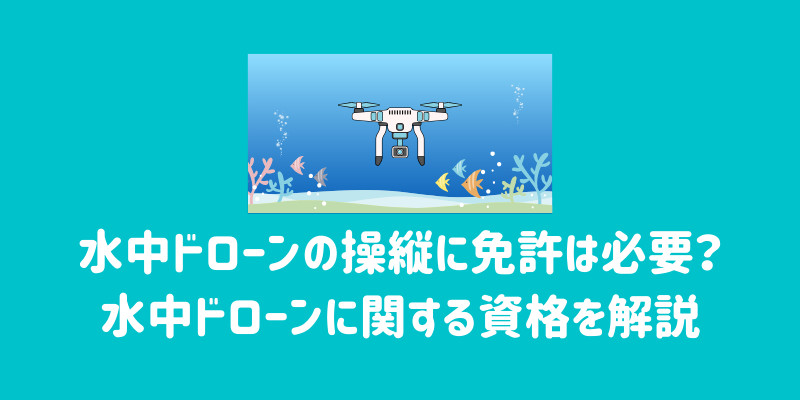
水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説
-
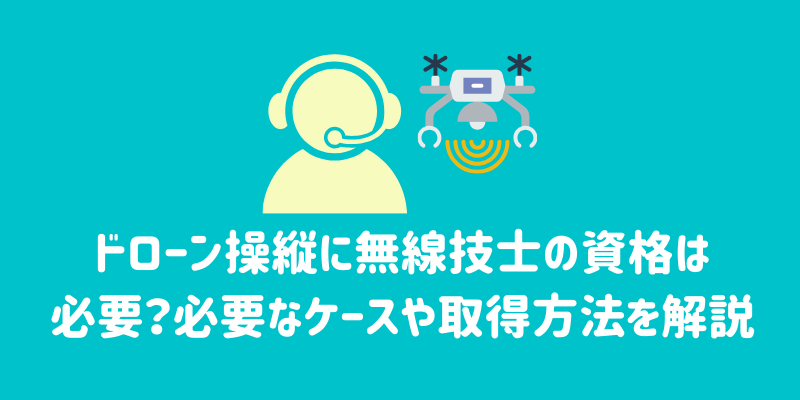
ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!
-
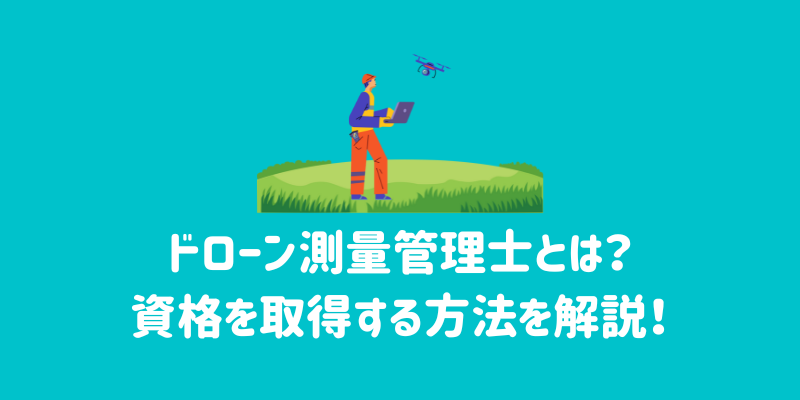
ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!
-
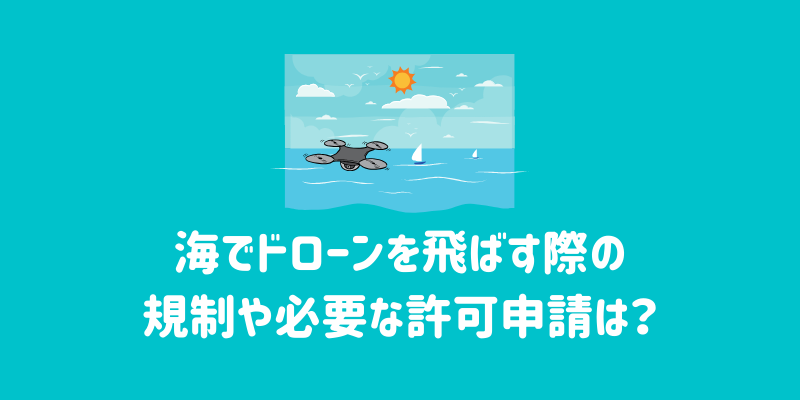
海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説