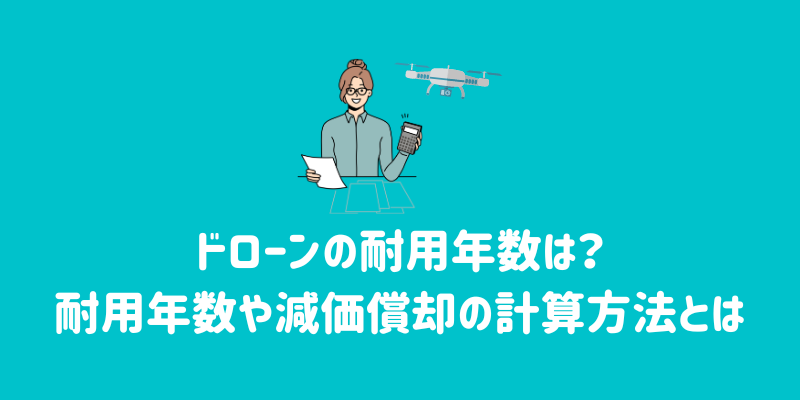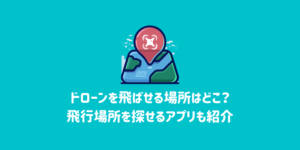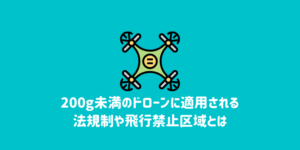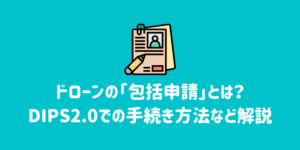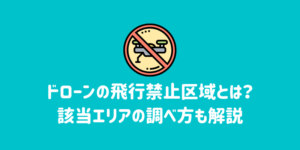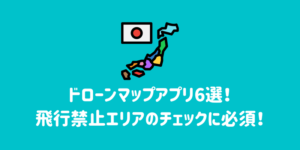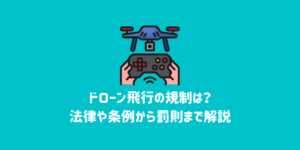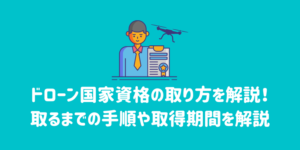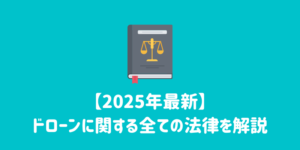業務にドローンを活用している場合、耐用年数に応じて経費計上する「減価償却」が可能です。
しかし、ドローンの耐用年数は用途によって変わるため注意が必要です。
今回はドローンの耐用年数を用途別にご紹介すると共に、中古ドローンの耐用年数やドローンを減価償却する際の計算方法も解説いたします。
減価償却とは
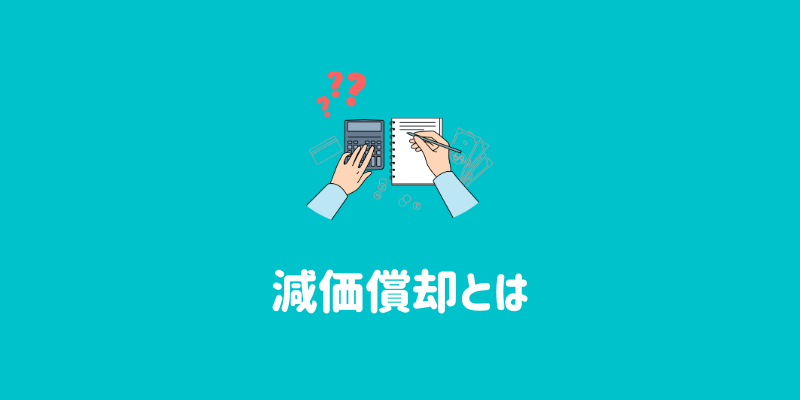
減価償却とは、事業者が所有している資産の取得に伴う費用を経費計上する際の考え方です。
資産の種類(資産区分)ごとに、「耐用年数」という一般的に使用の継続が可能な期間が細かく設定されています。
その期間に応じて、資産の取得価格を分割した金額を毎年経費計上することが可能です。
ドローンは減価償却できる?
業務に使っているドローンも、取得費用が10万円以上であれば原則として減価償却の対象になります。
また、30万円未満のドローンの場合は、一定の要件を満たすことで「少額減価償却資産の特例」を利用できる可能性があります。
少額減価償却資産の特例を利用すると、当期に取得価格の全額を経費計上することが可能です。
参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
10万円未満のドローンは、減価償却はせず一括で経費計上します。
ドローンの耐用年数の概要
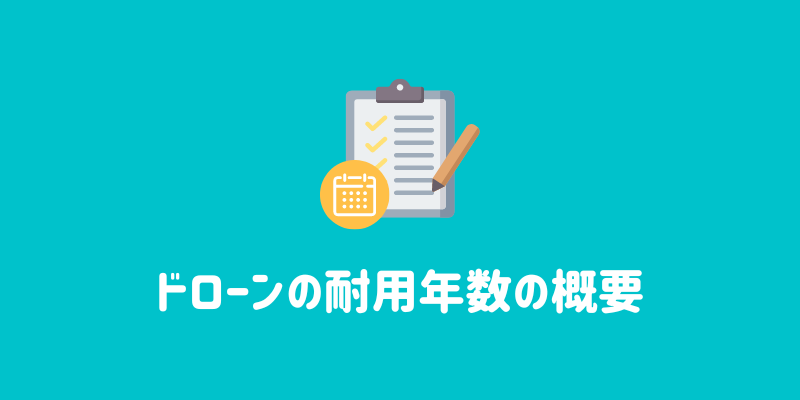
ここでは、ドローンに定められる耐用年数の詳細について解説いたします。
平均的な耐用年数
減価償却におけるドローンの耐用年数は、5~10年とされています。
すべてのドローンが一定の耐用年数で減価償却ができるわけではないため、ドローンの用途ごとに適用される耐用年数を知っておく必要があります。
なお、ドローンは航空法上は「無人航空機」と分類されていますが、税法上の「航空機」とは別物とされており、航空機の耐用年数で減価償却することはできません。
耐用年数に影響を与える要因
所有しているドローンの耐用年数を決める主なポイントは、用途です。
税法上、減価償却の耐用年数については大きく5つの区分に分けられています。
- 建物、建物付属設備
- 構築物、生物
- 車両・運搬具、工具
- 器具・備品
- 機械・装置
業務に使うドローンは上記のうち、「器具・備品」か「機械・装置」の中に含まれる設備のいずれかに定められた耐用年数を適用させる必要があります。
自分または自社が所有するドローンがどれに該当するかは、用途によって変わります。
用途別の耐用年数

ドローンを適切な耐用年数で減価償却するなら、業務のどんな用途にドローンを使うのか?その用途は税法上どの区分に当てはまるのか?を考える必要があります。
ここではドローンの主な用途ごとに、適用されると考えられる資産区分と耐用年数を解説いたします。
趣味用ドローンの耐用年数
個人的な趣味に使っているドローンは、事業とは無関係なものであるため取得費用を経費にすることができません。
そのため、どの資産の耐用年数も適用されません。
空撮用ドローンの耐用年数
空撮用ドローンの耐用年数については、国税庁ホームページにて5年であると明記されています。
専ら撮影に使うドローンは「器具・備品」内に含まれる「光学機器、写真製作機器」のうち、「カメラ」に該当します。
カメラは耐用年数が5年と定められているため、空撮用ドローンもそれが適用されるというのが国税庁の見解です。
農業用ドローンの耐用年数
農業用ドローンを使っている場合、以下の用途にドローンを使っているなら耐用年数は7年となる可能性が高いです。
- 農薬散布
- 肥料散布
- 播種
これらは基本的に資産区分の「機械・装置」に含まれる、「農業用設備」に該当します。
測量用ドローンの耐用年数
土地・建物・道路・橋梁などの測量や測定に使っているドローンの耐用年数は、5年となる可能性が高いです。
資産区分としては「器具・備品」内に含まれる「光学機器、写真製作機器」のうち、「カメラ」に該当します。
ドローンの耐用年数で気をつけるべきポイント
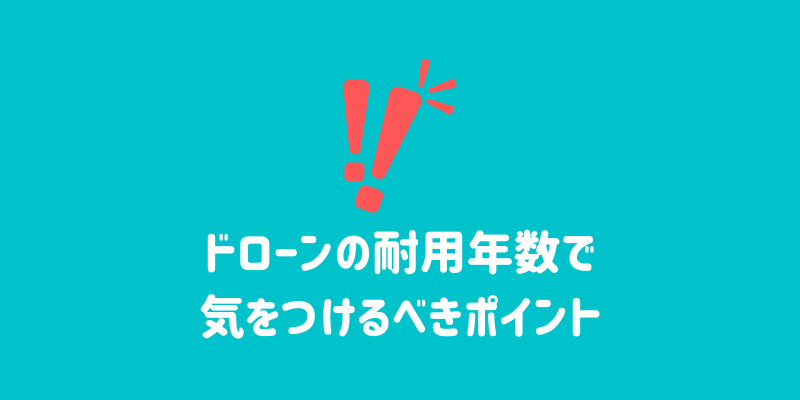
ドローンの耐用年数を判断するうえで、大まかな用途としては同じでも具体的な使い方によって適用される資産区分が変わる可能性に注意が必要です。
例えば農業用ドローンは農薬・肥料の散布や播種など何かを圃場に撒くために使うのであれば、一般的な農業用設備の範疇を超えるとみなされる可能性は低く、耐用年数が7年となります。
しかしカメラを活用した作物の生育状況診断や作物の運搬といった用途にドローンを使う場合、必ずしも農業用設備の耐用年数が適用されるとも断言できません。
また、ドローンであっても人が搭乗できる規模・構造をしている機体は、税法上「航空機」とみなされ、航空機の耐用年数が適用される可能性もある点に注意が必要です。
ドローンの使い方・規模・構造によっては耐用年数に関する見解が先述した内容と異なるため、経費計上の際は税理士など専門家に相談しておくことをおすすめします。
中古ドローンを購入した場合の耐用年数

中古品のドローンを購入のうえ業務に使用した場合、購入時点でそのドローンに残っている価値を考慮しながら、残りの使用期間(耐用年数)を算出しておく必要があります。
期間の算出には、国税庁が提示している「簡便法」という計算方法を使いましょう。
簡便法は、以下2通りの計算方法があります。
- 新品時の耐用年数×20%=中古資産の耐用年数
- 新品時の耐用年数-経過年数+経過年数×20%=中古資産の耐用年数
ただし中古ドローンを業務に使ううえで必要となった修理・改良などの費用が、新品時の取得費用の50%相当を超える場合は、新品と同様の耐用年数が適用されます。
減価償却の計算方法
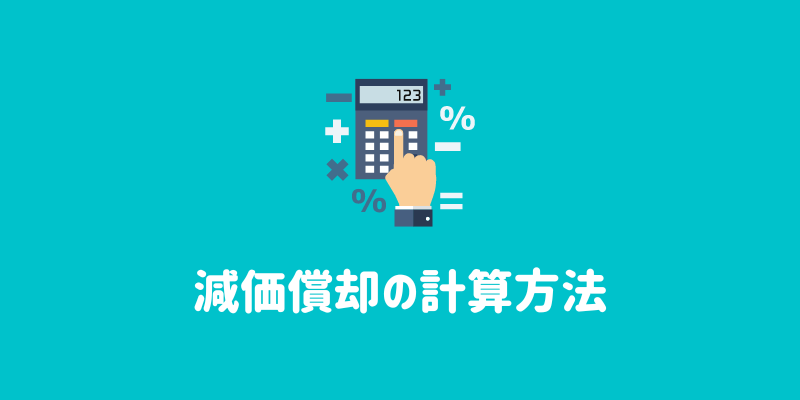
実際にドローンを減価償却する際、耐用年数をもとに計算のうえ経費として計上する金額を求める必要があります。
ここでは、ドローンの減価償却に使える具体的な計算方法をご紹介いたします。
ドローンの減価償却計算式
減価償却の計算方法には、「定額法」と「定額率」があります。
どちらを用いるかは資産ごとに選ぶことができるため、より早く費用化できる計算方法を選ぶケースが一般的です。
定額法
定額法とは、資産の取得価格を耐用年数で割って算出した金額を、毎年減価償却する計算方法です。
具体的な計算式は、以下の通りです。
- 取得価格×定額法の償却率=減価償却費
償却率については、国税庁が公開している「減価償却資産の償却率等表」の「定額法の償却率表」を参考にします。
定率法
定率法は、最初に計上できる減価償却費が大きくなり、それ以降は毎年少しずつ減っていくようになる計算方法です。
定率法で減価償却費を求める際の計算式は、以下の通りです。
- 未償却残高×定率法の償却率=減価償却費
また、減価償却費が償却保証額(=取得価額×耐用年数の保証率)を下回った場合は、以下の計算式を使います。
- 改定取得価額×改定償却率=減価償却費
実例による計算方法の解説
上述した定額法・定率法それぞれの計算式はどのように使うのか、具体的な条件でシミュレーションしてみましょう。
例えば耐用年数5年の撮影用ドローンを200万円で購入した場合、定額法・定率法を用いた減価償却費の計算は以下の通りとなります。
【定額法】
- 200万円×0.2=40万円
→毎年40万円を減価償却する
【定率法】
- 200万円×0.4=80万円(1年目の減価償却費)
- 120万円×0.4=48万円(2年目の減価償却費)
以下、前年の未償却残高から減価償却費を差し引いて計算を繰り返す
ドローンの耐用年数に関するよくある質問
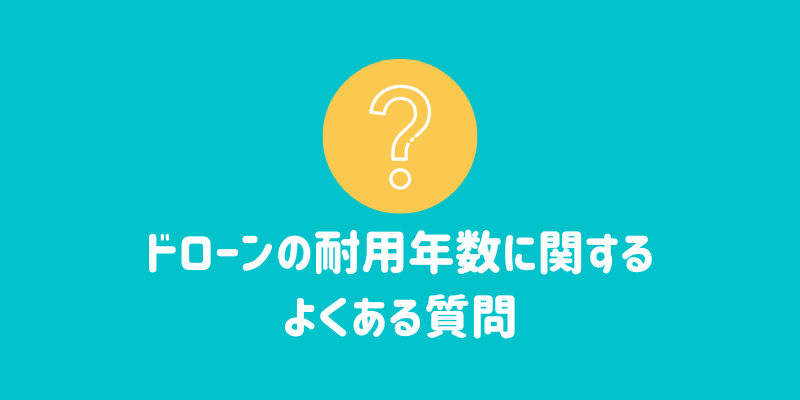
最後に、ドローンの耐用年数に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
ドローンを購入した際の勘定科目は?
ドローンを減価償却する場合、「直接法」と「間接法」のどちらで仕訳するかによって用いる勘定科目が変わります。
200万円の撮影用ドローンを定額法で減価償却する際のそれぞれの仕訳例と勘定科目は、以下の通りです。
【直接法】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 400,000 | 工具器具備品 | 400,000 |
【間接法】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 400,000 | 減価償却累計額 | 400,000 |
djiのドローンの耐用年数は何年ですか?
DJI製ドローンの中でも、空撮用なら5年・農業用なら7年・測量用なら5年を耐用年数として減価償却費を算出します。
使い方によって耐用年数が変わる可能性もあるため、注意が必要です。
運搬用ドローンの耐用年数は?
運搬用ドローンは、資産区分としては「機械・装置」の「運輸に附帯するサービス業用設備」に該当します。
そのため、耐用年数は10年として減価償却費を算出します。
ドローンのバッテリーの耐用年数は何年ですか?
メーカーや使い方によって変わりますが、一般的なドローンのバッテリーは1~2年程度が寿命となっています。
ちなみに、バッテリーはドローンを設備として形成するため・機能を発揮するために必要な「一部分」とみなされる可能性が高いです。
したがって、ドローンとバッテリーは一緒くたにして減価償却するのが適切と考えられます。
まとめ
業務活用しているドローンは、資産として取得価格を経費計上することができます。
その際、減価償却として耐用年数に応じた期間中、毎年取得価格の一部を経費計上しなければなりません。
耐用年数は税法上の資産区分に従って判断する必要がありますが、現状は撮影用ドローン以外の判断基準が明確となっていません。
自社で取り扱っているドローンはどんな資産区分に該当するのか、判断に迷う場合は専門家へ相談することもおすすめです。
ドローンの用途に関して今一度正しく認識できているかを見直し、適切に経費計上できるようにしましょう。