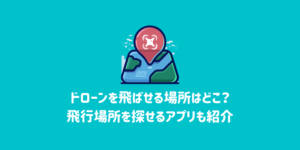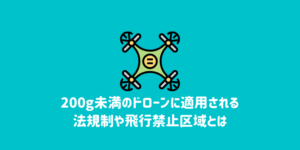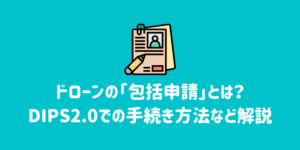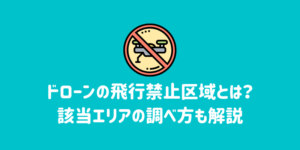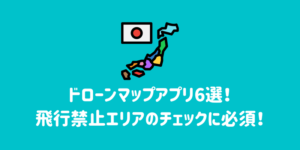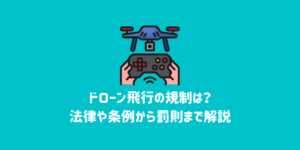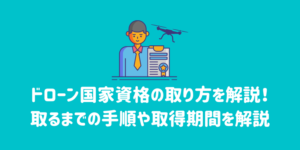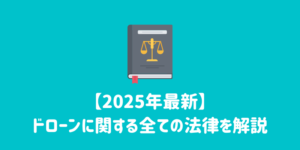ドローンは測量・点検・農業など、実に様々な産業分野への導入が進んでいます。
その中でも、近年特にドローンの需要と導入に対する注目度が高まっている分野が物流です。
2022年12月に施行された改正航空法でレベル4飛行が可能となりドローンを使った宅配サービスの実現が期待されていますが、現状として導入状況はどのようになっているのでしょうか。
今回はドローン宅配の現状・事例と共に、ドローン宅配がもたらすメリットや課題点、今後の展望などについて解説いたします。
宅配業界の現状

近年はインターネットの発達に加えて新型コロナウイルスの流行で外出が制限されていた時期も影響し、ネット通販の需要が大幅に高まっています。
これにより宅配サービスの需要もまた高まっている反面、宅配業界が抱える以下のような課題が顕著となっているのが現状です。
- 少子高齢化による人手不足
- 燃料の高騰によるコストの増幅
- 業界における競争の激化で利益の確保が難化
これらの課題を解決するには、いかに効率的かつコストを抑えた宅配ができるかがカギとなっています。
ドローン宅配の現状

宅配業界が抱える課題解決の有効策として注目を集めているドローン宅配ですが、現時点でどのような普及状況となっているのでしょうか。
導入事例と共に、ドローン宅配の現状について解説いたします。
現状
2022年12月、航空法の改正によりレベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)が解禁されています。
さらに、従来はドローンの飛行形態に関してレベル1~4という4段階の区分が設けられていましたが、レベル3.5飛行という区分も新設されました。
レベル3.5飛行とは、一定の条件を満たせば立入管理措置なしでレベル3飛行の実施が可能となるものです。
目視外飛行に対するハードルが緩和された現在、国内企業によるドローン宅配の実証実験の実施件数は増え続けています。
関連記事:2023年12月に新設したドローンの「レベル3.5飛行」とは?新設された背景や他レベルとの違いまで
事例
2024年4月現在、ドローン宅配を導入した企業の事例を一部ご紹介いたします。
レベル3.5飛行によるドローン郵便配達
2024年3月4日~3月22日の期間に行われた、日本郵便によるドローン配送サービスです。
国内産業用ドローンメーカーのACSLから提供された物流専用ドローン「JP2(通称)」を使い、兵庫県豊岡市の出石郵便局配達区間における配送をレベル3.5飛行で実施しました。
重量2kgの荷物配送にも成功し、中山間地域である出石町での効率的な配送だけでなく災害時の物資運搬にも期待されています。
本事例は試験飛行であり、日本郵便は2024年度以降のドローン配送実用化を目指すとしています。
「買い物弱者」支援のためのドローン配送サービス
長野県伊那市では、2020年8月からドローンを使った中山間地域住民への買い物支援を目的としたドローン配送サービス「ゆうあいマーケット」の本格運用が始まっています。
野菜・鮮魚・日配品・生活雑貨など最大約400品の商品が対象となっており、ケーブルテレビから午前11時までに注文すると当日の夕方までにドローンで商品が配送されるという定額制サービスです。
KDDIスマートドローンにより提供された、最大ペイロード30kgを誇る物資輸送ドローン「PD6B-Type3」を使用しています。
ドローン宅配のメリット

先述した宅配業界が抱える課題の解決に、なぜドローンの導入が有効策といえるのでしょうか。
その理由としては、ドローン宅配がもたらす以下5つのメリットが挙げられます。
渋滞を避けられる
近年のネット通販の需要拡大に伴い、配送トラックの交通量も増加傾向にあります。
これにより交通渋滞が慢性化し、配達の遅延につながるという懸念点が生じます。
ドローンなら上空を飛行しながら荷物を運搬できるため、交通渋滞の影響を一切受けずスムーズな配送が可能です。
ドローン宅配の普及が拡大すればさらなる交通渋滞の緩和に加えて配送中トラックの路上駐車も減少するため、一般車両も快適に通行できるようになります。
スピーディーな配送が可能
トラックなどの車両を使った配送では、交通渋滞の他に建物や地形による影響も受けます。
入り組んだ道にある配送先や舗装されていない道がある配送先、車両の進入が難しい配送先へ荷物を届けるには、どうしてもタイムロスが発生します。
ドローンなら地上のあらゆる障害物の影響も受けず、常に最短距離を通ることができるため効率的で素早い配送が可能です。
運搬時のコスト削減
従来の宅配では、配達員の人件費・トラックの維持費・燃料費といったコストがかかります。
ドローン宅配の社会実装が進めば、その分トラックの維持費や燃料費が削減されます。
また、同じ空輸でも有人航空機に比べてドローンの維持コストは低いため、結果的に配送コスト全体を抑えることが可能です。
交通の便が悪い遠隔地や被災地への迅速な配送
交通状況や地形の影響を受けないドローン宅配は、山間部や離島など交通の便が悪い地域に住む「買い物弱者」への支援にも最適です。
また、大規模な災害が発生して陸路での物資運搬が困難となったり、火災などで地上での物資運搬が危険な状況となったりした際にも、ドローンなら安全かつ迅速に必要な物資を運ぶことができます。
運送業の人手不足を補える
ドローン宅配なら無人での荷物配送が可能であり、宅配業界で深刻化が懸念されている人手不足問題もカバーできます。
また、ドローン宅配では基本的に配送先に荷物を自動的に置く「置き配」となるため、従来の宅配業界における重大な問題のひとつ、「不在による再配達の二度手間」も生じません。
ドローン宅配における技術的な課題点
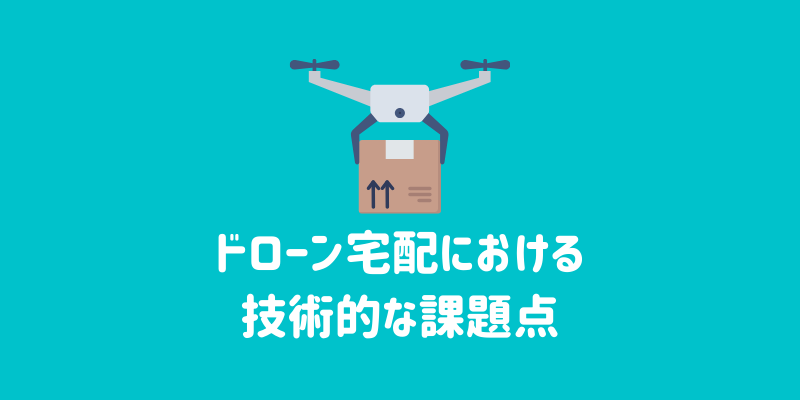
ドローン宅配には様々なメリットが生じますが、現状として技術的な課題点もいくつか残っています。
飛行時間と荷物の重量制限
ドローンの弱点として、稼働可能な時間と積載可能な荷物の重量が限られていることが挙げられます。
トラックなら、トン単位の荷物を積載のうえ長時間配送することが可能です。
一方でドローンは、現在流通している配送用モデルの積載量はkg単位となっており、最長1時間弱までしか連続飛行ができません。
気象条件への対応と安全運航技術
ドローンは上空を飛行するため、雨や風の影響を受けやすいというデメリットもあります。
悪天候の中で飛行させると機体の墜落による事故が発生したり、雨に濡れて機体が故障したりといったリスクを伴います。
そのため、どんな気象条件にも安全な飛行が可能なドローンの開発が求められている状況です。
配送費用
ドローン宅配はトラック配送のように車両や燃料に伴う費用がかからない反面、機体の購入費や許認可手続きに伴う諸費用といったものがかかります。
初期費用が高くなりやすいことに加え、オペレーターの人件費や機体の保守費用といったランニングコストが発生する中で利益を確保することは簡単ではありません。
法律と安全の問題
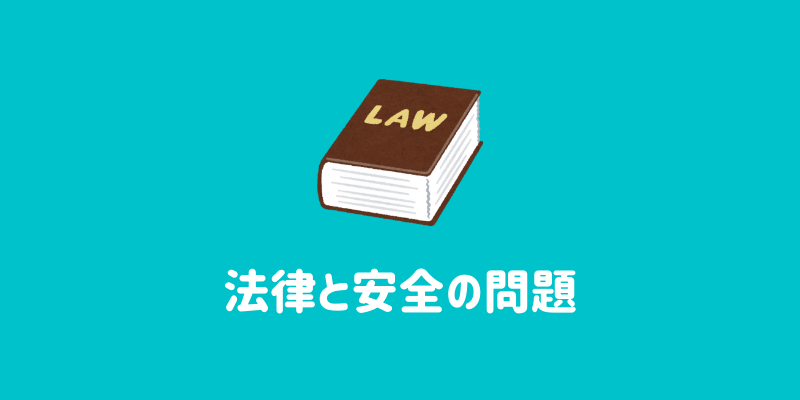
ドローン宅配には技術面の他、法律や安全性という観点でも気に留めるべき問題が残っています。
国内外の法規制の現状
現在はドローン宅配にも対応しうる法整備が国内外で進みつつありますが、ドローン宅配が広く普及するにはまだ時間がかかる見通しです。
例えばアメリカではFAA(アメリカ連邦航空局)はドローン宅配にまつわる規制を設けており、初期と比較して規制が緩和されている傾向にあります。
一方で人口過密地区における落下事故のリスクが懸念されている他、多くの地域で夜間飛行も規制されているのが現状です。
安全性への懸念や利用可能な時間帯の制限から、ドローン宅配の本格運用が可能となるには年単位で時間がかかることでしょう。
プライバシーとセキュリティの課題
ドローン宅配の実用化で懸念されている重大なポイントとして、プライバシー・セキュリティも挙げられます。
多くの産業用ドローンにはカメラが備わっており、飛行データ収集のために撮影した映像がプライバシー侵害につながる恐れもあります。
また、無線機器であるドローンが不正アクセスを受けて不適切な飛行をしないよう、堅牢なセキュリティ対策が必要です。
安全性向上のための取り組み
ドローンの飛行安全性を確保するには、ただ法規制に従うだけでなく事業者側のリテラシー向上やオペレーターの技術向上なども求められます。
運用中も飛行範囲に住まう人々が安心できるように法律に基づく十分な安全措置を考える、地域住民への理解を広めるために説明会などを行う、機体を正確にコントロールできる人材を確保するといった取り組みが重要です。
騒音への対応
常時プロペラを高速回転させて上空を飛ぶドローンは、騒音問題を引き起こす恐れがあります。
特に積載重量がkg単位の大型ドローンは飛行音が大きいため、近隣住民から苦情が生じる可能性を想定した対策も必要です。
今後の展望

宅配業界におけるドローンの今後の展望について、ドローン宅配の普及に必要な条件や宅配業界の今後という観点から解説いたします。
ドローン宅配の普及に向けた条件
ドローン宅配の普及に立ちはだかる数々の課題を解決するには、以下のような取り組みが必要となります。
- 配送用ドローンの開発技術向上
- ドローンの飛行に最適なインフラの構築
- ドローンの操縦技術や安全管理について習得した人材の確保、育成
法改正により無人・有人地帯の目視外飛行が実施しやすくなったとはいえ、より安全なドローン宅配サービスを提供するには飛行経路となる場所の最適化も求められます。
物流各社は2024年~2025年を目処に実用化を目指し実証実験を重ねており、今後いかにして普及の条件を満たすための取り組みを進めていくかに注目したいところです。
宅配業界の将来的な変化
ドローン宅配の普及拡大に伴い、ドローンは従来の配送業者に取って代わる存在となるのでしょうか。
事実としてドローン宅配はトラック配送にはない様々なメリットを持ちますが、完全に従来の配送方法を塗り替える存在になるとも断言できません。
ドローンの開発技術や安全面の影響から、トラックと同程度の範囲・荷物量を配送することは現時点で非常に困難だからです。
ドローン宅配が普及したとして、ドローンに配送可能な範囲・荷物量で運航しつつトラックと人の手による配送も続けて、互いのデメリットを補いながら共存していく形が現実的と考えられます。
ドローン宅配に関するよくある質問
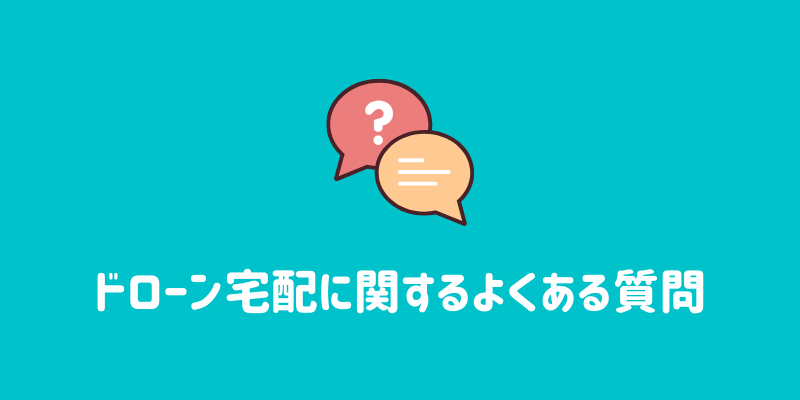
最後に、ドローン宅配に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
ドローン宅配の問題点は?
ドローン宅配が現在抱えている問題点としては、飛行時間や積載重量の限界・運航中の安全性に対する懸念・コストと採算性の問題・プライバシー侵害やセキュリティ対策・騒音問題などが挙げられます。
ドローン宅配の普及を拡大させるには、それらの問題を解決し得る取り組みが必要です。
ドローンの法規制は日本ではどうなっていますか?
2022年12月に施行された改正航空法により、ドローンはレベル4(有人地帯での目視外飛行)までの飛行を実施することが可能となりました。
飛行許可申請や国家資格・機体認証の取得が必要となりますが、宅配業界におけるドローン導入のハードルは少しずつ下がっている状況といえます。
ドローン配送はいつ実用化されるのでしょうか?
ドローン配送について、2024年~2025年の本格的な実用化が進むと見込まれています。
とはいえドローンにもスペックの限界があり、すぐに従来のトラック配送に代わる手段となるわけではありません。
宅配ドローンで運べる重量は?
2024年4月時点で国内に流通している配送用ドローンは、数kg~10kg程度の積載に対応しています。
また、2023年6月に開催されたJapan Drone 2023では積載重量200kgの大型ドローンが発表されており、今後さらに多くの荷物を運べるドローンの流通に期待できます。
参考:ほぼ“空飛ぶ軽トラ”、三菱重工が積載量200kgのドローン | 日経クロステック(xTECH)
まとめ
現状の宅配業界が抱える人手不足・燃料の高騰・交通渋滞による配達遅延といった問題の解決策として、ドローンを導入する企業は増えていくことでしょう。
ただしドローン宅配にも様々な問題点が立ちはだかるため、サービス提供者側が十分に法知識を把握したうえで、安全第一の運行管理体制や人員の確保などが求められます。
問題点は残りつつもそれぞれの解決策は明確化されているため、ドローン宅配が本格的に実用化される未来は訪れると考えらえれます。