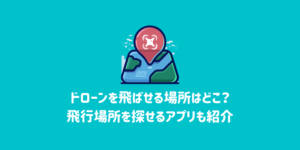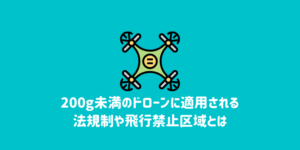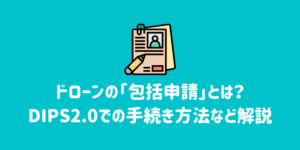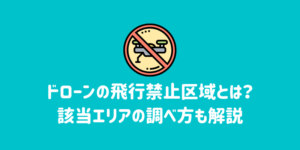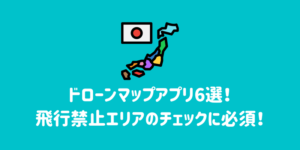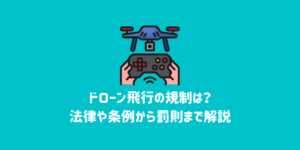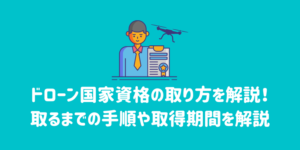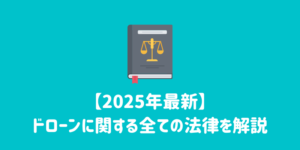KDDIでは山間部や海上といった通信が途切れる環境における遭難者救助について、「航空機型基地局」の実現に向けた取組みを行っています。
超小型の基地局設備を積み込みんだヘリコプターで上空から電波を発射し、現場での携帯電話の使用が可能になるというものです。
2021年1月、鹿児島県甑島にて「航空機型基地局」の実証実験が行われました。
ヘリコプターから電波を発射しエリアをつくる「単独型」、ヘリコプターから地上の可搬型基地局を通して衛星回線とつなぎエリアをつくる「連携型」の通信を成功させることが目的となります。
実証実験は、自然災害により携帯電話通信が断絶して1隻の漁船が海上で行方不明になったというシチュエーションで行われました。
ヘリコプターを使った航空機型基地局で、漂流している漁船の位置を特定したうえで安否確認をしようというものです。
上空で航空機型基地局から電波を発射すると、機体直下の約1.6~2.0Kmの範囲内約1.6~2.0Kmの範囲内で携帯電話が使えるようになります。
携帯電話は通信を行っていなくても常に微弱な電波を発し続けているため、「航空機型基地局」がつくる通信エリアに漂流中の漁船がいたら遭難者が持つ携帯電話からの電波をキャッチし位置の特定ができます。
また、遭難者への通信も可能なため安否確認やメッセージのやり取りもできるとのこと。
海上以外にも地震で倒壊した家屋の下など、上空からの目視による捜索が難しい環境でも遭難者が持っている携帯電話の電波により発見が可能となります。
ヘリコプターを飛ばせない気象や災害地域に有毒ガスが発生している場合、基地局の設備を搭載したドローンによる代用も可能です。
災害地域の状況に応じてヘリコプターとドローンを使い分けることで、より迅速な遭難者の発見につながります。
このように「航空機型基地局」単体で携帯電話が使えるエリアをつくるシステムのことを「単体型」と呼び、2019年11月には新潟県魚沼市での実証実験にて成功を収めています。
一方「連携型」はこれまでに実験を行った「単独型」が更に進化したもので、今回初めて実験に成功したシステムです。
ヘリコプターだけでなく一般の携帯電話の回線とつながり、遭難者が家族や職場などに自分の無事を直接知らせることができるというもの。
この仕組みを使うと、警察や消防などが遭難者のGPS情報を取得することもできます。
救助の手が必要となった場合、詳細な位置情報を防災関係者と共有することで安全かつ迅速な救助を行えるのです。
当初はヘリコプターに携帯電話の基地局を搭載して電波を発射するという発想自体が世の中になく、実験を行うために必要な国交省への届出において所管部署があるのかも不明でした。
また、KDDIはヘリコプターを所有していないため航空会社の協力も絶対とされていましたが、ノウハウのある会社もなかったとのこと。
そこで一旦ヘリコプターの基地局搭載を断念し、2017年12月に屋久島にてドローンを用いた航空機型基地局の実証実験を行いました。
この実験を機に国交省と「航空機型基地局」というアイディアを共通で認識し合い、中日航空とのパートナー連携も実現。
中日航空はヘリコプターに基地局設備を搭載して電波を発射できるのか、段階を踏みながら何度も試験を繰り返してノウハウを確立していったとのことです。
そうして2019年に行った魚沼での実証実験を経て、甑島にて行われた実証実験へと繋がります。
この実験で航空機型基地局の実現はより近づいたと言えますが、KDDIはそれを「いついかなるときでも使えるようにする仕様とオペレーションにする必要がある」と語ります。
今後も改善を繰り返していくことで、航空機型基地局をより実践的なものにしていくと述べました。